「自分には相続税がかかるのだろうか?」「相続の準備って、何から始めたらいいんだろう?」
ご自身の財産やご家族のことを考えたとき、漠然とした不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。特に、ご自身の資産が一定額以上ある場合、「相続税」の問題は避けては通れません。
この記事では、将来的に相続税がかかる可能性のある方(いわゆる「資産家」と呼ばれる方々)に向けて、後悔しないための生前対策の第一歩となる「相続税に強い税理士の選び方」を、3つの重要なポイントに絞って、専門家の視点から分かりやすく解説します。
この記事を最後までお読みいただければ、あなたに最適な専門家を見つけ、円満な相続に向けた具体的な準備を始めることができるはずです。
目次
1. そもそも相続税は誰にでもかかるわけではない
まず、大前提として知っておいていただきたいのは、相続税はすべての人にかかる税金ではないということです。
国税庁の統計によると、令和4年(2022年)に亡くなられた方のうち、相続税の課税対象となったのは全体の約9.6%でした。つまり、約90%の方は、相続税を納める必要がなかったのです。
この数字だけを見ると、「なんだ、自分も大丈夫だろう」と思われるかもしれません。
しかし、もしあなたが、その「約9.6%」に該当する可能性があるのなら、話は大きく変わります。相続税は、対策をしているかどうかで、納税額が数百万円、場合によっては数千万円単位で変わることも珍しくない、非常に専門性の高い税金だからです。
そして、その対策は、相続が起きてから、つまり、亡くなってからでは打てる手が非常に限られてしまいます。だからこそ、元気なうちから準備を進める「生前対策」が何よりも重要になるのです。
2. なぜ「生前の」相続税対策が重要なのか?
「相続対策なんて、まだ先の話だ」と思われるかもしれませんが、それは大きな誤解です。相続税対策は、時間をかければかけるほど、選択肢が増え、より効果的な対策を講じることが可能になります。
生前対策を行うことには、主に3つの大きなメリットがあります。
メリット1:節税効果を最大化できる
相続税の節税対策には、暦年贈与や生命保険の非課税枠の活用、不動産評価額の引き下げなど、様々な方法があります。これらの多くは、年単位で計画的に実行することで初めて効果を発揮するものです。例えば、年間110万円までの非課税贈与(暦年贈与)は、10年続ければ1100万円もの資産を非課税で次の世代に移すことができます。相続発生直前に慌てて多額の贈与をしても、税務署から否認されてしまうリスクがあります。
メリット2:納税資金の準備ができる
相続税は、原則として相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、現金で一括納付しなければなりません。遺産のほとんどが不動産で、手元に現金がない場合、納税資金を準備するために、大切なご自宅や土地を売却せざるを得ないケースもあります。生前から納税額をシミュレーションし、計画的に納税資金を準備しておくことで、このような事態を避けることができます。
メリット3:家族間の争いを防ぐ(争族対策)
相続が「争族」になってしまう最大の原因は、遺産の分け方(遺産分割)がスムーズに進まないことです。生前に誰がどの財産を相続するのか、なぜそのように分けるのか、ご自身の意思を「遺言書」という形で明確にしておくことは、残された家族が円満に手続きを進めるための何よりの道しるべとなります。また、生前対策を通じて財産の内容が整理されることで、遺産分割の話し合いも格段に進めやすくなります。
このように、生前の相続対策は、単なる節税のためだけではなく、ご自身の財産と家族の未来を守るための、非常に重要な準備なのです。
3. 相続税の相談は誰にするべきか?
では、具体的に相続税の対策を始めようと思ったとき、誰に相談すればよいのでしょうか。
相続に関わる専門家には、私たち司法書士のほか、弁護士、行政書士、そして税理士などがいます。また、銀行や信託銀行、保険会社、不動産会社なども相続相談の窓口を設けています。
それぞれに専門分野があり、役割が異なります。
- 弁護士:相続トラブルが起きてしまった場合の交渉や調停、裁判の代理人。
- 司法書士:不動産の名義変更(相続登記)や、遺言書作成のサポート、成年後見など。
- 行政書士:遺産分割協議書の作成や、各種許認可手続きなど。
そして、相続「税」の計算、申告、そして最も重要な「節税対策」については、税理士が専門家です。
私たち司法書士も、相続登記などを通じて相続税に関する知識は有していますが、複雑な財産評価や税額計算、最新の税制を踏まえた最適な節税プランの提案は、税金のプロフェッショナルである税理士には及びません。
したがって、あなたが相続税の納税対象者であり、本格的な対策を考えているのであれば、税理士に相談することをおすすめします。
4. 【最重要】失敗しない相続税理士選び・3つの鉄則
「税理士なら誰でもいい」というわけではありません。実は、税理士にも得意な分野とそうでない分野があります。会社の顧問税理士に相続税の相談をしたら、思ったような提案が受けられなかった、という話もよく耳にします。
ここでは、信頼できる税理士を見つけるための3つの鉄則をご紹介します。
鉄則①:大前提として「税理士資格」を持っているか確認する
当たり前のことですが、非常に重要です。相続税の申告書作成や税務代理は、税理士の独占業務です。無資格のコンサルタントなどがこれを行うことは、法律で禁じられています。
「相続専門コンサルタント」や「資産相談センター」といった肩書で相談業務を行っている業者の中には、税理士資格を持たない担当者が窓口となっているケースもあります。このような場合、結局は提携先の税理士に業務を外注することになり、伝言ゲームになってしまってあなたの真意が伝わりにくくなったり、中間マージンが発生して費用が割高になったりする可能性があります。
相談する相手が本当に税理士かどうかは、「税理士証票」の提示を求めたり、日本税理士会連合会のウェブサイトで検索したりすることで確認できます。まずは、国家資格を持った専門家であることを必ず確認しましょう。
鉄則②:「相続税の申告実績」が豊富な専門家を選ぶ
税理士の業務範囲は、法人税、所得税、消費税など非常に多岐にわたります。そのため、普段は企業の経理や確定申告をメインに扱っている税理士が、相続税に精通しているとは限りません。
相続税の計算では、特に「土地の評価」が非常に重要かつ複雑です。土地の形状や立地、周辺環境などによって評価額は大きく変わり、これが納税額に直結します。経験豊富な税理士は、土地を最大限減額評価できるノウハウ(小規模宅地等の特例の適用など)を持っています。
良い税理士を見極めるためには、相談の際に「相続税の申告を年間で何件くらい扱っていますか?」と、具体的な実績数を聞いてみるのが有効です。一般的に、年間10件以上扱っていれば、経験豊富と判断してよいでしょう。また、「どのような節税提案の実績がありますか?」といった質問を投げかけてみるのもおすすめです。
鉄則③:間に誰も挟まず「直接相談」でき、相性が良いこと
専門家がお客様にとって最善の提案をするためには、財産の状況だけでなく、ご家族構成やそれぞれの想い、将来に対するご希望など、背景にある様々な事情を直接お伺いすることが不可欠です。
他の業者や紹介会社が間に入り、担当者からの又聞きで税理士に情報が伝わるような体制では、こうした機微な情報が抜け落ちてしまいがちです。あなたの家族の未来を決める大切な相談です。必ず、担当する税理士本人と直接顔を合わせて話せる事務所を選びましょう。
そして、最後の決め手は「相性」です。生前対策は、長いお付き合いになることもあります。
- こちらの話を親身になって聞いてくれるか
- 専門用語を使わず、分かりやすく説明してくれるか
- 質問しやすい雰囲気か
- 料金体系が明確か
初回の相談などを利用して、あなたが「この先生なら信頼できる」「安心して任せられる」と感じられるかどうか、ご自身の感覚を大切にしてください。
5. まとめ:最適な専門家選びが、円満な相続への第一歩
今回は、相続税がかかる方向けの生前対策として、最も重要な「税理士選び」について解説しました。
- 相続税対策の相談は、税理士にする
- 税理士を選ぶ際は、①資格、②相続税の実績、③直接相談できるか、の3点を確認する
このポイントを押さえることが、あなたの相続対策を成功させるための第一歩です。
信頼できる税理士と共に相続税対策の道筋をつけることで、初めて「争族にしないための遺言書作成」や「スムーズな手続きのための財産整理」といった、他の相続対策も安心して進めていくことができます。
もし、あなたがこの記事で解説したような条件を満たす税理士の心当たりがなく、誰に相談して良いか分からないという状況でしたら、ぜひ一度当事務所にご相談ください。 当事務所は遺産相続に特化した司法書士事務所として、相続登記や遺言書作成のサポートを主業務としておりますが、お客様のご希望に応じて、相続専門の税理士を無料でご紹介することも可能です。
この記事が、あなたの不安を解消し、未来への準備を進める一助となれば幸いです。
なお、相続税がかかる方は、下記の記事を参考にしてください。







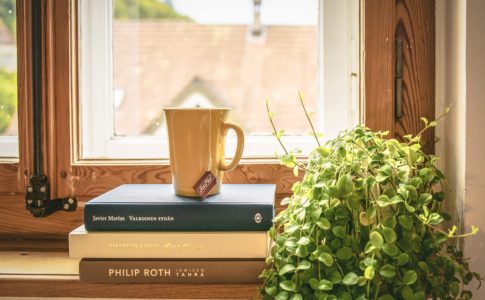










コメントを残す