生命保険は、相続税の対策において非常に有効な方法となります。
現預金を生命保険に移しておくだけで、相続税の非課税枠が活用でき、さらに資産運用、各種保障等が付きますので、相続税がかかる人なら必ず検討しておきたい項目の一つです。
ここでは、相続税と生命保険の関係をご説明してきます。
1.相続税の基本〜基礎控除額〜
まずは、相続税の基本を確認します。
相続税はだれにでもかかる税金ではありません。国税庁の調査によると、平成28年度、全体の92%の人は相続税を納める必要がなかったとの統計がでています。
なぜこのような結果になるのかというと、相続税には「基礎控除」とよばれる多額の控除があるからです。相続をする財産がこの基礎控除額以下だった場合は、相続税を申告する必要も、納付する必要もありません。
相続税の基礎控除額の計算は次のとおりです(平成27年度~)
★3000万円+600万円×法定相続人の人数
たとえば、相続人が子供3人だったとすると
3000万円+1800万円=4800万円の基礎控除となります。
相続財産の総額がこの基礎控除額以下だった場合は、相続税を申告する必要はありません。
なお、相続財産の評価額は、次の方法でざっくりと算出してみてください。
- 預貯金→現在の額
- 不動産→固定資産納税通知書に記載されている「評価額」
- 有価証券→現在の評価
相続財産を正確に評価するためには、複雑な計算が必要になります。たとえば、土地の評価方法には路線価方式と倍率方式とよばれる計算方法があり、その計算をするためには税務上の専門知識が必要になります。ここでは、一般の方でも計算しやすく、一応の目安になる評価額を算出するために、上記の計算方法をおすすめしています。
★この計算で、相続財産の評価額が相続税の基礎控除額を「超える」もしくは、「超えそう」だった場合は、次項以下のページを確認した後、相続税対策をする専門家にご相談に行かれることをおすすめします。
2.生命保険の非課税枠を活用
生命保険の死亡保険金には、一定額の非課税枠がありますので、これを相続税対策に活用できます。
この一定額の非課税枠の計算方法は、つぎのとおりです。
★相続人の人数×500万円
たとえば、相続人がABCの3人だった場合、非課税枠は1500万円となります。
保険金の受取人は、単純にABCで各500万円とすることもできるし、A一人に1500万円とすることもできます。
2−1.非課税枠を活用できる生命保険とは
非課税枠を活用できる生命保険は、死亡を原因として支払われる保険金である必要があります(終身保険)。その他の、医療保険、入院保険は、死亡を原因として支払われる保険金ではありませんので、非課税枠を活用できません。
2−2.保険契約者と受取人に注意
また、保険契約者、保険料負担者、保険金受取人、にも留意しておきましょう。
相続税の非課税枠を活用するには、被保険者、保険料負担者は被相続人、保険金受取人は、相続人である必要があります。
【相続税の非課税枠を活用できる生命保険契約】
被相続人:夫
| 被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 |
| 夫 | 夫 | 妻 |
その他の契約では、課税される税金の種類が変わってきます。
【所得税が課税される生命保険契約】
被相続人:夫
| 被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 |
| 夫 | 妻 | 妻 |
【贈与税が課税される生命保険契約】
被相続人:夫
| 被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 |
| 夫 | 妻 | 子 |
3.まとめ
ここでは、生命保険と相続税の関係を見てきましたが、いかがだったでしょうか。
相続税対策として、生命保険は非常に有効な方法となります。
単純に持っている現預金を保険に変えておくだけでも節税になりますし、資産運用、各種保障が付いてくる点も、メリットになるでしょう。
まずは、ご自身に相続税がかかるのか、一度試算されてみることをおすすめします。
ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。







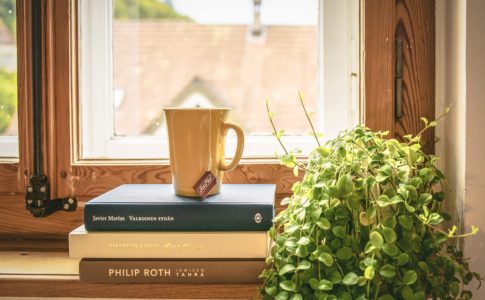









である必要がある。