「親が亡くなったら、相続税って必ず払うものなの?」
「うちはそんなに財産がないから関係ないと思っているけど、本当かな?」
ご家族の相続を経験する可能性は誰にでもありますが、相続税については漠然とした不安や疑問をお持ちの方が多いのではないでしょうか。
結論から言うと、相続税は、すべての人に関係する税金ではありません。 多くの場合は、相続税を支払う必要がないのです。
しかし、いざという時に「知らなかった」では済まされないのがお金の話。ご自身が対象になるのかどうか、基本的な知識を持っておくだけで、余計な心配をせず、スムーズに手続きを進めることができます。
この記事では、相続税の計算方法の全体像を、順を追って分かりやすく解説します。この記事を読み終える頃には、次のことが理解できるはずです。
- 自分は相続税の申告が必要かどうかの判断基準
- 相続税がどのように計算されるのかという全体的な流れ
- 納税額を抑えるための重要なポイント
- 困ったときに誰に相談すればよいか
専門用語をできるだけ避け、具体例を交えながら解説しますので、ぜひ最後までお付き合いください。
目次
1. まずはここから!相続税がかかるかどうかの分かれ道「基礎控除額」
相続税の計算で、何よりも先に確認すべきことがあります。それは、「遺産の総額が、相続税の基礎控除額を超えるかどうか」です。
相続税は、亡くなった方(被相続人)が遺した財産のすべてにかかるわけではありません。「この金額までであれば、税金はかかりませんよ」という非課税のラインが設けられています。この非課税枠のことを「基礎控除額」と呼びます。
つまり、遺産の総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税を納める必要も、税務署に申告をする必要もありません。手続き上、何もしなくてよいということになります。
相続税の基礎控除額の計算式
では、その基礎控除額はいくらなのでしょうか。計算式は非常にシンプルです。
◆ 基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
この計算式にある「法定相続人」とは、民法で定められた、遺産を相続する権利を持つ人のことです。誰が法定相続人になるかは、家族構成によって決まります。
- 亡くなった方の配偶者(夫または妻)は、常に法定相続人になります。
- 配偶者以外の人は、次の順位で相続人になります。
- 第1順位: 子供(子供が先に亡くなっている場合は孫)
- 第2順位: 親(親が先に亡くなっている場合は祖父母)
- 第3順位: 兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪)
第1順位の人がいる場合、第2順位、第3順位の人は相続人にはなれません。
具体的な家族構成で基礎控除額を計算してみよう
言葉だけでは分かりにくいので、具体的な例で計算してみましょう。
【ケース1】相続人が「妻と子供2人」の場合
- 法定相続人の数:3人(妻、長男、長女)
- 計算式:3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
- この場合、遺産の総額が4,800万円以下であれば、相続税の申告・納税は不要です。
【ケース2】相続人が「子供1人」の場合
- 法定相続人の数:1人
- 計算式:3,000万円 + (600万円 × 1人) = 3,600万円
- 遺産の総額が3,600万円以下であれば、相続税はかかりません。
【ケース3】相続人が「妻のみ(子供や親、兄弟はいない)」の場合
- 法定相続人の数:1人
- 計算式:3,000万円 + (600万円 × 1人) = 3,600万円
このように、まずはご自身の家族構成から法定相続人の数を確定させ、基礎控除額を計算することが最初のステップです。
「遺産の総額」には何が含まれる?
基礎控除額と比べる「遺産の総額」には、どのようなものが含まれるのでしょうか。基本的には、亡くなった方が所有していた金銭的な価値のあるものすべてが対象です。
- プラスの財産:
- 現金、預貯金
- 土地、建物などの不動産
- 株式、投資信託などの有価証券
- 自動車、貴金属、骨董品
- 生命保険金、死亡退職金(これらは「みなし相続財産」と呼ばれ、一定の非課税枠があります)
- マイナスの財産:
- 借金、ローン
- 未払いの税金や医療費
遺産の総額を計算する際は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて計算します。
2. 基礎控除を超えたらどうなる?相続税額の計算5ステップ
遺産の総額が基礎控除額を上回る場合は、相続税の申告と納税が必要になります。ここからは、実際に納める税額がどのように決まるのか、5つのステップに分けて見ていきましょう。
少し複雑に感じるかもしれませんが、「こういう流れで計算するんだな」という全体像を掴むことを目標に読み進めてみてください。
【計算モデルケース】
- 亡くなった人: 夫
- 遺産総額: 8,000万円
- 相続人: 妻、子供2人(計3人)
- 実際の財産取得割合: 妻が1/2、子供がそれぞれ1/4ずつ
ステップ1:課税遺産総額を計算する
まず、遺産の総額から基礎控除額を差し引きます。この税金の対象となる金額を**「課税遺産総額」**と呼びます。
- 基礎控除額: 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
- 課税遺産総額: 8,000万円 - 4,800万円 = 3,200万円
この3,200万円を元に、税額を計算していくことになります。
ステップ2:法定相続分で仮に按分する
次に、ステップ1で計算した課税遺産総額を、法律で定められた相続割合(法定相続分)で一度、仮に分けてみます。
法定相続分
配偶者と子供の場合:配偶者 1/2、子供 1/2(子供が複数いる場合は均等に分ける)
モデルケースでは、妻1/2、子供2人で1/2(つまり各1/4)となります。
- 妻: 3,200万円 × 1/2 = 1,600万円
- 子供A: 3,200万円 × 1/4 = 800万円
- 子供B: 3,200万円 × 1/4 = 800万円
これはあくまで税額を計算するための一時的な分割です。実際の遺産の分け方とは関係ありません。
ステップ3:仮の相続税額を計算する
ステップ2で分けた各人の金額に、相続税の税率を掛けて、それぞれの仮の税額を計算します。税率は、金額が大きくなるほど高くなる累進課税方式です。
【相続税の速算表】
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | – |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この表を使って、モデルケースの税額を計算します。
- 妻: 1,600万円 × 15% - 50万円 = 190万円
- 子供A: 800万円 × 10% = 80万円
- 子供B: 800万円 × 10% = 80万円
ステップ4:相続税の総額を計算する
ステップ3で計算した各人の仮の税額を、すべて合計します。これが、この相続全体でかかる「相続税の総額」となります。
- 相続税の総額: 190万円 + 80万円 + 80万円 = 350万円
ステップ5:実際に納める各人の相続税額を計算する
最後に、ステップ4で計算した「相続税の総額」を、実際に財産を取得した割合に応じて割り振ります。
モデルケースでは、実際の取得割合も法定相続分と同じ(妻1/2、子供各1/4)でしたので、
- 妻が実際に納める税額: 350万円 × 1/2 = 175万円
- 子供Aが実際に納める税額: 350万円 × 1/4 = 87.5万円
- 子供Bが実際に納める税額: 350万円 × 1/4 = 87.5万円
これが、各種控除を適用する前の、各人が納めるべき相続税額となります。もし遺言などで「妻がすべての財産を相続する」となっていた場合は、相続税の総額350万円をすべて妻が負担することになります。
3. 納税額が大きく変わる!知っておきたい特例と税額控除
ステップ5までお疲れ様でした。しかし、計算はまだ終わりではありません。実は、ここからが非常に重要です。
相続税には、様々な事情に応じて税金の負担を軽くするための「税額控除」や「特例」という制度が用意されています。これらを適用することで、最終的な納税額が大きく減額されたり、ゼロになったりすることも珍しくありません。
ここでは、代表的なものをいくつかご紹介します。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
最も影響が大きいのが、この制度です。配偶者が相続した財産については、
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
の、いずれか多い金額まで相続税がかからないという非常に強力な制度です。
先ほどのモデルケースで計算した妻の納税額は175万円でしたが、この制度を使えば、妻が相続した財産は4,000万円(8,000万円×1/2)であり、1億6,000万円以下なので、妻の納税額は0円になります。
ただし、この制度を適用するためには、納税額がゼロでも相続税の申告は必要なので注意が必要です。
小規模宅地等の特例
亡くなった方が住んでいた土地や、事業をしていた土地を相続した場合、その土地の評価額を最大で80%も減額できる制度です。
例えば、評価額5,000万円の自宅の土地にこの特例が適用できれば、評価額は1,000万円(5,000万円×20%)として相続税を計算できます。遺産総額に占める不動産の割合が大きい場合、この特例を使えるかどうかで納税額が劇的に変わります。ただし、適用要件は非常に複雑なため、専門家の判断が不可欠です。
その他の控除
- 未成年者控除: 相続人が20歳未満の場合に適用できます。
- 障害者控除: 相置人が障害者の場合に適用できます。
- 相次相続控除: 10年以内に二度目の相続(例:父の相続の後、母が亡くなった)が発生した場合に、税負担を軽減する制度です。
これらの特例や控除を正しく適用することが、適切な納税額を算出する上で極めて重要になります。
4. 相続税の申告は誰に頼む?司法書士と税理士の役割分担
ここまで読んで、「計算が複雑で、自分たちだけでやるのは難しそうだ」と感じた方も多いのではないでしょうか。その感覚は、決して間違いではありません。
相続手続きには、様々な専門家が関わりますが、こと相続税に関しては、税理士が専門家となります。
- 税理士の役割: 税金のプロフェッショナルです。相続税の複雑な計算、特例適用の判断、税務署への申告手続きをすべて代行してくれます。
- 司法書士の役割: 相続手続きの専門家です。不動産の名義変更(相続登記)や、銀行口座の解約、遺産分割協議書の作成、家庭裁判所への手続きなどを担当します。
つまり、「相続税の申告・納税」は税理士、「不動産の名義変更などの相続手続き」は司法書士、という役割分担になります。
相続税の申告が必要なケースでは、財産の評価や特例の適用判断に専門的な知識が求められます。申告内容に誤りがあると、後から追加で税金を納める(追徴課税)ことになるリスクもあります。そのため、基礎控除額を超えることが分かった時点で、早めに税理士に相談することをおすすめします。
なお、当事務所にご依頼いただいたお客様で、相続税の申告が必要だと判断された場合には、私たちが信頼できる相続専門の税理士を無料でご紹介することも可能です。相続に関する手続きをワンストップで進められるようサポートいたしますので、ご安心ください(紹介料は無料ですが、税理士報酬は別途発生します)。
参考記事:【司法書士が解説】相続税がかかる人必見!失敗しない税理士選び3つのポイントと生前対策の重要性
まとめ
今回は、相続税の計算方法について、その全体像を解説しました。最後に、この記事の重要なポイントを振り返ります。
- 相続税は全員が対象ではなく、遺産総額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除額以下なら申告不要。
- 基礎控除額を超える場合、5つのステップで納税額を計算するが、その計算は複雑。
- 「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、納税額を大きく減らせる制度の活用がカギ。
- 相続税の申告は専門知識が必要なため、税理士への相談が最も確実で安心な方法。
相続は、多くの方にとって初めての経験です。何から手をつけていいか分からず、不安に思うのは当然のことです。まずは、ご自身の状況が相続税の対象になるのかどうか、本記事を参考に確認してみてください。
そして、もし手続きの進め方や、専門家への相談で迷うことがあれば、私たち司法書士にお気軽にご相談ください。相続手続き全体の流れを整理し、お客様にとって最善の道筋をご提案させていただきます。







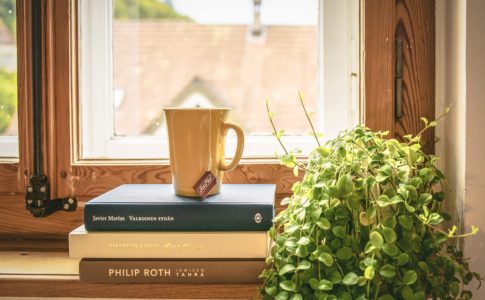










コメントを残す