公正証書遺言とは、法律の専門家である公証人の関与のもと作成する遺言のことです。遺言の種類の中では、もっとも確実性のある遺言といえます。
ここでは、公正証書遺言の作成方法・費用。必要書類について解説していきます。
目次
1.公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証役場に在籍する公証人に作成してもらう遺言のことです。法律の専門家である公証人が関与し作成しますので、遺言がその形式の不備によって無効となることはまずありえません。
また、作成した遺言は、公証役場に長期間保管されますので、紛失の心配がありません。
したがって、遺言の種類の中では、もっとも確実性のある遺言といえます。
1-1.公証人とは
公証人とは、法律の専門家で、書類等の「公証」をする国家機関です。公証人は、裁判官や検察官など、法律実務を長く努めた方の中から法務大臣が任命をします。
1-2.公証役場とは
公証人が在籍し執務をする場所を「公証役場」と呼びます。公証役場は全国各地にありますが、必ずしも市区町村に1つあるわけではありません。自分の住んでいる市区町村にない場合には、近隣の市区町村の公証役場を探してみましょう。
1-3.公正証書とは
公正証書とは、当事者からの依頼により、公証人が作成する文書のことです。遺言、財産分与契約書、信託契約書、任意後見契約書等、様々な書類を公正証書として作成することができます。
公証人が作成した公正証書は、極めて高い証拠力があり、紛争の発生を未然に防ぐ役割を果たします。
2.公正証書遺言の作成件数
日本公証人連合会が公開している情報によると、平成31年1月から令和元年12月までの1年間に全国で作成された公正証書遺言は、11万3,137件でした。
また、過去10年間の推移を見るとその件数は増加傾向にあり、遺言に関心を持たれている方が増えていることが分かります。当事務所においても、遺言の相談件数が年々増加しています。
| 暦年 | 公正証書遺言作成の件数 |
| 平成22年 | 81,984件 |
| 平成23年 | 78,754件 |
| 平成24年 | 88,156件 |
| 平成25年 | 96,020件 |
| 平成26年 | 104,490件 |
| 平成27年 | 110,778件 |
| 平成28年 | 105,350件 |
| 平成29年 | 110,191件 |
| 平成30年 | 110,471件 |
| 令和1年 | 113,137件 |
3.公正証書遺言の作成方法
3-1.必要書類の収集
公正証書遺言に必要な書類は次のとおりです。
- 遺言者の実印・印鑑証明書
遺言者の本人確認資料として必要です。 - 遺言者と相続人(財産を譲り渡す人のみ)との関係がわかる戸籍謄本
相続人が甥、姪など、遺言者の戸籍謄本だけでは続柄が不明の場合は、その続柄の分かる戸籍謄本も必要です。 - 受遺者(相続人以外で財産を譲り受ける人)の住民票
遺言者の財産を相続人以外の人に譲る場合に必要です。この財産を譲り受ける人を「受遺者」といいます。なお、受遺者が法人の場合は、その法人の登記事項証明書が必要です。 - 固定資産税納税通知書
不動産を遺言に記載する場合に必要です。 - 不動産の登記簿謄本
不動産を遺言に記載する場合に必要です。 - その他、遺言に記載する財産を特定する資料
そのほかの財産を遺言に記載する場合は、その財産を特定する資料が必要です。たとえば、預貯金の通帳、有価証券の明細書、保険証券、自動車登録証等が該当します。 - 証人の確認資料
証人2人の本人確認資料が必要です。免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書等が本人確認資料として、使用できます。 - 遺言執行者の確認資料
遺言に遺言執行者を記載する場合は、その方の住所、職業、氏名、生年月日が確認できる資料が必要です。遺言執行者が法人の場合は、法人の登記事項証明書が必要です。
3-2.証人2名が必要
公正証書遺言には、証人2名の立ち会いが必要です。証人は、次のような欠格事由に当たらない人を選びます(民法974条)。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
以上の方は、証人とはなれません。
なお、ご自分で証人を探すことが難しければ、公証役場に有料で紹介してもらうこともできます。
3-3.公正証書遺言作成の手順
公正証書遺言の作成方法は、次の民法の条文に定められています。
民法第969条(公正証書遺言)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人2人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
法令検索:民法
具体的には、事前準備を含めて次のような手順になります。
- 公証役場へ連絡
公正証書遺言を作成するための公証役場の管轄は決まりはありません。ご自身が行きやすい公証役場に連絡しましょう。 - 公証人との面談・遺言内容の確定
必要書類を揃えて公証役場へ出向きます。公証人へご自身の遺言の内容を伝えましょう。なお、1回の面談で遺言の内容が定まらなければ、公証人との打ち合わせを重ねます。 - 遺言文案の作成・確認
②の内容をもとに、公証人が遺言の文案を作成してくれます。この文案がそのま遺言になりますので、ご自身の希望に沿っているかきちんと確認して、公証人に返答をしましょう。 - 公正証書遺言の作成
③の遺言文案をもとに、公証役場で公正証書遺言を作成します。このときに、立会人となる証人2名にも同行してもらいましょう。
持ち物は、ご自身の実印・印鑑証明、公証人の手数料、証人の本人確認資料です。
公証人が、③の遺言文案の内容を尋ねてくるので、口頭で答えましょう。そのあと、遺言者、証人、公証人が遺言に署名・捺印をして公正証書遺言の完成です。
公証役場以外でも公正証書遺言の作成は可能
公正証書遺言の作成は、原則として公証役場で行いますが、遺言者が高齢・病気等で公証役場に伺えない場合は、手数料・日当・交通費を負担して、公証人が自宅、病院、老人ホーム等まで出張してくれます。
3-4.公正証書遺言の保管期間
公正証書の原本は、原則として20年間、公証役場で保存されることになります(公証人法施行規則第27条)。
しかし、遺言者亡き後に効力を生ずる公正証書遺言の保管期間が20年では短すぎます。
そこで、公正証書遺言は、原則として、遺言者が生存中は公証役場に保管する取り扱いになっています。
具体的な保管期間は公証役場によって異なりますが、静岡市の公証役場では、遺言者の年齢が120歳に達する年まで保管してくれるとのことでした。
3-5.作成後は遺言の撤回が可能
遺言作成後は、遺言の方式にしたがって撤回・変更が可能です。これはもちろん、公正証書遺言にも該当します。
なお、公正証書遺言の撤回を自筆証書遺言で撤回・変更することも可能です。後の遺言の作成が遺言の方式にしたがって適法になされていれば、問題はありません。
(遺言の撤回)
民法 第1022条遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
法令検索:民法
4.公正証書遺言を作成するメリット
ここからは、公正証書遺言を作成するメリットを、主に自筆証書遺言と比べてみていきましょう。
なお、自筆証書遺言については、こちらの記事が参考になります。
4-1.確実性と信頼性
自筆証書遺言は、基本的に紙とペンがあれば誰にでも簡単に作成することができますが、法律上厳格な形式が定められていて、この形式からはずれた遺言は無効となってしまうおそれがあります。
この点、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が関与し作成しますので、遺言がその形式の不備によって無効となることはまずありえません。
また、自筆証書遺言は、その効力の有無をめぐって相続人同士の争いに発展する例も珍しくありません。簡単に作成できるメリットの裏を返せば、悪意のある相続人による偽造や、意思能力のない遺言者に無理やり遺言を書かせるといったことも可能なのです。
他方、法律専門家である公証人が作成した公正証書遺言は、極めて高い証拠力があるため紛争の発生を未然に防ぐことができます。
このような、確実性や信頼性が公正証書遺言を作成するメリットの一つといえるでしょう。
4-2.全文を自署する必要がない
自筆証書遺言は全文を自書する必要があるため、高齢等で体力が弱ってきたときに作成が困難になってしまいます。
他方、公正証書遺言は公証人が遺言を作成してくれますので、高齢者等でも、きちんと遺言を作成することができます。
4-3.検認不要
自筆証書遺言は、原則として、遺言者の亡き後に裁判所での「検認」という手続きが必要となります。検認には、申立てから1~2ヶ月程度の期間がかかり手続きも煩雑なものとなります。
他方、公正証書遺言に「検認」は不要です。遺言者亡き後すぐに相続手続きを進めることができます。
法改正により、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は「検認」が不要になりました。
4-4.遺言者亡き後は、全国の公証役場で遺言を検索できる
遺言者亡き後は、相続人が公証役場へ赴けば、遺言の検索をすることができます。全国の公証役場で可能です。
5.公正証書遺言にかかる費用(デメリット)
公正証書遺言は、公証人に支払う手数料が発生します。この点は、公正証書遺言唯一のデメリットといえるでしょう。
★公正証書遺言作成時、公証人に支払う手数料
| 目的財産の価額 | 手数料の額 |
| 100万円まで | 5,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 11,000円 |
| 1000万円まで | 17,000円 |
| 3000万円まで | 23,000円 |
| 5000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
1億円を超える部分については
| 1億円を超え3億円まで | 5000万円毎に13,000円 |
| 3億円を超え10億円まで | 5000万円毎に11,000円 |
| 10億円を超える部分 | 5000万円毎に8,000円 |
- 手数料は、財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、合算します。
- 全体の財産が1億円以下のときは、上記①の金額の手数料額に、11,000円が加算されます。
- 原本が4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が加算されます。
- 遺言者が病気又は高齢等のために公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成した場合には、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と現地までの交通費が加算されます。
6.まとめ
公正証書遺言は、もっとも確実性の高い遺言と言えます。公正書遺言なら、後日の相続に備えて法的に効力のある確実な遺言を残しておくことができるでしょう。
当事務所では、公正証書遺言作成のサポートも行っております。遺言に関してお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。











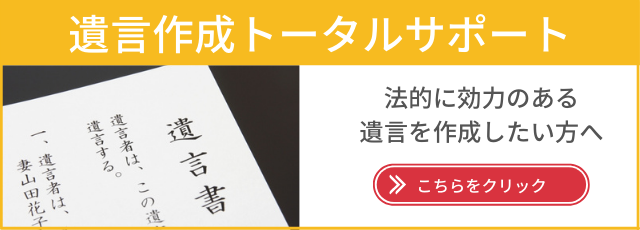

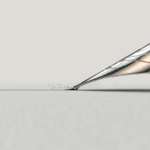




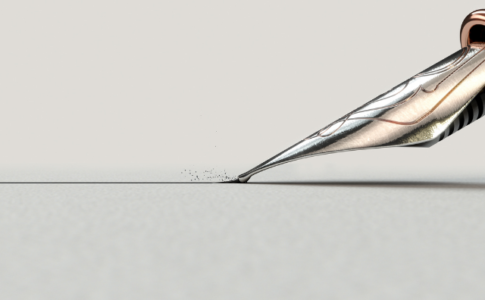
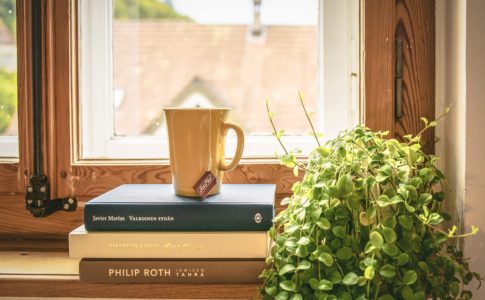

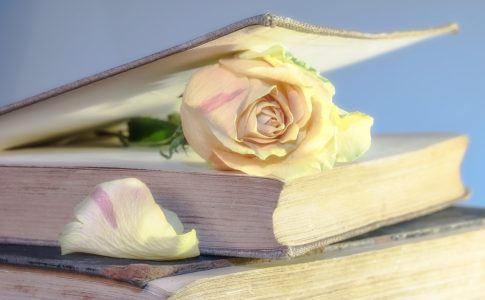

コメントを残す