「遺言書さえあれば、財産は想い通りに分けられるはず」
「特定の相続人に多くの財産を残したいが、後で揉めないか心配…」
「遺言の内容に納得できない。最低限もらえる財産はないのだろうか?」
相続において、故人の最終的な意思を示す遺言は非常に重要です。しかし、その遺言が原因で、残された家族が対立してしまう「争族」に発展するケースは少なくありません。
その大きな原因となるのが「遺留分」です。遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の遺産の取り分のこと。この知識がないまま遺言書を作成すると、後から「遺留分を侵害された」として、相続人間で金銭トラブルに発展する可能性があるのです。
この記事では、相続問題に詳しい司法書士が、以下の点について分かりやすく解説します。
- 遺言より優先される?「遺留分」の基本的な役割
- 遺留分を無視した遺言が招く深刻なトラブル
- 【ケース別】誰が、いくら遺留分をもらえるのか?計算方法を具体例で紹介
- 遺留分を侵害された場合の対処法と時効
- 円満な相続を実現するための、賢い遺言書の作成ポイント
大切な家族を想うからこそ、遺言と遺留分の正しい知識を身につけ、後悔のない相続準備を進めましょう。
目次
遺言は万能ではない?相続の基本と「遺留分」の重要性
人が亡くなると相続が発生し、残された財産(遺産)を誰がどのように引き継ぐか決めなければなりません。
民法では、誰が相続人になるか(法定相続人)、それぞれの取り分はどのくらいか(法定相続分)が定められています。通常はこのルールに従って遺産分割が行われます。
しかし、故人が遺言書を残していた場合、原則として法定相続よりも遺言の内容が優先されます。これは、故人が築いた財産を最期にどう処分するか、その意思を最大限尊重すべきという「遺言自由の原則」に基づいているからです。「お世話になった友人へ遺贈したい」「社会貢献のために寄付したい」といった想いを実現できるのが、遺言の大きな力です。
遺言の自由を制限する「遺留分」というセーフティネット
一方で、遺言の自由が無制限だと、残された家族が生活に困窮してしまう事態も起こり得ます。例えば「全財産を愛人に譲る」という遺言がそのまま実現されれば、長年連れ添った配偶者や、故人の財産をあてにしていた子供の生活基盤が失われかねません。
そこで法律は、遺言者の意思を尊重しつつも、残された相続人の生活を保障し、公平性を図るために、最低限の財産の取り分を保障する制度を設けました。それが「遺留分」です。
遺留分は、いわば残された家族のためのセーフティネット。遺言の自由と、相続人の生活保障とのバランスを取る、非常に重要な役割を担っているのです。
関連記事:【図表付き】遺留分の割合、計算方法をケース別に解説
遺留分を無視した遺言が「争族」の火種に!知っておくべきリスクとは
「遺留分を侵害するような遺言は、無効になるのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、それは間違いです。たとえ「全財産を長男に相続させる」といった、他の相続人の遺留分を完全に無視した遺言であっても、遺言自体は法的に有効です。
しかし、これは「遺言通りにすべてが完了する」という意味ではありません。
遺留分を侵害された相続人は、遺言によって多くの財産を受け取った人に対し、「侵害された分のお金を支払ってください」と請求する権利があります。これを「遺留分侵害額請求権」と呼びます。
この請求は、口頭だけでなく、後々の証拠とするために内容証明郵便などを用いて正式に行われるのが一般的です。当事者間の話し合いで解決できなければ、調停や訴訟へと進みします。
故人の「想い」が込められたはずの遺言書が、かえって家族の間に深刻な亀裂を生み、精神的にも金銭的にも大きな負担を強いる「争族」の引き金になってしまうのです。このような事態は、避けたほうが望ましいでしょう。
【一覧】遺留分は誰に保障される?相続人の範囲をチェック
遺留分は、すべての法定相続人に認められているわけではありません。法律で遺留分が保障されているのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
具体的には、以下の人が遺留分権利者となります。
| 遺留分権利者 | 詳細 |
|---|---|
| 配偶者 | 常に遺留分権利者となります。 |
| 子(直系卑属) | 被相続人の子供。もし子が先に亡くなっていて孫がいる場合、その孫(代襲相続人)が遺留分を持ちます。 |
| 直系尊属 | 被相続人の親や祖父母。子や孫がいない場合に限り、遺留分権利者となります。 |
| 胎児 | 無事に生まれた場合、子として遺留分を持つことができます。 |
| 兄弟姉妹 | 遺留分はありません。 |
兄弟姉妹に遺留分がないのは、配偶者や子、親に比べて、被相続人との生活上の結びつきが相対的に弱いと考えられているためです。
遺留分の計算方法|あなたの取り分はいくら?具体例で解説
遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって変わります。計算は2段階で行います。
- 総体的遺留分:遺産全体に対する遺留分の割合を算出
- 個別的遺留分:総体的遺留分を、各相続人の法定相続分で按分
1. 総体的遺留分の割合
| 相続人の構成 | 総体的遺留分 |
|---|---|
| 直系尊属(親など)のみが相続人の場合 | 遺産の3分の1 |
| 上記以外の場合 | 遺産の2分の1 |
「上記以外の場合」とは、配偶者や子が含まれるケース(例:配偶者と子、子のみ、配偶者と親)を指します。
2. 具体的な計算例
例1:相続人が配偶者と子2人、遺産が6000万円の場合
- 総体的遺留分:6000万円 × 1/2 = 3000万円
- 個別的遺留分:
- 配偶者:3000万円 × 1/2 (法定相続分) = 1500万円
- 長男:3000万円 × 1/4 (法定相続分) = 750万円
- 次男:3000万円 × 1/4 (法定相続分) = 750万円
例2:相続人が父と母のみ、遺産が6000万円の場合
- 総体的遺留分:6000万円 × 1/3 = 2000万円
- 個別的遺留分:
- 父:2000万円 × 1/2 (法定相続分) = 1000万円
- 母:2000万円 × 1/2 (法定相続分) = 1000万円
このように、遺留分の計算は相続人の構成によって大きく異なります。ご自身のケースで正確な金額を知りたい場合は、専門家への相談をおすすめします。
遺留分計算の基礎となる財産の範囲
遺留分を計算する際の「遺産」には、亡くなった時点の財産だけでなく、過去の生前贈与なども含まれるため注意が必要です。
| 対象となる財産 | 詳細 |
|---|---|
| 相続開始時の財産 | 預貯金、不動産、株式などプラスの財産すべて。 |
| 遺贈 | 遺言による贈与はすべて含まれます。 |
| 生前贈与(相続人以外へ) | 相続開始前1年以内の贈与。遺留分を害すると知って行われた贈与は1年以上前でも含まれます。 |
| 生前贈与(相続人へ) | 特別受益にあたる贈与(結婚資金、住宅資金など)は、相続開始前10年以内のものに限って含まれます。 |
| 被相続人の債務 | 借金などのマイナスの財産は、上記の合計額から差し引きます。 |
特に、相続人への生前贈与(特別受益)や、被相続人の介護など特別な貢献(寄与分)は、計算を複雑にする要因です。これらの詳細については、以下の記事もご参照ください。
関連記事:資金援助等を受けた人は相続分が減少する?特別受益とは
遺留分を侵害されたら?請求権の行使方法と「時効」というタイムリミット
遺留分が侵害されていることが分かった場合、権利を行使しなければ取り戻すことはできません。
請求手続きの流れ
- 話し合い(協議):まずは当事者間で穏便な解決を目指します。
- 内容証明郵便の送付:協議が難しい場合や、時効の完成を止める(時効の更新)ために、請求の意思を明確に書面で通知します。
- 家庭裁判所での調停:話し合いがまとまらない場合、調停委員を交えて解決を図ります。
- 地方裁判所での訴訟:調停でも合意に至らない場合の最終手段です。
絶対に注意すべき「時効」
遺留分侵害額請求権には、2つの時効があり、いずれか早い方が到来すると権利が消滅してしまいます。
- 消滅時効(1年):相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間。
- 除斥期間(10年):事実を知っているか否かにかかわらず、相続開始の時から10年間。
「まだ時間がある」と思っていても、あっという間に1年の時効は迫ってきます。遺留分が侵害されている可能性があると分かったら、すぐに専門家へ相談し、内容証明郵便を送るなどの対策を取ることが極めて重要です。
まとめ:円満相続のために、今すぐできる遺言・遺留分対策
最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。
- 遺言は万能ではない:遺言の自由には、「遺留分」という相続人のための最低保障制度がある。
- 遺留分を無視した遺言は有効だが危険:後から遺留分侵害額を請求され、「争族」の火種になる。
- 遺留分権利者は兄弟姉妹以外:配偶者、子(孫)、親が対象。
- 遺留分侵害額請求には時効がある:知ってから1年、相続開始から10年。
故人の想いを実現し、残された家族が円満に相続を終えるためには、遺言作成の段階で各相続人の遺留分をきちんと計算し、配慮することが何よりも大切です。
後悔しない遺言のために、司法書士へご相談ください
「自分のケースの遺留分はいくらだろう?」
「遺留分に配慮した遺言書の書き方が分からない」
「遺言に付言事項として想いを書き残し、相続人の理解を得たい」
このようなお悩みやご希望がありましたら、ぜひ相続の専門家である司法書士にご相談ください。
あなたの想いを丁寧にヒアリングし、財産状況や家族構成を踏まえたうえで、遺留分トラブルを未然に防ぐ最適な遺言作成をサポートします。
後悔のない相続の第一歩として、まずは一度、お気軽にご相談ください。






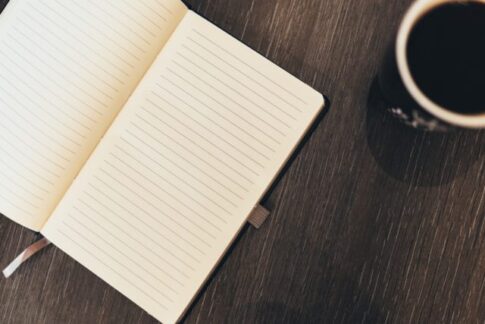











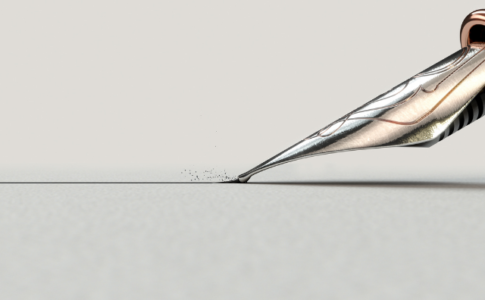

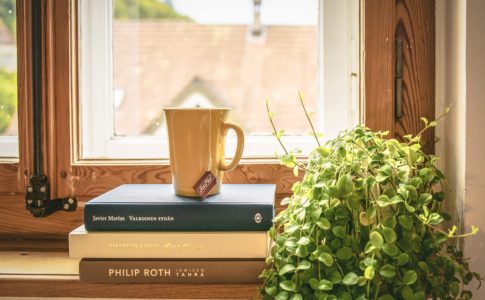

コメントを残す