最近では、「親の遺産を放棄したい」というご相談が非常に増えています。その背景には、社会の変化に伴う様々なご事情があります。
- 「親が遺した借金を相続したくない」
- 「事業を継ぐ気はなく、他の兄弟にすべてを譲りたい」
- 「離婚して何十年も会っていない親の相続に、今さら関わりたくない」
- 「相続人の数が多く、関係も疎遠で、話し合いがまとまりそうにない」
このように、経済的な理由だけでなく、ご家族間の関係性やご自身のライフプランを考えた上で、「相続しない」という選択を検討される方が多くいらっしゃいます。
しかし、一口に「遺産を放棄する」と言っても、その方法にはいくつかの選択肢があり、それぞれ法的な効果や手続き、注意点が大きく異なります。特に、借金を法的に免れるためには、特定の手続きを踏むしかありません。
安易な判断で意図しない結果を招かないためにも、ご自身の状況に最も適した方法を知ることが重要です。
この記事では、相続問題に詳しい司法書士が、「親の遺産を放棄したい」と考えたときに選べる3つの選択肢について、それぞれのメリット・デメリット、具体的な手続き、費用、注意点まで、網羅的に分かりやすく解説します。
この記事を最後までお読みいただくことで、ご自身の状況に最適な「放棄」の方法が明確になり、後悔のない選択をするための一歩を踏み出せるはずです。
目次
1:「相続放棄」と「遺産の放棄」は全くの別物です
まず、多くの方が混同しがちなのですが、法律の世界では、家庭裁判所で行う「相続放棄」と、相続人間の話し合いで財産を受け取らない「遺産の放棄(相続分の放棄)」は、全く異なる意味を持ちます。
この違いを理解することが、適切な選択をするための第一歩です。
| 相続放棄(家庭裁判所) | 遺産の放棄(相続分の放棄) | |
|---|---|---|
| 法的効果 | 初めから相続人ではなかったことになる | 相続人としての地位は残る |
| 放棄の対象 | プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全て | 原則としてプラスの財産のみ |
| 借金の支払義務 | 免れることができる | 免れることができない |
| 手続き | 家庭裁判所への申述 | 相続人間の遺産分割協議 |
| 期間制限 | 原則3ヶ月以内 | 特になし |
ご覧の通り、最も大きな違いは「借金の支払義務」です。
亡くなった親に借金や連帯保証債務などがある場合、その支払義務から法的に免れるためには、必ず家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをしなければなりません。
相続人同士で「私が借金も全部引き継ぐから、あなたは財産を放棄して」といった内容の合意書(遺産分割協議書)を作成したとしても、その合意は債権者(お金を貸した側)に対して主張することはできません。債権者は、法律で定められた相続分に従って、各相続人に返済を求めることができるのです。
この点を誤解したまま手続きを進めると、「財産はもらっていないのに、借金の督促状だけが届く」という事態になりかねません。まずはこの大原則をしっかりと押さえておきましょう。
2:選択肢1.家庭裁判所での「相続放棄」【借金がある場合】
最初の選択肢は、法的に最も強力な効果を持つ「相続放棄」です。
相続放棄とは?
相続放棄とは、家庭裁判所に「私は相続人としての地位を一切放棄します」と申述(申し立て)をすることです。これが受理されると、その人は「初めから相続人ではなかった」とみなされます。
つまり、預貯金や不動産といったプラスの財産を一切受け取れない代わりに、借金やローン、損害賠償義務といったマイナスの財産も一切引き継ぐ必要がなくなります。
こんな方におすすめ
- 亡くなった人に借金や保証債務があることが明らかな場合
- プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い、または財産調査をしても全貌が不明でリスクを避けたい場合
- 他の相続人や親族との関わりを一切断ち、相続手続きから完全に離脱したい場合
メリット・デメリット
【メリット】
- 借金の支払義務を法的に免れることができる唯一の方法である。
- 相続人としての地位そのものを失うため、その後の遺産分割協議などに参加する必要がなくなる。
- 自分一人で手続きを進めることができ、他の相続人の同意は不要。
【デメリット】
- 「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という厳しい期間制限がある。
- 一度受理されると、原則として撤回できない。
- プラスの財産も全て放棄することになるため、「借金はないと思っていたのに、後から高価な財産が見つかった」という場合でも相続できない。
- 自分自身は相続人でなくなる、相続権が消滅するわけではなく、次の順位の相続人に権利が移る。(後述)
手続きの全体像と流れ
相続放棄は、ご自身で行うことも可能ですが、戸籍の収集や書類作成が複雑なため、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
STEP1:必要書類の収集 まず、申述に必要な戸籍謄本などを集めます。誰が亡くなり、誰が相続放棄をするのかによって必要書類が異なります。
- 【共通で必要な書類】
- 相続放棄の申述書
- 被相続人(亡くなった方)の住民票除票 または 戸籍附票
- 申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本
- 【申述人が配偶者または子の場合】
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
- 【申述人が孫(代襲相続人)の場合】
- 被代襲者(本来の相続人である親)の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
- 【申述人が親などの直系尊属の場合】
- 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子・孫で死亡している方がいる場合、その方の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本
- 【申述人が兄弟姉妹・甥姪の場合】
- 上記に加え、被相続人の直系尊属(親や祖父母)の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
STEP2:相続放棄の申述書の作成 裁判所のウェブサイトで書式をダウンロードし、必要事項を記入します。申述の理由などを具体的に記載します。
STEP3:家庭裁判所への申述 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、収集した書類と申述書を提出します。郵送での提出も可能です。
- 費用(実費)
- 収入印紙:800円分(申述人1人につき)
- 連絡用の郵便切手:数百円分(裁判所によって異なる)
- 戸籍謄本等の取得費用:1通450円~750円程度
STEP4:照会書への回答と受理 申述後、1~2週間ほどで裁判所から「照会書(回答書)」が送られてきます。これは、「本当に自分の意思で放棄するのか」「財産を処分したりしていないか」などを確認するための質問状です。これに回答して返送し、問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きは完了です。
注意点1:3ヶ月の期間制限(熟慮期間)
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行う必要があります。これを「熟慮期間」と呼びます。
- 起算点はいつ?:「被相続人が死亡した日」からではなく、「死亡の事実を知り、かつ、それによって自分が相続人になったことを知った時」からカウントします。
- 期間を過ぎてしまったら?:原則として相続放棄はできず、単純承認したものとみなされます。ただし、期間内に手続きが間に合いそうにない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることも可能です。
【参考記事】
注意点2:法定単純承認(財産を処分してはいけない)
相続放棄を検討している期間に、相続財産の一部でも処分してしまうと、相続する意思がある(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
民法921条(法定単純承認) 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。(後略)
では、具体的にどのような行為が「処分」にあたるのでしょうか。
- 「処分」にあたる可能性が高い行為
- 被相続人の預貯金を引き出して自分のために使う
- 不動産や自動車を売却したり、名義変更したりする
- 株式や投資信託を解約・売却する
- 高価な遺品(骨董品、貴金属など)を形見分けとして持ち帰る
- 「処分」にあたらないとされる行為
- 葬儀費用を被相続人の財産から支払うこと
- 一般的な価値の低い衣服などを形見分けすること
- 財産の価値を維持するための保存行為(例:壊れた家屋の修繕)
判断に迷う場合は、何も手を付けずに速やかに専門家に相談することが賢明です。
【参考記事】
注意点3:相続権は次の順位の人へ移る
あなたが相続放棄をすると、あなたは初めから相続人ではなかったことになります。その結果、相続権は次の順位の相続人に移ります。
- 第1順位:子・孫(子が既に亡くなっている場合)
- 第2順位:親・祖父母(第1順位が誰もいない場合)
- 第3順位:兄弟姉妹・甥姪(第1,2順位が誰もいない場合)
例えば、子が相続放棄をすると、親(被相続人の父母)が相続人になります。親も既に亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人になります。借金がある場合、その支払義務も次の順位の人に移ることになります。
3:選択肢2.遺産分割協議による「相続分の放棄」【借金がない場合】
次の選択肢は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)の中で、ご自身の相続する権利(相続分)を放棄する方法です。これは法的な「相続放棄」とは異なり、あくまで相続人間の合意に基づくものです。
相続分の放棄とは?
相続人としての地位は有したまま、「私は今回の相続で財産を一切受け取りません」と意思表示し、その内容で遺産分割協議を成立させることです。例えば、相続人がAとBの2人で、Bが相続分を放棄したい場合、遺産分割協議書に「被相続人の遺産全部を相続人Aが取得する」と記載し、全員で実印を押印すれば完了です。
こんな方におすすめ
- 借金などのマイナスの財産がない、または極めて少ないことが確実な場合
- 相続人全員と連絡が取れ、円満に話し合いができる関係にある場合
- 「長男に家を継いでほしい」「お世話になった母に全財産を」など、特定の相続人に財産を集中させたい場合
メリット・デメリット
【メリット】
- 相続放棄のような3ヶ月の期間制限がない。
- 家庭裁判所での手続きが不要で、相続人間の話し合いだけで完結できるため簡便。
- 特定の財産だけを放棄するなど、柔軟な対応が可能。
【デメリット】
- 借金などのマイナスの財産を放棄することはできない。(最重要)
- 相続人であることに変わりはないため、相続税の申告義務が生じる場合がある。
注意点:債務の取り扱い
前述の通り、遺産分割協議で「長男Aが全ての債務を負担する」と決めたとしても、それはあくまで相続人間の内輪の約束にすぎません。
債権者は、この合意に拘束されず、各相続人の法定相続分に応じて返済を請求できます。なぜなら、支払い能力のない人に債務が集中させられると、債権者は貸したお金を回収できなくなってしまうからです。法律は、こうした事態から債権者を保護しているのです。
もし、遺産分割協議の内容通りに特定の相続人だけに債務を負担させたいのであれば、**全ての債権者から個別に承諾(免責的債務引受契約など)を得る必要があります。
【参考記事】
4:選択肢3.「相続分の譲渡」【トラブルから離脱したい場合】
最後の選択肢が「相続分の譲渡」です。これは、ご自身の「相続人としての地位」そのものを、他の人に有料または無料で譲り渡す契約のことです。
相続分の譲渡とは?
相続分を譲渡すると、プラスの財産もマイナスの財産も含めた「相続人」というパッケージごと譲渡することになります。これにより、譲渡した人は遺産分割協議に参加する必要がなくなり、相続手続きから離脱することができます。
譲渡する相手は、他の共同相続人でも、全く関係のない第三者でも構いません。
こんな方におすすめ
- 相続人同士の関係が悪く、遺産分割協議が紛糾していて関わりたくない場合
- 相続財産に興味がなく、とにかく早く手続きから抜け出したい場合
- 特定の相続人に自分の相続分を渡し、その人に遺産分割協議を有利に進めてもらいたい場合
メリット・デメリット
【メリット】
- 遺産分割協議が成立する前であれば、いつでも行うことができる。
- 遺産分割協議から離脱できる。
- 有償で譲渡すれば、一定の対価を得られる可能性がある。
【デメリット】
- 相続分の放棄と同様、債務の支払義務を完全に免れるためには債権者の承諾が必要。
- 譲渡する相手を見つける必要がある。
- 第三者に譲渡した場合、他の相続人が「取戻権」を行使する可能性や、協議がさらに複雑化するリスクがある。
注意点:譲渡する相手は慎重に
相続分は第三者にも譲渡可能ですが、通常は他の共同相続人に譲渡するのが一般的です。見ず知らずの第三者がいきなり遺産分割協議に参加してくると、他の相続人は困惑し、話し合いがまとまりにくくなる可能性があるからです。
また、共同相続人の一人がその相続分を第三者に譲渡した場合、他の共同相続人は、その価額と費用を支払って、1ヶ月以内にその相続分を取り戻すことができます(相続分の取戻権 民法第905条)。この権利の存在も、第三者への譲渡を難しくしている一因です。
【参考記事】
5:【総まとめ】あなたに最適な方法は?3つの選択肢を徹底比較
ここまで解説してきた3つの選択肢を、一覧表で比較してみましょう。
| ①相続放棄 | ②相続分の放棄 | ③相続分の譲渡 | |
|---|---|---|---|
| 目的 | 借金を含め一切の相続を拒否 | 自分の財産の取り分をゼロにする | 相続手続きから離脱する |
| 借金の放棄 | できる | できない | できない(※) |
| 手続き | 家庭裁判所への申述 | 遺産分割協議 | 相続分譲渡契約 |
| 期間制限 | 原則3ヶ月以内 | なし | 遺産分割協議成立まで |
| 他の相続人 | 同意不要 | 全員の同意が必要 | 譲渡相手との合意が必要 |
| 費用 | 実費(数千円~) | 不要 | 契約書作成費用など |
| 適したケース | 借金がある場合 | 相続人が円満な場合 | 相続トラブルから抜けたい場合 |
※債権者の同意があれば可能です。
状況別・目的別のおすすめ選択フロー
どの方法を選ぶべきか迷ったら、以下のフローを参考にしてみてください。
- 被相続人に借金があり債務超過の状態であるか?
- YES → 選択肢1「相続放棄」が唯一の方法です。すぐに相続放棄の手続にに着手し、3ヶ月の期間に備えましょう。
- 被相続人に借金がない、またはあっても債務超過でないと断言できるか?
- YES → 次の質問へ
- 他の相続人と円満に話し合いができるか?
- YES → 選択肢2「相続分の放棄」が最も簡単です。遺産分割協議で財産を受け取らない旨を伝え、協議書に署名・押印しましょう。
- NO(話し合いが困難・関わりたくない) → 選択肢3「相続分の譲渡」を検討します。他の相続人の誰かに自分の相続分を譲渡できないか打診してみましょう。
最後に:安易な判断は禁物。まずは専門家へご相談ください
この記事では、親の遺産を放棄するための3つの方法を詳しく解説しました。
重要なポイントを繰り返します。
- 借金の放棄をしたいなら、選択肢は家庭裁判所での「相続放棄」。
- 借金がないなら、「相続分の放棄」か「相続分の譲渡」を状況に応じて選ぶ。
- 「相続放棄」には3ヶ月の期間制限と、財産を処分してはいけないというルールがある。
「遺産を放棄する」という決断は、ご自身の人生にとって大きな一歩です。しかし、その手続きは複雑で、一つ間違えると取り返しのつかない事態にもなりかねません。
「どの方法が自分にとって最適なのか判断できない」
「戸籍の収集や書類の作成に不安がある」
「3ヶ月の期限が迫っている」
このような場合は、決して一人で抱え込まず、私たち司法書士のような相続の専門家にご相談ください。専門家が介入することで、正確な財産調査から、ご状況に合わせた最適な手続きの提案、そして煩雑な書類作成や裁判所への提出まで、スムーズかつ確実に行うことができます。
初回相談は無料で行っている事務所も多くあります。まずは専門家の話を聞いてみることから始めてみてはいかがでしょうか。この記事が、あなたの後悔のない相続手続きの一助となれば幸いです。







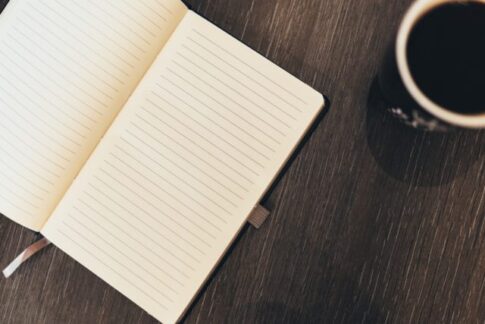














コメントを残す