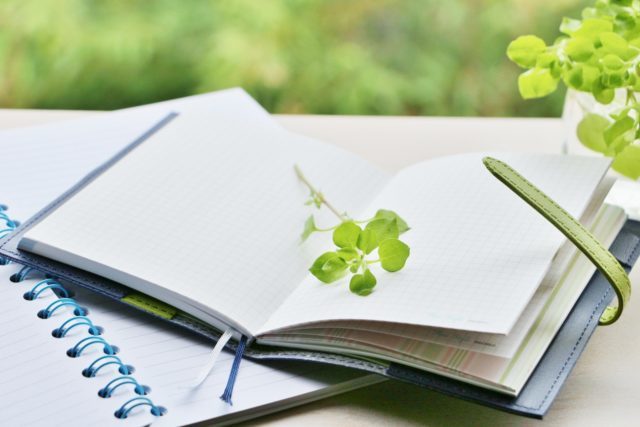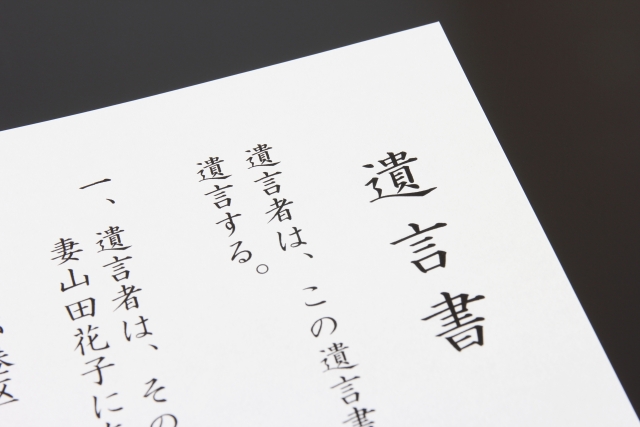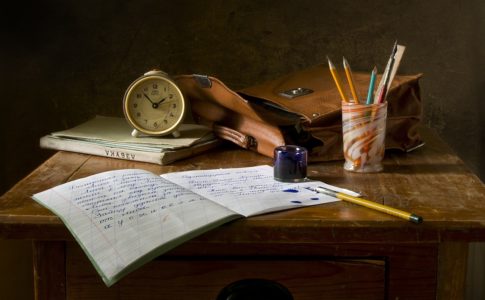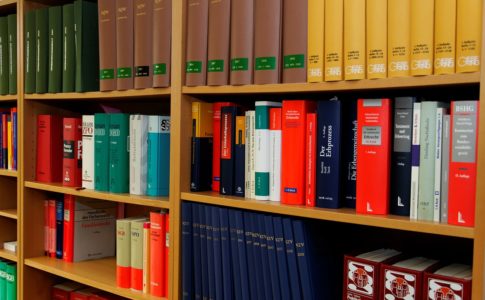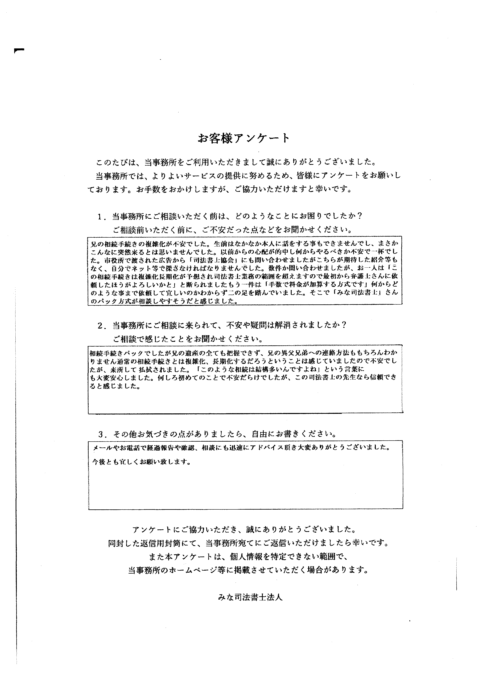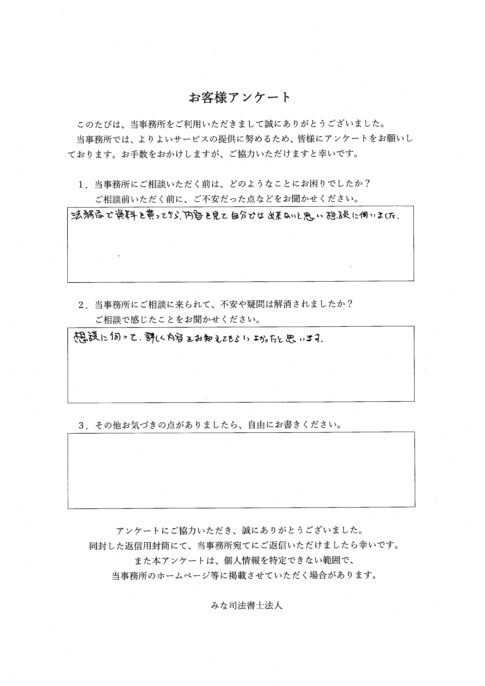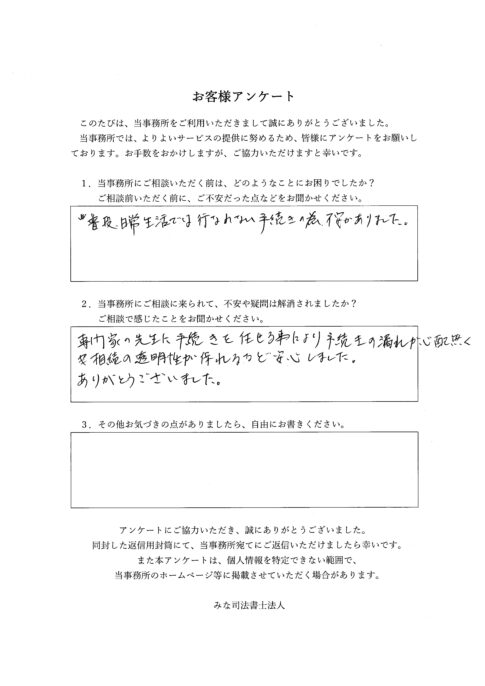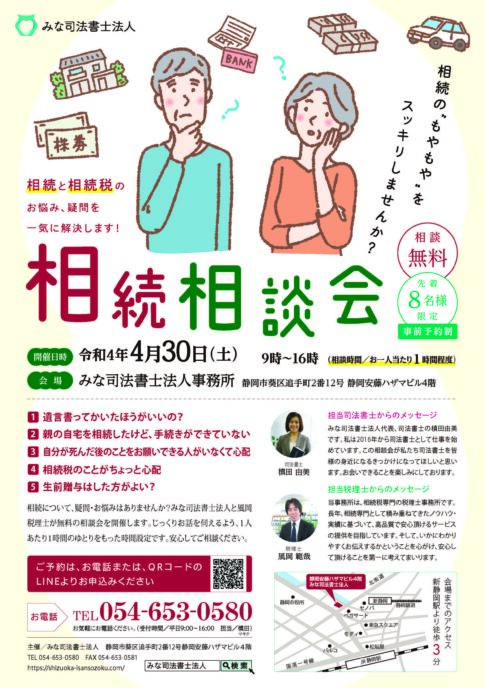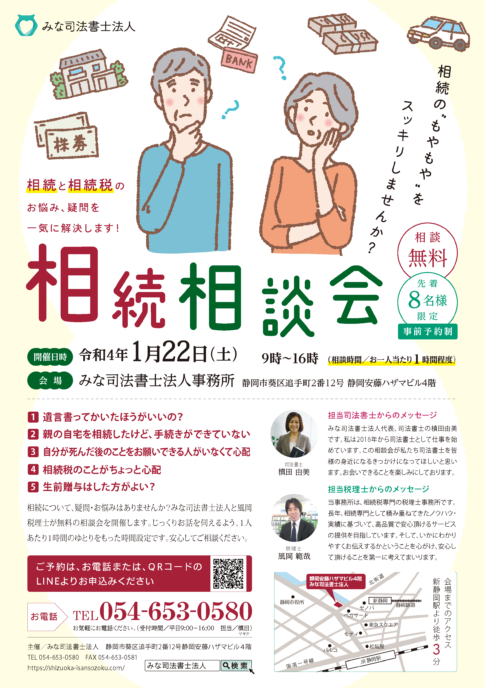人の気持ちは変わるもの。一旦遺言を書いてみたけどやっぱり書き直したい…と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、遺言の書き直しとその方法についてご説明していきます。
1.遺言の方式にしたがって撤回
遺言を書き直すことを法律の用語で「遺言の撤回」といいます。遺言の撤回については、次の条文に規定されています。
民法第1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
ここに書かれているとおり、遺言を書いた人は、いつでも自由に遺言を変更、撤回することができます。
遺言を撤回する方法は「遺言の方式にしたがって」行います。「遺言の方式にしたがって」とは、「自筆証書遺言や公正証書を作成するのと同じ方法で行ってくださいね」という意味です。
なお、撤回をする遺言は前に作った遺言と同じ種類にする必要はありません。つまり、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできますし、その逆も可能です。
具体的には次のような文言を、新たに作成する遺言に入れておきます。
2.前の遺言と後の遺言の内容が抵触した部分
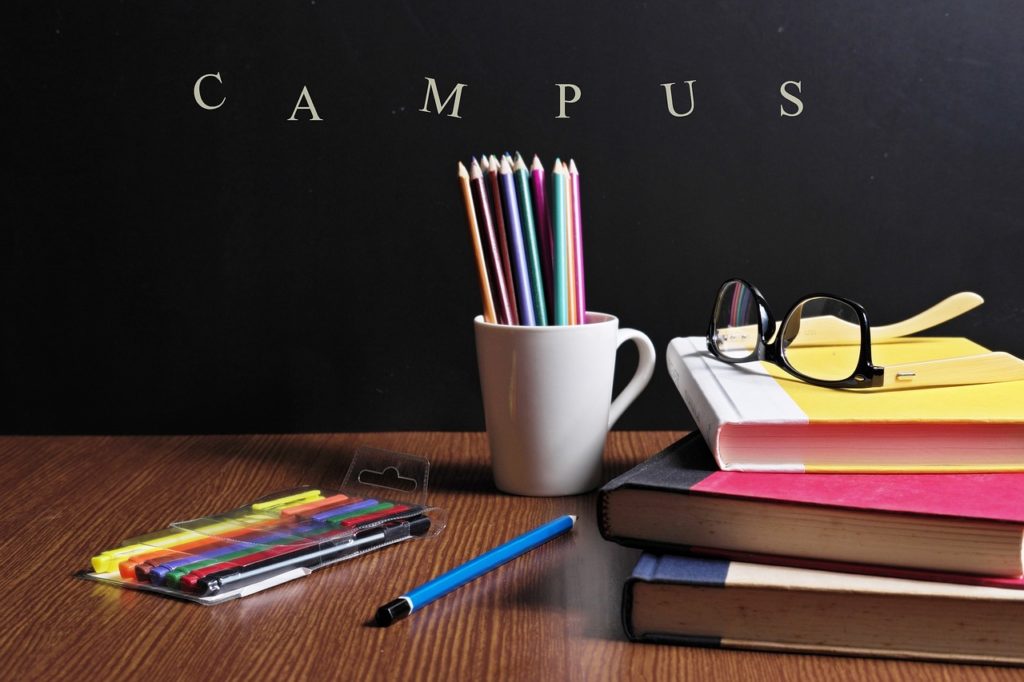
前の遺言と後の遺言で内容の抵触する部分がある場合、後の遺言の効力が優先します。
民法第1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
1.前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2.前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
まず1項を見てみます。ここには、「その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と書かれていますね。これは、「前の遺言と後の遺言で内容の同じ部分があった場合は、後の遺言の効力が優先しますよ」という意味です。
後の遺言が優先するのは、「前の遺言と内容が同じ部分だけ」なことに注意しましょう。内容の異なる部分は、依然として前の遺言が効力を持ちます。
具体例は次のようになります。
- 前の遺言
1.甲土地をAに譲る。
2.乙土地をBに譲る。 - 後の遺言
1.甲土地をCに譲る。
この例では、前の遺言と後の遺言で内容の同じ部分は、甲土地の部分だけですよね。したがって、甲土地については、後の遺言が優先するためCに譲ることになります。一方、乙土地については前の遺言が効力を持ちますので、そのままBに譲ることになります。
次に2項を見てみます。ここには、「遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する」と書かれていますね。生前処分とは売買などの行為を指します。
たとえば、遺言に「甲土地をAに譲る」と記載した後、生前に甲土地をBに売却してしまえば、「甲土地をAに譲る」と書いた部分は撤回したものとみなされます。
3.遺言・目的物の破棄
遺言を故意に破棄した場合も、遺言は撤回したものとみなされます。
第1024条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
自筆証書遺言の場合は、遺言者が保管している遺言書を破棄するだけで撤回したものとみなされます。
これに対して、公正証書遺言の場合は、遺言書の原本は公証人役場で保管されていますので、手元にある遺言書を破棄しても撤回したことにはなりません。公正証書遺言を撤回したい場合は、前述した遺言の方式にしたがって撤回されることをおすすめします。
4.遺言の撤回まとめ
遺言の撤回について次の4点にまとめておきます。
- 遺言を書いた人は、いつでも自由に遺言を変更、撤回することができる
- 遺言を撤回する方法は、「遺言の方式にしたがって」行う
- 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる
- 遺言を故意に破棄した場合も、遺言は撤回したものとみなされる
以上見てきたように、一旦書いてしまった遺言でも、簡単に撤回や書き直しをすることができます。遺言を書こうかどうか迷われている方は、これらの撤回方法があることを知ったうえで、まずは気軽に作成されてみてはいかがでしょうか。