ここでは、ご自身で成年後見の申立てを行う場合の、手続きの流れについてご説明していきます。
この記事の申立て手続きの流れは、すべて「法定後見制度」についての解説となります。
法定後見と任意後見の違いは、こちら↓の記事をご覧ください。
目次
1.成年後見の申立てをすることができる人
成年後見の申立てをすることができる人は、
- 本人
- 親族(4親等内)
- ①、②の人が申し立て困難の場合、市町村長
となります。
申立ての際、ご本人はすでに判断能力が低下した状態にあると思いますので、ほとんどのケースで親族が申立人となります。
2.成年後見の申立てに必要な書類
成年後見申立て時の必要書類は、次のとおりです。ここでは、主に静岡家庭裁判所へ申し立てる際の流れについてご説明しています。
- 戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
- 住民票または戸籍附票(発行から3ヶ月以内)
- 登記されていないことの証明書(発行から3ヶ月以内。静岡県内の窓口交付は、静岡地方法務局のみ。郵送での送付は、東京法務局へ請求。詳細はこちらの法務局HPへ)
- 医師の診断書(発行から3ヶ月以内。主治医に作成してもらう。こちらの家庭裁判所HPからダウンロードできます)
- 住民票または戸籍附票
- 収入印紙(申立て手数料及び登記手数料)
- 後見・保佐800円分
- 保佐・補助+代理権付与1600円分
- 保佐・補助+同意権付与1600円分
- 保佐・補助+代理権付与+同意権付与2400円分
- 登記手数料2600円分
- 郵便切手
- 後見 3960円分
500円(4枚)・100円(1枚)・82円(20枚)・20円(5枚)10円(10枚)・2円(10枚) - 保佐・補助 4460円分
500円(5枚)・100円(1枚)・82円(20枚)・20円(5枚)10円(10枚)・2円(10枚)
- 後見 3960円分
- 親族の同意書
3.実際に申立て手続きを進めた場合の流れ
まずは、申立先の家庭裁判所を確認しましょう。
申立て先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
裁判所の管轄はこちら
ここでは、実際に静岡家庭裁判所へ後見開始の手続きを進めた場合の流れをみていきます。
たとえば、「後見制度が思ってた内容と違った…」「自分の希望していない人が後見人に選任された…」といった理由で、後見制度を取りやめることはできません。申立ての際には、後見制度の内容をよく理解しておきましょう。
① 家庭裁判所HPから必要書類をダウンロード(または直接家庭裁判所の窓口から入手する)
まずは、申立てに必要な書類を入手します。静岡家庭裁判所後見ガイドからのダウンロードがおすすめです。
静岡家庭裁判所後見ガイド
直接家庭裁判所の窓口から入手することもできます。
② 主治医に医師の診断書を作成してもらう
①で入手した書類の中に、後見開始手続き用の医師の診断書が入っていますので、これをご本人の主治医に作成してもらいましょう。診断書を作成する医師は、精神科の専門医でなくてもかまいません。
③ 親族の同意書を作成
①で入手した書類の中に、親族の同意書が入っていますので、署名・捺印をもらいましょう。
④ 後見の登記されていないことの証明書を取得
静岡県内の窓口交付は、静岡地方法務局のみ。郵送での送付は、東京法務局のみの取扱いになります(静岡市外の方は、郵送での請求がおすすめです)。
詳細はこちらの法務局HPへ
⑤ 戸籍謄本等を取得
各市区町村役場で戸籍謄本等を取得します。取得する書類は次のとおりです。
- 本人
- 戸籍謄本
- 住民票または戸籍附票
- 後見人候補者に関する書類
- 住民票または戸籍附票
⑥ 申立て書類の作成
①で入手した書類の中に、次の書類が入っていますので作成しましょう。これら書類の記載例も、静岡家庭裁判所後見ガイドで確認できます。
静岡家庭裁判所後見ガイド
- 後見・保佐・補助開始申立書
- 親族関係図
- 申立書付票(付票1~3)
- 付票添付資料
- 収支予定表
- 財産目録
⑦ 本人の財産に関する書類をコピー
⑥で作成した、財産目録・収支予定表の元となった預金通帳等をコピーして提出します。具体的には、次のような書類をコピーしておきます。
- 預貯金の通帳(過去1年分の入出金がわかる部分)
- 各種税金・社会保険料についての納税通知書
- 医療費・福祉サービス利用料についての領収書
- 株式の残高証明書
- 保険契約についての保険証券・証書
- 不動産登記事項証明書原本・固定資産税評価証明書
- 住宅ローンの残高証明書 など
⑧ 家庭裁判所へ後見開始の申立て
以上の書類を整えて、家庭裁判所へ後見開始の申立てをします。
⑨ 家庭裁判所調査官との面談
⑧の申立て書類に特に不備がなければ、家庭裁判所から連絡がきて調査官との面談日を予約することになります。面談日には、できれば本人も同席されたほうがよいですが、施設入所中などで外出が難しい場合は、申立人だけでの面談も可能です。
面談では、現在の本人の様子や、申立ての動機などを尋ねられますので正直に答えましょう。
⑩ 本人の精神鑑定(省略されることが多い)
この鑑定は、裁判所の判断によって実施されるもので、状況によっては省略されることもあります。たとえば、診断書の内容から明らかに後見相当であることが分かる場合は、省略されることになるでしょう。なお、鑑定が実施される場合は、約5万円〜10万円程度の費用がかかります。
⑪ 後見開始の審判・確定・後見人の選任
以上の手続きを経て、後見開始の審判が下り、成年後見人が選任されます。この審判書が成年後見人に届いてから2週間を経過すると確定となります。
4.まとめ
以上のような手順で、後見開始の手続きは進んでいきます。
前述していますが、「後見開始の申立て後は、原則として取り下げはできない」という点には十分注意してください。後見制度の内容をよく理解してから、申立てをするようにしましょう。
もし、ご自身での申立てを負担に感じるようでしたら、一度専門機関に相談に行かれることをおすすめします。
もちろん、当事務所においてもご相談は受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。






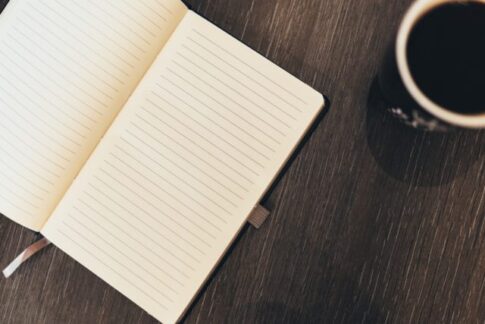
















入手先:家庭裁判所窓口または裁判所HPからダウンロード
(静岡家庭裁判所はこちら)