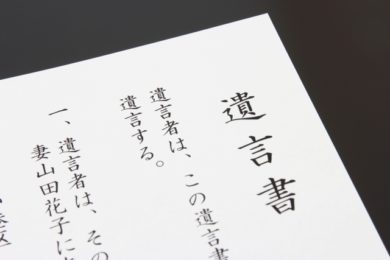「被相続人(亡くなった人)が残してくれた遺言のとおりに相続をしていったら、他の相続人から遺留分の請求を受けてしまった…」というご相談が増えています。
この遺留分の対策としては、
- そもそも遺留分が発生しないように遺言を作成する
- 遺留分減殺請求を受けることを前提として、その資金を別に用意しておく
といった、2通りの方法があります。
このうち、②の対策において、生命保険金は非常に有効な方法となりますので、ここでご説明していきます。
1.遺留分とは
相続は人の死亡によって開始します。そして、残された財産を、①誰に、②どのように分けるのかの一つの目安として、法律は相続人の範囲と法定相続分というものを定めています。
通常多くの場合は、この規定を目安に遺産を分けていくことになりますが、被相続人(亡くなった人)が遺言を残していた場合には、法律の定めた法定相続の規定よりも遺言の内容が優先します。
これは、自分の財産の最後の処分方法は、その人の意思を最大限に尊重すべきと考えられているからです。
しかし、被相続人の意思の尊重といっても「全財産を愛人に渡す」などといった遺言を書かれてしまっては、被相続人の財産を頼って生計を維持してきたような方(妻など)は困ってしまうでしょう。
そうならないように、残された相続人の最低限の相続分を確保するために定められた制度が遺留分という制度です。
1−1.遺留分の権利を持つ人とその割合
遺留分の権利を持つ人とその割合は、次のとおりです。
- 遺留分の権利を持つ人
- 兄弟姉妹以外の相続人(兄弟姉妹に遺留分はありません)
- 胎児も無事生まれたら、子としての遺留分を持つ
- 子の代襲相続人も遺留分を持つ
- 遺留分の割合
- 直系尊属(親)のみが相続人の場合 被相続人の財産の3分の1
- その他の相続人の場合 被相続人の財産の2分の1
2.遺留分対策としての生命保険

遺留分は、被相続人の相続財産に対して、前述した割合で定められます。この点、注意すべきは、相続財産の内訳です。
相続財産がすべて預貯金だった場合は、請求された金額を支払えば問題ありません。
しかし、相続財産のほとんが不動産で、預貯金が少額しかない場合はどうでしょうか。遺留分減殺請求に対して支払うべき金銭がありません。
たとえば、次のような事例が考えられます。
- 相続人 :妻、子4人(内、前妻の子が一人)
- 相続財産:不動産(評価額5,600万円)預貯金(400万円)
- 遺言の内容:妻に全財産を相続させる
この遺言内容の場合、子一人あたり遺留分は375万円です。このケースでは、前妻の子から遺留分を請求される可能性が高いといえます(遺留分の権利行使をするか否かは、権利を持つ人の意思に委ねられます。現在の妻の子が自身の母に遺留分を請求する可能性は低いでしょう)。
子の一人から375万円を請求されてしまうと、妻の手元に残る預貯金は25万円しかありません。妻の今後の生活を考えると、なるべく多くの現金を手元に残しておきたいところです。
こうした場合の対策として、生命保険が役に立ちます。遺留分減殺請求の分の資金を生命保険金で用意しておけばよいわけです。
仮に、遺留分権利者に不動産の持分の移転を請求された場合であっても、次の法律の規定により、金銭で支払うことが可能となります。
民法第1041条(遺留分権利者に対する価額による弁償)
受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。
3.生命保険金は遺留分減殺請求の対象とならない
もう一つ、生命保険金が遺留分対策として有効となる理由に、「生命保険金(死亡保険金)は相続財産には含まれない」という点があります。
相続される財産については次の法律に規定されています。
民法896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
「被相続人の財産に属した一切の権利義務」とは、預貯金や不動産などの金銭的価値のあるものに加えて、借地権、借家権、損害賠償請求権など、法律上の権利をも含みます。
具体例として次のようなものです。
- 不動産・現金・有価証券・預貯金・ゴルフ会員権・車・家財などの動産・貸付金売掛金・借地権・借家権・抵当権・損害賠償請求権 など
そして、この相続財産の中に生命保険金(死亡保険金)は含まれません。これは、生命保険金は、保険金受取人となる人の「固有の権利」となるためです。
たとえば次のようなケースの場合、預貯金を生命保険金に移しておくだけで、遺留分減殺請求の金額が少なくなります。
- 相続財産:4,000万円
- 相続人 :妻、子2人
- 遺言の内容:妻に全財産を相続させる
★通常の場合の子1人あたりの遺留分
4,000万円(相続財産)×2分の1(遺留分)×4分の1(子の相続分)=500万円(子一人あたりの遺留分)
★相続財産のうち、2,000万円を生命保険金にした場合(生命保険金は「受取人固有の権利」になるため、「相続財産」には含まれない)
2000万円(相続財産)×2分の1(遺留分)×4分の1(子の相続分)=250万円(子一人あたりの遺留分)
例外的に、生命保険金が「特別受益」に該当すると判断された場合は、相続財産に含まれる可能性があります。
この点について、裁判例は「生命保険金は原則として特別受益の対象とはならない」としながらも、「相続人間に生ずる不公平が、到底見過ごすことのできないほどの特段の事情があれば、生命保険金は特別受益として持ち戻しの対象となる」と判示しています。
生命保険金と相続財産の関係について、詳しくはこちら↓をご覧ください。
遺留分対策としての生命保険金の受取人は、「遺留分権利者へ」と考える方もいるようですが、これは間違いです。前述しているように、生命保険金は相続財産の範囲から外れますので、遺留分権利者を受取人としてしまうと、遺留分権利者は、生命保険金を受け取った後さらに遺留分も請求できてしまう、という事態になってしまいます。
遺留分対策として生命保険金を用意しておく場合は、必ず、保険金受取人を相続財産の取得者にしておきましょう。
4.遺留分減殺請求権の時効期間

遺留分減殺請求権は、次のように時効期間が定められています。
- 相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
- 相続開始の時から10年
上記の期間が過ぎたら、遺留分対策として残してある生命保険金を、自分のものとしてもよいでしょう。
民法1042条(減殺請求権の期間の制限)
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
5.まとめ
- 遺留分とは、残された相続人の最低限の相続分を確保するために定められた制度
- 遺留分の権利を持つ人は、兄弟姉妹以外の相続人
- 遺留分の割合は、①直系尊属(親)のみが相続人の場合→被相続人の財産の3分の1、②その他の相続人の場合→被相続人の財産の2分の1
- 遺留分を請求された時の対策として、生命保険金を用意しておくとよい
- 生命保険金は、原則として、遺留分減殺請求の対象とはならない
- 遺留分減殺請求権は、①相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、②相続開始の時から10年、いずれかの期間を経過すると時効によって消滅する
ここでは、遺留分対策として生命保険を活用する方法を見てきましたが、いかがだったでしょうか。
遺留分は、遺言を残した場合に発生する可能性があります。生命保険金と相続財産の関係を知っておくと、遺留分の対策として役立つでしょう。
ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。