最近では、任意後見制度が注目を集めています。自分が元気なうちに任意後見人と契約をするため、与える代理権の範囲や自分のライフプランなどを、きちんと後見人予定者に伝えられる点が、任意後見契約の大きな特徴です。
ここでは、任意後見契約のメリットや手続きの方法について、ご説明していきます。
目次
1.任意後見制度と法定後見制度の違い
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類に分かれます。
法定後見制度は、すでに判断能力が衰えてしまった方が利用するのに対し、任意後見制度は、ご自身が元気なうちに、後見人になってほしい人とあらかじめ契約をしておく制度です。
★法定後見制度と任意後見制度の違い
| 法定後見制度 | 法定後見制度 現に判断能力が低下してしまった人が利用する。
①後見、②保佐、③補助、3つの類型に分かれる。 |
| 任意後見制度 | 任意後見制度 自分の判断能力が衰える前に、後見人になってほしい人とあらかじめ契約をする。 |
両制度のおおまかな違いは、こちらの↓の記事でもご紹介しています。
2.任意後見制度のメリット
2−1.後見人になってほしい人を、自分で指定しておける
任意後見契約のメリットは、自分の判断能力があるうちに、後見人となってほしい人をあらかじめ指定しておける点にあります。
この後見人予定者とする人は、ご自身の家族でもよいですし、司法書士などの第三者を指定することもできます。
一方で、法定後見制度では、後見人の選任権限は裁判所にありますので、自分の意志で後見人を選ぶことは難しくなります(ただし、申立て時に後見人候補者を推薦することはできます)。
法定後見制度における後見人選任の流れは、こちら↓の記事が参考になります。
2−2.後見人の仕事内容を、自分の意志で決められる
任意後見契約では、契約を締結する祭に、後見人の仕事内容をあらかじめ決めておくことができます。自分の預貯金や不動産をどのように管理してほしいか、それらの利用方法はどうしてほしいか、などを指定しておくことができます。
ほかに、身上監護の方法の指定として、自分が体調を崩したらどこの医療機関に受診してほしいか、施設入所が必要になったときに、どこの施設に入所したいか、などの指定も可能です。
これに対し、法定後見制度では、すでに判断能力が衰えてしまった方を対象に申立てられるので、そもそも自分の意向を伝えられる状況にあるのか分かりません。自分の意向が伝えられない場合は、後見人の判断で後見事務が遂行されていくことになります。
3.任意後見制度の注意点
3−1.任意後見人には取消権がない
任意後見制度の注意点として、任意後見人には契約の取消権がないことが挙げられます。
たとえば、認知症などで判断能力が低下している中、悪質な業者などに騙されてしてしまった不要な契約を法定後見人なら取り消せるのに対し、任意後見人は取り消すことができません。
3−2.任意後見契約に定められていない事項について手が出せない
前述しているとおり、任意後見制度を利用する際は、自分の意志で任意後見人の仕事の範囲を定めておくことができます。
しかし、当初は意図していなかった業務が必要になったときは、別途法定後見の申立てが必要な場合もあります。
4.任意後見制度利用の流れ
任意後見制度は、次のような流れで進んでいきます。
- 任意後見契約の締結
本人の判断能力が低下する前に、任意後見人になってほしい人と任意後見契約を締結します。この契約は、必ず公正証書でする必要があります。 - 任意後見監督人選任の申立
本人の判断能力が衰えてきたら、家庭裁判所へ任意後見監督人を選任するための申立てを行います。この申立ては、多くの場合、①の契約で締結した任意後見人予定者がすることになります(本人の親族等も申立てることができます)。 - 家庭裁判所の審理、後見監督人の選任
家庭裁判所の審理によって、実際に本人に後見が必要な状態だと認められれば、任意後見監督人が選任されます。この後見監督人が選任されたときから、任意後見人は、その職務を開始することになります。
5.任意後見契約3つのパターン

任意後見契約の締結から、実際に後見人が職務を開始するまでには、次の3つの手順があります。
- 即効型
- 移行型
- 将来型
それぞれ、詳しく見ていきます。
5−1.移行型
移行型とは、自分の判断能力が十分にあるうちは通常の任意代理契約を締結し、自分の判断能力が衰えてきた時点で、任意後見へと移行するパターンです。
このパターンでは、自分の判断能力のあるうちから、通常の任意代理契約に基づいて支援を受けることができます。そして、判断能力が低下した時点で、後見人予定者等の申立てにより、任意後見制度への移行がなされることになります。
なお、任意代理契約とは、任意後見契約ではなく、通常の委任契約のことです。任意代理人から支援を受ける事項は契約によって定めておくことができます。
任意代理人の行動を監督する人は、契約をした本人です。自分の判断能力が十分にあるうちはきちんと監督できると思いますが、判断能力が衰えていった場合の監督機能に不安は残ります。
また、最近では、本人の判断能力が衰えた後にも後見の申立がなされないケースもあるようです。
移行型を利用する際は上記の点を慎重に検討し、本当に信頼できる人に後見人を任せるようにしましょう。
5−2.将来型
移行型との違いは、自分の判断能力があるうちは、任意代理契約を締結しない点です。後見人予定者には代理権を与えずに見守り契約のみとして、自分の判断能力が衰えた時点で、後見を開始するパターンです。
5−3.即効型
即効型とは、任意後見契約と同時に任意後見を開始するパターンです。任意後見契約とほぼ同時に、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立てを行うことで、任意後見契約を発効させることになります。
本人の判断能力が相当程度衰えているが、契約締結能力はまだ残っているという段階で利用することができます。
6.まとめ
ここでは、任意後見制度のメリットや注意点をみてきましたが、いかがだったでしょうか。
法定後見制度は、すでに判断能力が衰えてしまった方が利用するのに対し、任意後見制度は、ご自身が元気なうちに、後見人になってほしい人とあらかじめ契約をしておく制度です。
自分の判断能力がしっかりしているうちに、後見人予定者やその仕事内容を決めておける点が任意後見制度の大きなメリットといえるでしょう。
ここでの記事が、あなたの参考になれば幸いです。








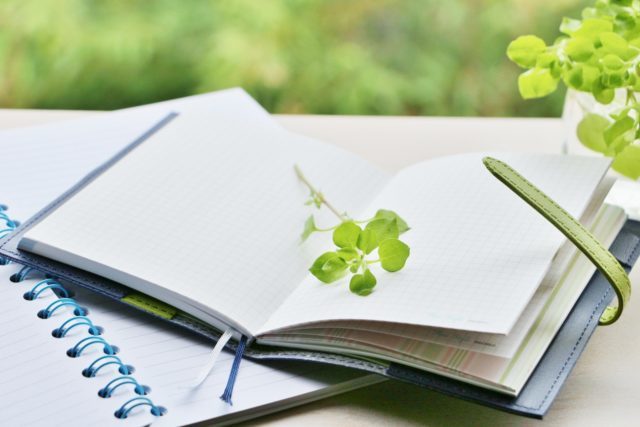

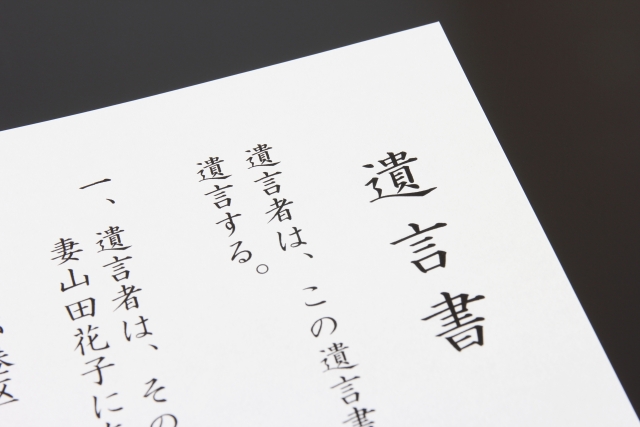










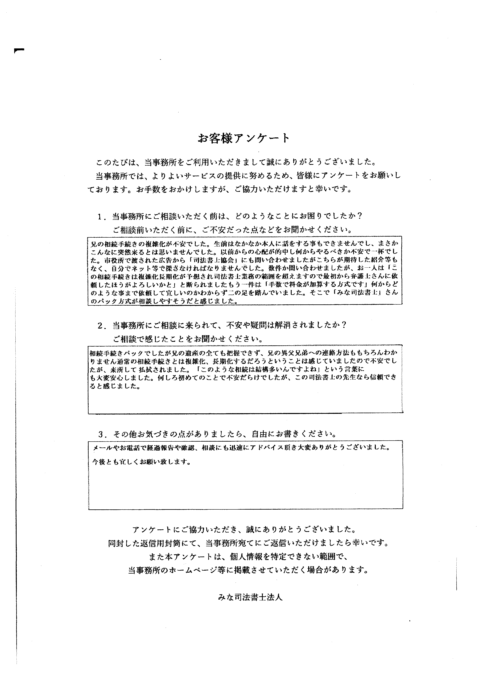
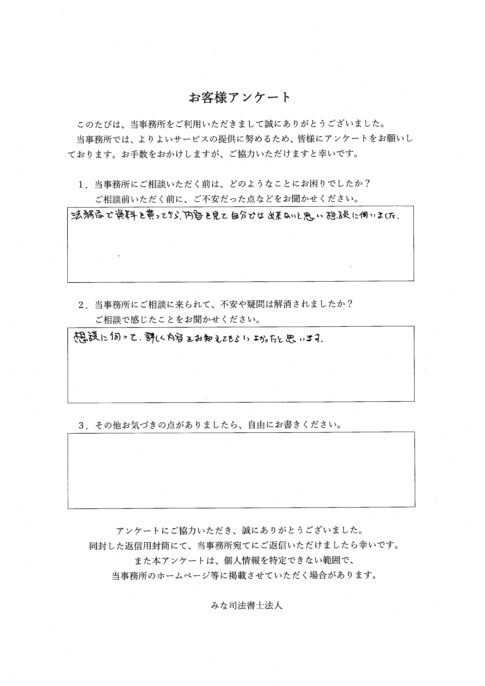
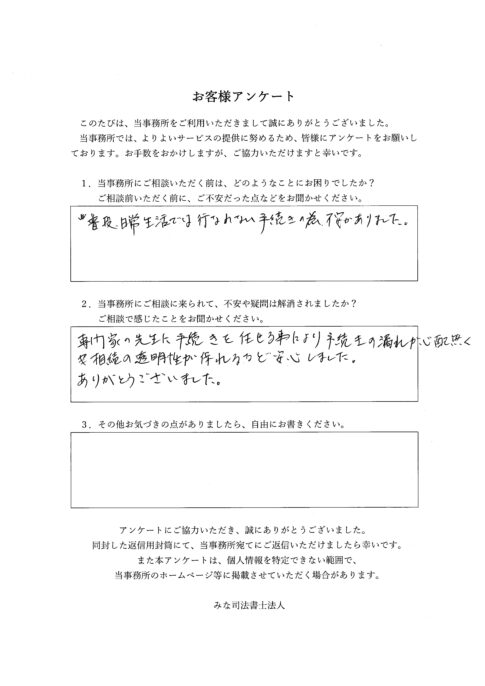
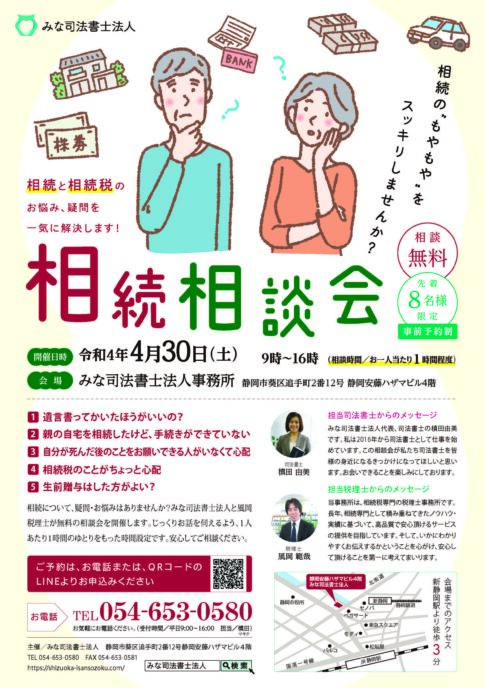
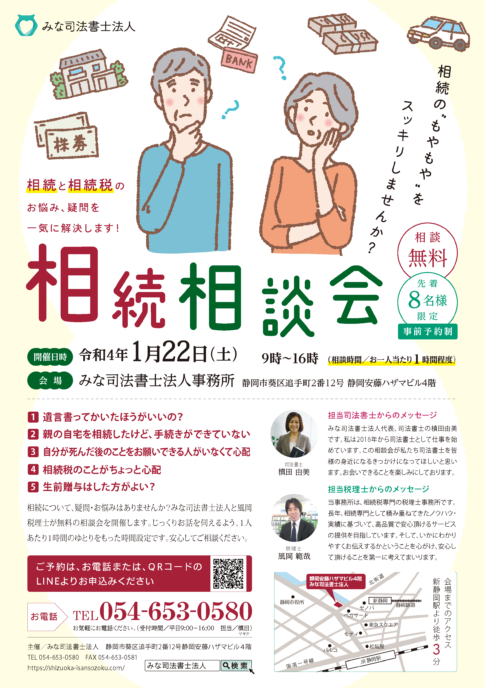

コメントを残す