相続人の中に未成年の子がいるため、特別代理人を選任して遺産分割協議を成立させたケース
相続時の状況 亡きご主人の相続人は、妻のAさん、13歳の子、10歳の子の3名でした。相続財産はご自宅といくらかの預貯金があり、残り15年の住宅ローンも残っています。 亡きご主人の遺産はすべてAさんが取得し、未成年の子の養...
 解決事例
解決事例相続時の状況 亡きご主人の相続人は、妻のAさん、13歳の子、10歳の子の3名でした。相続財産はご自宅といくらかの預貯金があり、残り15年の住宅ローンも残っています。 亡きご主人の遺産はすべてAさんが取得し、未成年の子の養...
 解決事例
解決事例ご相談時の状況 被相続人(亡くなった人)は2度結婚されていて、前妻との間に子が2人、後妻との間に子が2人いらっしゃいました。相続人は全員で4人となります。 当事務所に依頼に来られたのは、後妻との間の子のAさん。被相続人と...
 相続専門家の選び方
相続専門家の選び方相続手続きに関わる専門家は、税理士、弁護士、司法書士といわれています。また仲介役として、銀行等の機関が相続手続きに関わることも増えてきました。 各専門家にはそれぞれ得意分野というものがあります。あなたの要望に沿った相続手...
 法定相続証明書
法定相続証明書「法定相続証明書」とは、法務局から発行される相続人を証明する書類のことです。公的な書類として、各種の相続手続きで使用することができます。 平成29年度から始まった新制度でまだ馴染みの薄いものですが、取得しておけば相続手続...
 預貯金の相続
預貯金の相続預貯金の口座名義人が亡くなった場合には、相続手続きをする必要があります。手続きの詳細は各金融機関によって異なりますが、大筋では一致しています。 ここでは、預貯金の相続手続きについてご説明していきます。 1.預貯金の相続手...
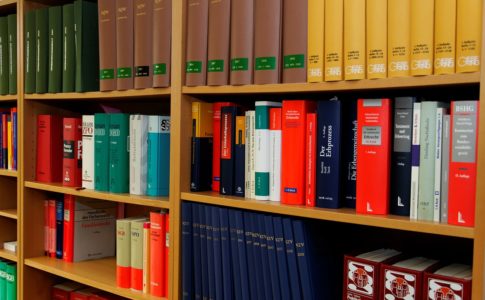 遺言
遺言正しく使えば便利な遺言ですが、偽造などのよからぬことを考える人がいることもまた事実。遺言を偽造した人は相続人の欠格事由というものにあたり、相続権を剥奪されます。 ここでは、遺言の偽造についてご説明していきます。 1.遺言...
 遺言
遺言遺言に記載して効力の生じる事項は、法律によって定められています。その内容をまとめてみました。 遺言として記載すれば法的に効力の生じる事項 1.認知 遺言によって子供を認知することができます。生前になんらかの理由で認知する...
 不動産の名義変更(相続登記)
不動産の名義変更(相続登記)不動産を共有持分で相続すると、不動産の管理や処分をする際に、他の共有者の同意を得なければならないなどの調整的な制約が生じてきます。 ここでは、不動産を共有で相続する際の注意点についてご説明していきます。 1.不動産を共有...
 遺産分割協議
遺産分割協議賃貸物件からの賃料は、相続する財産の対象となります。ただし、その賃料の分け方、いわゆる遺産分割をするにあたっては、法律上いくつかの決まりごとがありますので、ここでご説明していきます。 1.相続開始と遺産分割協議 遺産分割...
 遺産分割協議
遺産分割協議相続した不動産に抵当権が登記されている場合は、原則としてその抵当権を付けたまま不動産を相続することになります。 もっとも、抵当権が担保している債権が住宅ローンだった場合は、団体信用生命保険(だんしん)の適用により抵当権を...