親が亡くなり、相続の手続きを進める中で、多くの方が直面するのが「不動産の分け方」という課題です。預貯金のように単純に割り算で分けることができず、相続人それぞれの想いや事情も絡み合うため、不動産の遺産分割はトラブルの原因になりやすいポイントでもあります。
「実家をどうしようか」
「誰も住まない土地がある」
「公平に分けるにはどうすればいいのか」
こうしたお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって、誰が何をどのくらい相続するのかを決める手続きです。特に、遺産の中で大きな割合を占めることが多い土地や家などの不動産については、その分け方を慎重に検討する必要があります。
この記事では、不動産の遺産分割における代表的な3つの方法「換価分割」「代償分割」「共有分割」について、それぞれのメリット・デメリットや注意点を、司法書士が分かりやすく解説します。
ご自身の状況に最も合った分割方法を見つけ、円満な相続を実現するための一助となれば幸いです。
参考記事:遺産相続の最重要ポイント-遺産分割協議の知識と進め方
目次
1.不動産の遺産分割、3つの基本的な方法
不動産の遺産分割には、大きく分けて次の3つの方法があります。
- 換価分割(かんかぶんかつ):不動産を売却してお金に換え、その現金を相続人で分ける方法
- 代償分割(だいしょうぶんかつ):相続人の一人が不動産を取得し、他の相続人に対してその分のお金(代償金)を支払う方法
- 共有分割(きょうゆうぶんかつ):不動産を複数の相続人の共有名義にする方法
どの方法を選ぶかによって、手続きの流れや将来的な影響が大きく異なります。それぞれの特徴を理解し、ご家族の状況と照らし合わせながら、最適な選択をすることが重要です。
1-1.換価分割|公平性を重視するなら
換価分割は、不動産を第三者に売却し、その売却代金から諸経費(仲介手数料、税金など)を差し引いた残額を、相続人間で合意した割合(通常は法定相続分)に応じて分配する方法です。
【具体例】
相続人が子Aと子Bの2人。実家の土地建物を3,000万円で売却し、経費が150万円かかった場合。
(3,000万円 – 150万円)÷ 2人 = 1,425万円
AとBがそれぞれ1,425万円ずつ取得する。
メリット
- 公平な分割がしやすい物理的に分けられない不動産を、1円単位で分けられる現金にすることで、相続人間の不公平感をなくしやすい最も分かりやすい方法です。
- 不要な不動産を整理できる誰も住む予定のない実家や、管理が難しい遠方の土地など、相続人にとって維持管理が負担となる不動産を整理できます。固定資産税などの維持費の心配もなくなります。
デメリットと注意点
- 不動産を失うことになる当然ですが、思い出のある実家などを手放すことになります。「誰かが住み続けたい」と考えている場合は、この方法は選択できません。
- 売却に時間がかかることがある不動産は、すぐに希望の価格で売れるとは限りません。立地や物件の状態によっては、売却までに数ヶ月から1年以上の期間を要することもあります。遺産分割協議が長引く原因にもなります。
- 売却費用や税金がかかる売却時には、不動産会社に支払う仲介手数料や、登記費用、印紙税などの諸経費がかかります。また、不動産を購入した時よりも高く売れた場合は、その利益に対して譲渡所得税・住民税が課税される点にも注意が必要です。
- 希望額で売れるとは限らない想定していた価格よりも低い金額でしか売却できない可能性もあります。そうなると、各相続人が手にする金額も目減りしてしまいます。
1-2.代償分割|不動産を残したい場合に
代償分割は、相続人のうちの一人(または複数人)が不動産を現物で相続する代わりに、その不動産を取得した人が、他の相続人に対して自身の固有の財産(現金など)から代償金を支払う方法です。
【具体例】
相続人が長男Aと次男Bの2人。長男Aが評価額4,000万円の実家を相続する。
法定相続分は各2,000万円なので、長男Aは次男Bに代償金として2,000万円を支払う。
メリット
- 不動産を売却せずに残せる先祖代々の土地や、現在も誰かが住んでいる家などを、売却せずに特定の相続人が引き継ぐことができます。
- 公平な分割を実現できる代償金を支払うことで、不動産を取得しない相続人との間の公平性を保つことができます。
デメリットと注意点
- 不動産を取得する人に支払い能力が必要最大の課題は、不動産を取得する相続人に、他の相続人へ支払うだけの十分な資力(預貯金など)があるかどうかです。代償金が高額になると、支払いが困難になるケースも少なくありません。
- 不動産の評価額で揉める可能性がある代償金の額を算出する基礎となる不動産の評価額をいくらにするかで、意見が対立することがあります。不動産の価格には、固定資産税評価額、路線価、時価(実勢価格)など複数の基準があり、どの基準を用いるかで金額が大きく変わるためです。公平を期すためには、複数の不動産会社に査定を依頼するなど、相続人全員が納得できる価格基準を設定することが重要です。
- 代償金の支払いが贈与とみなされないように注意遺産分割協議書に「代償分割であること」を明確に記載しておかないと、単なる個人間の金銭のやり取りと見なされ、代償金を受け取った側に贈与税が課税されるリスクがあります。必ず「遺産分割協議の結果、代償金として金銭を支払う」という趣旨を明記しましょう。
1-3.共有分割|原則として避けるべき選択肢
共有分割(または現物分割の一種)は、一つの不動産を、複数の相続人が法定相続分などの持分割合を決めて、共有名義で相続する方法です。
【具体例】
相続人が配偶者Aと子Bの2人。実家の土地建物を、Aが持分2分の1、Bが持分2分の1の共有名義で登記する。
一見、手続きが簡単で公平に見えるため安易に選択されがちですが、将来的に最もトラブルに発展しやすい分割方法であり、司法書士としては積極的におすすめできない選択肢です。
メリット
- その場では公平に分割できるとりあえず法定相続分通りに分けることができるため、その場での合意は得やすいかもしれません。
デメリットと注意点
- 不動産の活用・処分に全員の同意が必要共有名義の不動産は、「共有者全員の同意」がなければ、売却したり、大規模なリフォームをしたり、取り壊したりすることができません。 共有者の一人でも反対すれば、何もできなくなってしまいます。
- 賃貸に出す場合も過半数の同意が必要不動産を賃貸に出すといった「管理行為」については、持分の過半数の同意が必要となります。意見がまとまらず、活用できないまま放置されるケースも少なくありません。
- 相続が発生すると、共有者が増えていく最大の問題は、共有者の一人が亡くなると、その人の持分がさらにその相続人に引き継がれることです。例えば、兄弟2人で共有していた不動産で、兄が亡くなり妻と子2人が相続すると、共有者は弟、兄の妻、兄の子2人の合計4人になります。このように、相続を重ねるごとにねずみ算式に共有者が増え、関係性も薄れていき、意見調整は困難になります。
- 共有物分割請求訴訟に発展するリスク共有関係を解消したいと思っても、話し合いがまとまらない場合、裁判所に「共有物分割請求訴訟」を提起するしかありません。裁判所の判断によっては、不動産が競売にかけられ、市場価格よりも安い金額で強制的に売却されてしまう可能性もあります。
共有分割は、その場しのぎの解決策にはなりますが、問題を将来に先送りしているに過ぎません。次の世代に負の遺産を残さないためにも、原則として避けるべき方法だと考えてください。
2.【節税】小規模宅地等の特例を考慮する
相続税の申告が必要なケースでは、「小規模宅地等の特例」を誰が使えるかが、遺産分割の方法を決める上で非常に重要な要素になります。
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方が住んでいた土地などを、配偶者や同居していた親族などが相続した場合に、その土地の相続税評価額を最大で80%減額できるという、非常に節税効果の大きい制度です。
例えば、評価額5,000万円の土地であれば、この特例を使えれば評価額が1,000万円(5,000万円 × 20%)となり、相続税を大幅に軽減できます。
この特例の適用を受けられる主な相続人は以下の通りです。
- 配偶者:無条件で適用できます。
- 同居していた親族:相続税の申告期限までその土地建物を所有し、居住し続けることが要件です。
- 同居していなかった親族(家なき子):亡くなった方に配偶者や同居親族がおらず、かつ、相続開始前3年以内に自分や配偶者所有の家に住んだことがないなど、一定の要件を満たす必要があります。
遺産分割協議では、この特例の適用要件を満たす相続人がその不動産を取得するように調整することで、相続税の負担を大きく減らせる可能性があります。相続税がかかりそうな場合は、どの分割方法を選択するかと併せて、税理士などの専門家にも相談しながら慎重に検討しましょう。
3.不動産の遺産分割方法 まとめ
この記事で解説してきた不動産の遺産分割方法のポイントをまとめます。
| 分割方法 | 特徴 | こんな場合におすすめ |
| 換価分割 | 不動産を売却し、現金を分ける | ・相続人全員が不動産を不要と考えている ・物理的に公平に分けたい |
| 代償分割 | 一人が不動産を相続し、他の相続人へ代償金を支払う | ・特定の相続人がその不動産に住み続けたい ・事業用の土地などで後継者が引き継ぎたい |
| 共有分割 | 複数の相続人の共有名義にする | ・将来のリスクが非常に高いため、原則として避けるべき ・他に方法がない場合の最終手段 |
不動産の遺産分割で最も大切なことは、目先の公平性や手続きの簡便さだけで判断するのではなく、長期的な視点を持って、将来にわたって誰もが困らない方法を選択することです。
預貯金の分割とは異なり、不動産の分割は法律や税金、登記といった専門的な知識が不可欠な場面が多くあります。また、相続人同士の感情的な対立が生まれやすいデリケートな問題でもあります。
もし、ご自身たちでの話し合いが難しい場合や、どの方法が最適か判断に迷う場合は、決して無理に進めようとせず、私たち司法書士のような専門家にご相談ください。
司法書士は、不動産登記の専門家として法的に安全な手続きをサポートするだけでなく、第三者の中立的な立場で話し合いの調整役となり、皆様にとって円満な遺産分割が実現できるようお手伝いをさせていただきます。お近くの司法書士事務所へ、お気軽にお問い合わせください。







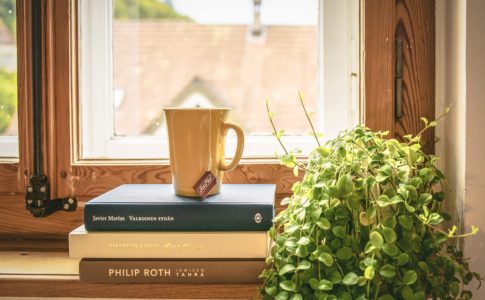














コメントを残す