「自分の財産は、希望通りに大切な人へ引き継いでほしい」
「残された家族が相続のことで揉めないようにしたい」
終活を考えるとき、多くの方がこのように願うのではないでしょうか。その想いを実現するための有効な手段が「遺言書」の作成です。
しかし、一口に遺言書といっても、実はいくつかの種類があることをご存知でしょうか?遺言には法律で定められた3つの方式があり、それぞれに作成方法や効力、メリット・デメリットが異なります。
ご自身の状況や想いに合わない方式を選んでしまうと、せっかく書いた遺言が無効になったり、かえって相続トラブルの原因になったりする可能性もゼロではありません。
この記事では、相続の専門家である司法書士が、遺言の3つの種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)について、それぞれの特徴から作成方法、注意点まで、網羅的に解説します。
この記事を読めば、あなたに最適な遺言の形式がわかり、円満な相続への第一歩を踏み出すことができるでしょう。
目次
1. 遺言の3つの基本形式
法律(民法)で定められている遺言の方式は、大きく分けて「普通方式遺言」と「特別方式遺言」があります。特別方式遺言は、病気や災害などで死期が迫っているなど、特殊な状況下でのみ認められるものです。
一般的に遺言を作成する場合は、「普通方式遺言」を用います。そして、この普通方式遺言には、次の3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
これらは、いわば遺言の「公式ルール」です。このルールに則って作成しないと、法的な効力を持つ遺言とは認められません。
それでは、一つひとつの特徴を詳しく見ていきましょう。
2. 自筆証書遺言|手軽さと注意点
自筆証書遺言とは、その名の通り、遺言者が全文、日付、氏名を自筆し、押印して作成する遺言です。
2-1. 自筆証書遺言の作り方
最も手軽で、思い立ったときにすぐ作成できるのが大きな特徴です。基本的には紙とペン、印鑑さえあれば、誰の力も借りずに作成できます。
ただし、手軽な反面、法律で定められた要件が非常に厳格です。一つでも要件を欠くと、遺言全体が無効になってしまう可能性があるため、細心の注意が必要です。
【自筆証書遺言の作成要件】
- 全文を自書する:遺言の内容は、すべて自分で手書きする必要があります。パソコンや代筆は認められません。
- 日付を自書する:「令和〇年〇月〇日」のように、作成した年月日を正確に記載します。吉日などの曖昧な表現は無効となる可能性があります。
- 氏名を自書する:戸籍上の氏名を正確に記載します。
- 押印する:認印でも構いませんが、実印を使用することが望ましいです。
【法改正による変更点:財産目録】
以前は財産の内容を記した「財産目録」もすべて手書きする必要がありましたが、2019年の法改正により、財産目録についてはパソコンでの作成や、通帳のコピー・登記事項証明書などを添付することが可能になりました。ただし、その目録の全ページに署名・押印が必要です。
2-2. 自筆証書遺言のメリット
- 手軽で費用がかからない:紙とペンがあれば、いつでも自分のタイミングで作成できます。公証人の手数料などもかかりません。
- 内容を秘密にできる:誰にも知られることなく、一人で作成できます。
- 証人が不要:作成時に誰かに立ち会ってもらう必要はありません。
2-3. 自筆証書遺言のデメリットとリスク
- 方式不備で無効になるリスク:日付の記載漏れや押印忘れなど、わずかなミスで無効になる可能性があります。専門家のチェックがないため、内容が不明確で、法的に実現不可能な内容を書いてしまう恐れもあります。
- 紛失・改ざん・隠匿のリスク:自宅で保管している場合、紛失したり、相続人の誰かに発見され、自分に不都合な内容であったために破棄・改ざんされたりする危険性があります。
- 発見されない可能性がある:せっかく遺言を書いても、相続人に発見されなければ意味がありません。保管場所を工夫したり、信頼できる人に伝えておく必要があります。
- 遺言の有効性を巡る争い:「本当に本人が書いたのか?」「無理やり書かされたのではないか?」など、遺言の有効性そのものが相続人間で争いになるケースが少なくありません。
- 家庭裁判所の「検認」が必要:自筆証書遺言(法務局保管制度を利用しない場合)は、発見後、家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければ、不動産の名義変更や預金の解約などの相続手続きを進めることができません。
2-4. 自筆証書遺言の弱点を補う「法務局保管制度」
これまで述べた自筆証書遺言のデメリット(紛失、改ざん、検認手続き)をカバーするために、2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
これは、作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で預かってもらえる制度です。
【法務局保管制度のメリット】
- 紛失・改ざんのリスクがない:原本を法務局が保管するため、安全です。
- 家庭裁判所の検認が不要になる:相続開始後、面倒な検認手続きを経ずに相続手続きに入れます。これは非常に大きなメリットです。
- 相続人への通知:あらかじめ指定しておけば、遺言者の死亡後、法務局から指定された相続人等へ遺言書が保管されている旨を通知してもらえます。
この制度を利用すれば、自筆証書遺言の利便性を活かしつつ、デメリットを大幅に軽減できます。ただし、法務局はあくまで「保管」してくれるだけで、遺言の内容が法的に有効かどうかをチェックしてくれるわけではない点には注意が必要です。
参考記事:【改正法対応】自筆証書遺言を書くために必要な全知識
3. 公正証書遺言|最も確実で安心な方法
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。公証人は、長年、裁判官や検察官などを務めた法律の専門家であり、その公証人が関与することで、極めて信頼性の高い遺言を作成できます。
3-1. 公正証書遺言の作り方
公正証書遺言の作成は、以下のステップで進めるのが一般的です。
- 遺言内容の検討・必要書類の収集:誰にどの財産を渡すかなどを決め、印鑑証明書や戸籍謄本、財産に関する資料(不動産の登記事項証明書、預金通帳のコピーなど)を準備します。
- 証人2名の依頼:公正証書遺言の作成には、証人2名以上の立会いが必要です。
- 公証人との事前打ち合わせ:公証役場へ連絡し、準備した資料をもとに公証人と遺言の内容について打ち合わせを行います。
- 作成当日:遺言者、証人2名が公証役場へ出向き、公証人が作成した遺言書の原案を読み上げ、内容に間違いがなければ全員が署名・押印して完成です。
なお、病気などで公証役場へ行けない場合は、公証人に出張してもらうことも可能です。
3-2. 公正証書遺言のメリット
- 法的に無効になる心配がほぼない:法律の専門家である公証人が作成するため、方式の不備で無効になることはまずありません。内容についても、法的に実現可能な形で整理してもらえます。
- 遺言の有効性で争いになりにくい:公証人と証人が立会い、本人の意思確認を経て作成されるため、「本人が書いたものではない」といった後日の紛争を防ぐことができます。
- 家庭裁判所の検認が不要:相続開始後、検認手続きなしで、速やかに相続手続きを進めることができます。
- 原本が公証役場に保管される:作成した遺言の原本は、原則として遺言者が亡くなるまで公証役場で厳重に保管されます。紛失や改ざんの心配がありません。
- 心身が衰えても作成可能:字が書けない状態であっても、意思表示ができれば、公証人が代筆する形で作成できます。
3-3. 公正証書遺言のデメリット
- 費用がかかる:公証役場に支払う手数料が必要です。手数料は、相続させる財産の価額に応じて変動します。
- 手間と時間がかかる:必要書類の準備や公証人との打ち合わせなど、作成までに一定の手間と時間がかかります。
- 証人が2名必要:作成に立ち会う証人を2名見つける必要があります。推定相続人や未成年者などは証人になれないという制約があります。信頼できる知人や、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
- 内容を完全に秘密にはできない:作成の過程で、公証人と証人には遺言の内容が知られることになります。
確実性を最優先するならば、公正証書遺言が最も優れた方式といえるでしょう。
参考記事:【保存版】公正証書遺言の作成方法・費用・必要書類を詳細に解説
4. 秘密証書遺言|内容を秘密にしたい場合に
秘密証書遺言とは、遺言者が作成・封印した遺言書を、公証人と証人の前に提出し、その存在を証明してもらう方式の遺言です。
4-1. 秘密証書遺言の作り方
遺言の内容自体は自筆証書遺言と同様に自分で作成します(パソコンでの作成も可)。その遺言書に署名・押印し、封筒に入れて封をし、遺言書で使ったものと同じ印鑑で封印します。
その封書を公証役場へ持参し、公証人1名と証人2名以上の前で、自分の遺言書であることと氏名・住所を述べます。その後、公証人が封紙に日付などを記載し、遺言者、証人とともに署名・押印して完了です。
4-2. 秘密証書遺言のメリット
- 遺言の内容を秘密にできる:公証人や証人にも内容を見られることなく、遺言の存在だけを公的に証明してもらえます。
- 偽造・変造を防げる:封印された状態で公証役場に記録が残るため、偽造や変造のリスクは低くなります。
- 代筆やパソコンでの作成が可能:自筆証書遺言と違い、本文はパソコンで作成しても、第三者に代筆してもらっても構いません(署名は自書が必要)。
4-3. 秘密証書遺言のデメリット
- 方式不備で無効になるリスク:遺言の内容は公証人がチェックしないため、自筆証書遺言と同様に、内容の不備によって無効となる可能性があります。
- 費用と手間がかかる:公証役場の手数料(一律11,000円)がかかり、証人も2名必要です。
- 紛失・発見されないリスク:遺言書そのものは自分で保管するため、紛失したり、死後に発見されなかったりするリスクがあります。
- 家庭裁判所の検認が必要:自筆証書遺言と同様に、相続開始後には家庭裁判所の検認が必要です。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の「中間」のような制度ですが、実際にはそれぞれのデメリットを併せ持ってしまう側面があり、利用されるケースは極めて少ないのが現状です。
5. 3種類の遺言を比較|あなたにおすすめの遺言は?
これまで見てきた3種類の遺言の特徴を一覧表にまとめました。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
| 作成方法 | 全文・日付・氏名を自書、押印 | 公証人が作成 | 自分で作成・封印し、公証人が存在を証明 |
| 費用 | 原則無料(保管制度利用時は3,900円) | 必要(財産額による) | 必要(一律11,000円) |
| 証人 | 不要 | 2名以上必要 | 2名以上必要 |
| 内容の秘密 | 保てる | 公証人と証人には知られる | 保てる |
| 無効リスク | 高い | 極めて低い | 高い |
| 保管 | 自分(法務局も可) | 公証役場 | 自分 |
| 検認 | 必要(法務局保管なら不要) | 不要 | 必要 |
結論:司法書士が「公正証書遺言」をおすすめする理由
3つの遺言を比較してきましたが、最もおすすめするのは「公正証書遺言」です。
なぜなら、遺言を作成する一番の目的は、「ご自身の最後の想いを確実に実現し、残された家族の円満な相続をサポートすること」にあるからです。
自筆証書遺言は手軽ですが、方式の不備で無効になったり、その有効性を巡って家族が争ったりするケースが後を絶ちません。せっかく想いを込めて書いた遺言が、かえって争いの火種になってしまっては、本末転倒です。
公正証書遺言は、確かに費用や手間がかかります。しかし、その費用は、**将来の相続トラブルを防ぎ、ご家族がスムーズに手続きを進めるための「安心料」**と考えることができます。法的に確実で、執行力も高く、ご家族の負担を最も軽減できる方法なのです。
あなたの想いを、最も確実な形で未来へつなぐために。ぜひ、公正証書遺言の作成をご検討ください。
6. 遺言作成で迷ったら専門家へ相談を
遺言の作成は、ご自身の財産と、大切なご家族の将来に関わる重要な法律行為です。
「どの遺言を選べばいいかわからない」
「自分の考えた内容で法的に問題ないか不安」
「必要書類の集め方や、手続きの進め方が複雑で難しい」
このようにお悩みの方は、ぜひ一度、司法書士などの専門家にご相談ください。
私たち専門家は、次のようなサポートを通じて、あなたの遺言作成を全面的にバックアップします。
- あなたのご希望やご家族の状況に最適な遺言方式のご提案
- 法的に有効で、想いを実現できる遺言内容のコンサルティング
- 公正証書遺言作成に必要な、戸籍謄本などの各種書類の収集代行
- 公証役場との打ち合わせ調整
- 公正証書遺言作成時の証人の手配
初回相談は無料で行っている事務所も多くあります。一人で悩まず、まずは専門家の話を聞いてみることから始めてみてはいかがでしょうか。
7. まとめ
今回は、遺言の3つの種類、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」について解説しました。
- 自筆証書遺言:手軽だが無効リスクあり。法務局保管制度の利用がおすすめ。
- 公正証書遺言:最も確実で安心な方法。専門家として一番におすすめ。
- 秘密証書遺言:内容は秘密にできるが、デメリットも多く利用は稀。
遺言は、単なる事務的な手続きではありません。ご自身の人生の集大成であり、愛するご家族へ贈る「最後のラブレター」ともいえます。
この記事が、あなたのその大切な想いを、最適な形で残すための一助となれば幸いです。







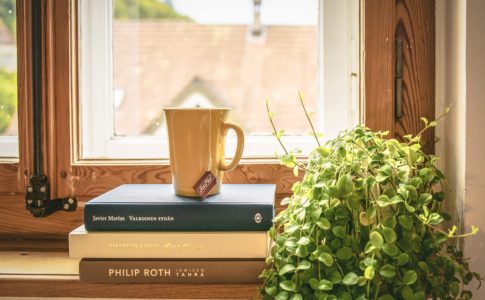





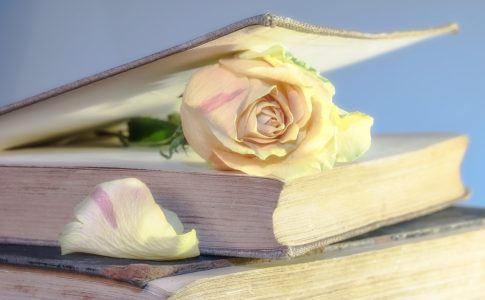


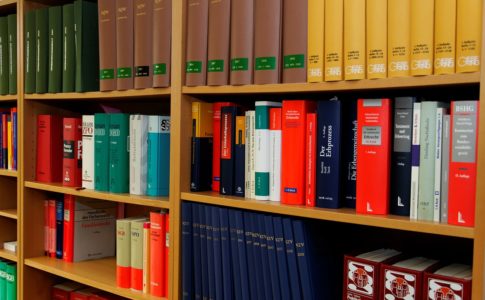



コメントを残す