「長年、私の世話を献身的にしてくれた長男のお嫁さん。本当に感謝しているから、財産の一部を遺してあげたい。」
ご高齢の方から、このようなご相談をいただくことがあります。しかし、多くの方が同時に「法律上、息子の嫁は相続人ではないと聞いた。どうすれば想いを実現できるのだろうか?」という疑問や不安を抱えていらっしゃいます。
この記事では、法定相続人ではない「長男のお嫁さん」へ、ご自身の意思で財産を渡すための具体的な方法と、その想いを確実にする「公正証書遺言」について、当事務所で実際にサポートさせていただいたご相談事例をもとに、わかりやすく解説します。
ご自身の感謝の気持ちを、未来へ、そして大切な方へ、確実につなぐための一助となれば幸いです。
目次
1.ご相談事例:「献身的な嫁に、どうしても財産を遺したい」Aさんの想い
先日、当事務所へお越しになったAさん(80代・女性)からのご相談です。
Aさんは数年前にご主人を亡くされ、現在は長男ご夫婦と同居されています。特に、長男のお嫁さんであるBさんは、毎日の食事の支度から、買い物、病院への付き添いまで、ご自身のことを本当の親のように親身になってお世話をしてくれていました。
「長男に財産が渡るのは当然ですが、それと同じくらい、直接お世話になっているBさんにも、感謝の気持ちとして預貯金の一部を確実に渡したいのです。でも、万が一、長男が私より先に亡くなってしまったら、Bさんには何も渡らなくなると聞きました。それに、息子夫婦が離婚する可能性もゼロではないし、他の親族から何か言われるのも心配で…。」
Aさんの願いは切実でした。それは、「法定相続人ではないBさんへ、他の相続人とのトラブルを避けながら、確実に財産を遺すこと」。
この想いを実現するために、当事務所は「公正証書遺言」の作成をご提案しました。
2.【基本の解説】なぜ「長男の嫁」は財産を相続できないのか?
Aさんが心配されていた通り、どれだけ身近でお世話になっていても、法律上、「子の配偶者(長男のお嫁さん)」は法定相続人には含まれません。
法定相続人とは?
民法で定められた、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つ人のことを「法定相続人」といいます。法定相続人になれる人には、順位が定められています。
- 常に相続人: 配偶者(夫または妻)
- 第1順位: 子(子が既に亡くなっている場合は孫)
- 第2順位: 直系尊属(父母、祖父母)
- 第3順位: 兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合はその子である甥・姪)
このように、相続人に「子の配偶者」は含まれていません。そのため、何もしなければ、Aさんが亡くなった後、Aさん名義の財産がBさんに渡ることはないのです。
では、どうすればよいのでしょうか。そこで登場するのが「遺言」です。
3.法定相続人以外に財産を渡す唯一の方法「遺贈」とは
遺言書を用いることで、法定相続人ではない人にも財産を譲り渡すことができます。これを「遺贈(いぞう)」といいます。
- 相続: 法定相続人が財産を受け継ぐこと。
- 遺贈: 遺言によって、特定の人(法人含む)に無償で財産を譲ること。
AさんがBさんに財産を渡すことは、この「遺贈」にあたります。そして、遺贈を行うためには、必ず遺言書が必要になります。遺言書は、ご自身の最終的な意思表示であり、法定相続のルールよりも優先される、非常に強い力を持つのです。
参考記事:【完全ガイド】相続人以外に財産を遺す「遺贈」とは?司法書士が書き方・税金・注意点を徹底解説
4.なぜ「公正証書遺言」がトラブル防止に最適なのか?
遺言書には、自分で書く「自筆証書遺言」などいくつかの種類がありますが、当事務所はAさんに「公正証書遺言」の作成をお勧めしました。特に、相続人以外への遺贈を考えている場合や、相続トラブルを未然に防ぎたい場合には、最も確実で安心な方法といえます。
公正証書遺言には、主に4つの大きなメリットがあります。
メリット1:形式不備で無効になるリスクがゼロ
自筆証書遺言は、日付の記載漏れや押印ミスなど、法律で定められた形式を一つでも満たさないと、それだけで無効になってしまいます。せっかく書いた想いが、小さなミスで台無しになることも少なくありません。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成に関与するため、形式不備で無効になる心配がありません。
メリット2:相続トラブルの予防効果が高い
遺言書をめぐるトラブルでよくあるのが、「本人の意思で書いたものではない」「無理やり書かされたのではないか」といった主張です。
公正証書遺言は、公証人が遺言者本人と直接面談し、その意思能力や内容をしっかり確認した上で作成します。そのため、遺言書の信頼性が非常に高く、後々の紛争を強力に防ぐことができます。
メリット3:相続開始後の手続きがスムーズ
自筆証書遺言の場合、遺言者の死後、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。これは、相続人全員に遺言書の存在を知らせ、その内容を確認する手続きで、時間も手間もかかります。
公正証書遺言は、この検認手続きが不要です。相続開始後、すぐに不動産の名義変更や預貯金の解約といった手続きを進めることができ、相続人の負担を大きく軽減します。
メリット4:紛失・改ざんの心配がない
作成された公正証書遺言の原本は、公証役場で厳重に保管されます。自宅で保管する自筆証書遺言のように、紛失したり、誰かに隠されたり、書き換えられたりする心配が一切ありません。
Aさんの「他の親族と揉めたくない」というご希望を叶え、Bさんへ確実に財産を渡すために、公正証書遺言は最適な選択肢だったのです。
5.司法書士による公正証書遺言作成サポートの流れ
当事務所は、ご依頼者様の想いを法的に有効な形で実現するため、以下のようなサポートを行いました。
Step1:丁寧なヒアリング
まず、Aさんが「誰に」「どの財産を」「どれくらい」遺したいのか、そして「なぜそうしたいのか」という背景にある想いをじっくりと伺いました。ご家族構成や財産全体の状況もお聞きし、最適な遺言内容を一緒に考えます。
Step2:財産調査と必要書類の収集サポート
遺言書に正確な財産内容を記載するため、預貯金の通帳や不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)など、必要な資料のリストアップや取得のサポートを行いました。
Step3:遺言の文案作成 Aさんのご希望に基づき、法的に明確で、誰が読んでも誤解の生じない遺言の文案を作成しました。 特に重要視したのが「付言事項」です。
これは、法的な効力はありませんが、遺言者が家族へメッセージを遺せる部分です。「なぜBさんに財産を遺すことにしたのか」について、Aさんの「長年の感謝の気持ち」を具体的に記すことをご提案しました。この一文があるだけで、他の相続人が遺言内容を知ったときの心情は大きく変わります。
Step4:公証役場との事前打ち合わせ
作成した文案や必要書類を、司法書士が公証役場へ持参し、公証人と事前に打ち合わせを行います。これにより、当日の手続きが非常にスムーズに進みます。ご依頼者様が公証人と直接何度もやり取りする手間を省くことができます。
Step5:公証役場での作成当日
当日は、Aさん、私(司法書士)、そしてもう1名の証人の合計3名で公証役場へ向かいました。公証人がAさんに遺言内容を読み聞かせ、Aさんの最終意思を確認した後、署名・押印をして完成です。司法書士が同行することで、Aさんも終始リラックスしたご様子でした。
証人には、推定相続人や受遺者などはなれません。本件では、当事務所がもう一人の承認を手配しました。
Step6:完成後の謄本の保管
完成した遺言書の「正本」と「謄本」(いずれも写し)を受け取り、Aさんにお渡ししました。原本は公証役場で安全に保管されるため、ご自宅で保管する必要はありません。
6.まとめ:感謝の気持ちを、確実な形で未来へ
後日、Aさんからは「ずっと心に引っかかっていたことが解決して、本当に安心しました。これでBさんにも顔向けができます。専門家の方に頼んで、本当によかったです。」という、晴れやかなお言葉をいただきました。
ご自身の人生を振り返り、お世話になった方へ感謝の気持ちを伝えたい、形として遺したいと考えるのは、とても自然で尊い想いです。その想いを、法的なルールの中で、争いのない円満な形で実現するのが遺言書の役割です。
特に、法定相続人ではない方へ財産を遺したいとお考えの場合には、トラブル防止の観点からも、信頼性の高い公正証書遺言の作成をお勧めします。
当事務所では、お一人おひとりの想いに真摯に耳を傾け、その想いが最も良い形で実現できるよう、全力でサポートいたします。遺言書の作成や相続について、少しでもご興味やご不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。







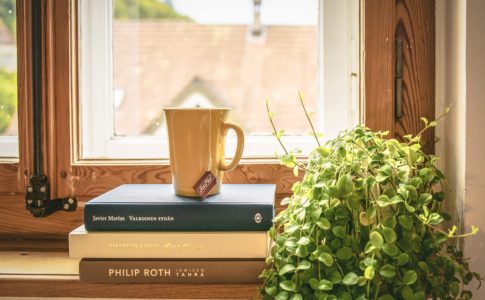














コメントを残す