「相続が発生したけれど、相続人の一人と長年連絡が取れず、手続きが全く進まない…」
このようなご相談は、決して珍しいものではありません。遺産分割協議は相続人全員の参加が原則のため、一人でも行方不明の方がいると、預貯金の解約や不動産の名義変更(相続登記)ができず、多くの方が途方に暮れてしまいます。
特に2024年4月からは相続登記が義務化され、手続きを放置しておくことへの不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、このような状況でも、法的な手続きを踏むことで解決への道筋をつけることができます。
この記事では、相続人の中に行方不明者がいる場合に「不在者財産管理人」という制度を活用し、遺産分割協議を成立させ、最終的に不動産の売却まで実現した解決事例を、司法書士の視点から分かりやすく解説します。
目次
1. なぜ、相続人に行方不明者がいると手続きが止まってしまうのか?
そもそも、なぜ相続人の一人が行方不明だと、あらゆる相続手続きがストップしてしまうのでしょうか。その理由は、「遺産分割協議」のルールにあります。
遺産分割協議は「相続人全員」の合意が必須
遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、どの相続人が、どのように引き継ぐのかを話し合う手続きです。この協議は、法律上の相続人全員が参加し、全員が合意しなければ成立しません。
たとえ、他の相続人全員が「この内容で進めよう」と納得していても、行方不明の相続人一人の合意(署名・押印)がなければ、遺産分割協議書は法的に無効です。
その結果、次のような問題が発生します。
- 預貯金の解約・払い戻しができない
- 不動産の名義を相続人に変更(相続登記)できない
- 株式などの有価証券の名義変更ができない
- 不動産を売却して現金で分けたいと思っても、売却できない
特に不動産は、相続登記ができないまま放置されると、管理が難しくなり、いわゆる「空き家問題」の原因にもなりかねません。
参考記事:遺産相続の最重要ポイント-遺産分割協議の知識と進め方
2. 解決の鍵は「不在者財産管理人」
このような状況を打開するための有効な手段が、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらう手続きです。
「不在者財産管理人」とは?
不在者財産管理人とは、その名の通り、行方不明になっている方(不在者)の代わりに、その方の財産を管理・保存する人のことです。家庭裁判所が、申立てに基づいて選任します。
重要なのは、この不在者財産管理人が、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加できるという点です。
管理人が不在者の代理人として協議に参加し、遺産分割協議書に署名・押印することで、相続人全員の合意があったものとみなされ、協議を有効に成立させることができるのです。
どんな場合に利用できる?
この制度を利用するための「不在者」とは、「従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みがない者」とされています。
「生死が不明」である必要はなく、「生きているのは分かっているが、どこに住んでいるか見当もつかない」というケースでも、この制度を利用できます。
3. 【解決事例】不在者財産管理人選任から不動産売却までの具体的な流れ
それでは、当事務所で実際に取り扱ったご相談をモデルケースとして、手続きの具体的な流れを見ていきましょう。
ご相談の状況
- ご依頼者: Aさん(長男)
- 被相続人: Aさんの父
- 相続人: 母、Aさん、弟Bさんの3名
- お悩み: 弟Bさんが10年以上前から音信不通。親族の誰も現在の連絡先や居住地を知らない。父が遺した実家の土地建物を売却し、その代金を3人で分けたいが、Bさんがいないため何もできずに困っている。
ステップ1:ご相談と方針の決定
まず、Aさんから詳しい状況をヒアリングしました。弟Bさんが不在者にあたる可能性が高いと判断し、解決策として「不在者財産管理人」の選任申立てを家庭裁判所に行う方針をご提案。手続きの全体像、期間の目安、概算費用について丁寧にご説明し、正式にご依頼いただきました。
ステップ2:不在者財産管理人選任の申立て
不在者財産管理人の選任は、不在者(Bさん)の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
申立てには、多くの書類が必要となります。
- 申立書
- 申立人や不在者の戸籍謄本、住民票除票
- 不在の事実を証明する資料
- 遺産の内容がわかる資料(例:不動産の登記事項証明書、預金通帳のコピーなど)
- 管理人候補者の住民票など
当事務所では、これらの複雑な必要書類の収集サポートから、申立書の作成まで、すべて代行いたしました。特に「不在の事実を証明する資料」は、何を用意すればよいか分かりにくい部分ですが、本件の事情に合わせて適切な資料を準備しました。
ステップ3:家庭裁判所による審理と管理人の選任
申立て後、家庭裁判所は本当にBさんが「不在者」にあたるのか、財産管理の必要があるのかなどを審理します。場合によっては、裁判所の調査官による調査が行われます。
審理の結果、申立てが認められると、家庭裁判所は不在者財産管理人を選任します。管理人には、申立人が推薦した候補者(利害関係のない親族など)や、弁護士・司法書士といった専門家が選ばれるのが一般的です。
今回のケースでは、利害関係の公平性を保つため、当事務所とは別の司法書士が管理人として選任されました。
ステップ4:遺産分割協議と「権限外行為許可」の申立て
管理人が選任されたら、いよいよ遺産分割協議です。Aさん、お母様、そしてBさんの代理人である不在者財産管理人の3者で協議を行いました。
ここで重要なポイントがあります。遺産分割協議のように「不在者の財産そのものを処分する行為」は、管理人の基本的な権限(保存行為)を超えています。そのため、協議を行う前に、あらかじめ家庭裁判所に対して「権限外行為許可」の申立てを行い、「この内容で遺産分割協議を進めても良いか」という許可を得る必要があります。
協議の内容は、不在者であるBさんの利益を不当に害するものであってはなりません。今回は、法定相続分(Bさんの相続分は1/4)が確保される形で不動産を売却し、代金を分けるという内容で協議案を作成し、無事に家庭裁判所の許可を得ることができました。
ステップ5:遺産分割協議の成立と相続登記
家庭裁判所の許可が下りた後、正式に遺産分割協議書を作成。Bさんの署名押印欄には、不在者財産管理人が記名し、裁判所に届け出た印鑑を押印します。
この完成した遺産分割協議書と、家庭裁判所の選任審判書、権限外行為許可書などを添付して、法務局に相続登記を申請。これにより、実家の不動産の名義を、売却のために相続人の代表(今回はAさん)へ変更することができました。
ステップ6:不動産の売却と財産の分配・管理
相続登記完了後、Aさんが窓口となり、不動産会社を通じて実家を売却。売却代金は、遺産分割協議の内容に基づき、お母様とAさん、そしてBさんの分として不在者財産管理人にそれぞれ分配されました。
Bさんの取得分である売却代金は、今後Bさんが見つかるまで、不在者財産管理人が責任をもって管理することになります。
4. 不在者財産管理人制度の注意点と費用
非常に便利な制度ですが、利用にあたってはいくつか注意すべき点があります。
- 時間がかかる
申立ての準備から管理人が選任されるまでに3ヶ月~半年程度、その後の遺産分割協議や各種許可の申立てを含めると、解決まで半年から1年以上かかることも珍しくありません。 - 費用がかかる
- 申立て実費: 収入印紙800円と、連絡用の郵便切手代(数千円程度)が必要です。
- 予納金: 管理人の報酬や経費に充てるため、数十万円から100万円程度の現金をあらかじめ家庭裁判所に納めるよう指示される場合があります。
- 専門家への依頼費用: 申立書作成などを司法書士や弁護士に依頼する場合の報酬です。
- 希望通りの分割ができるとは限らない
不在者財産管理人は、あくまで不在者の利益を守る立場です。そのため、不在者の法定相続分を大きく下回るような、一方的に不利な内容の遺産分割協議は、家庭裁判所が許可しません。
5. まとめ:相続人に行方不明者がいても、諦めないでください
相続人に行方不明の方がいると、法的な知識がないままでは、どうすることもできずに時間だけが過ぎてしまいがちです。
しかし、今回ご紹介した「不在者財産管理人」の制度を使えば、時間はかかりますが、着実に手続きを進め、遺産分割や相続登記を実現することができます。手続きは複雑で専門的な判断を要する場面も多いため、一人で抱え込まずに、まずは専門家である司法書士にご相談ください。
当事務所では、不在者財産管理人の選任申立てから、その後の遺産分割協議のサポート、相続登記、不動産売却に関する手続きまで、ワンストップで対応することが可能です。ご相談者様のお気持ちに寄り添いながら、最善の解決策をご提案いたします。
まずはお気軽にお問い合わせいただき、現状のお悩みをお聞かせください。





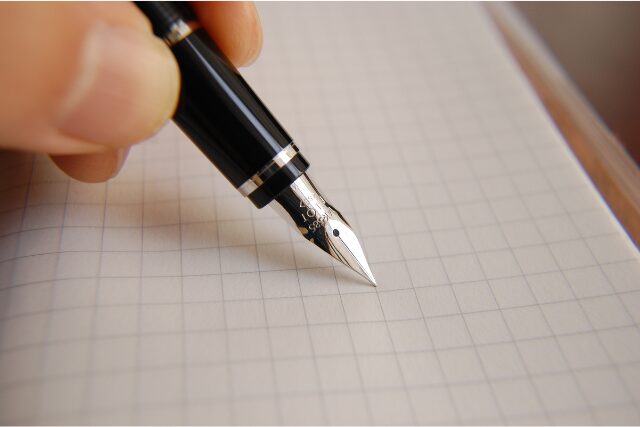

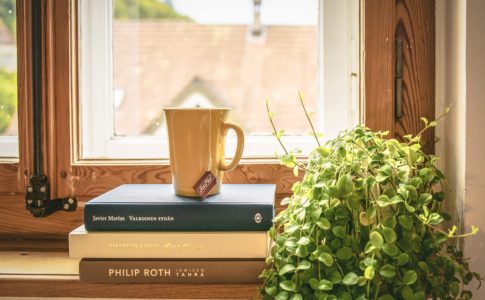





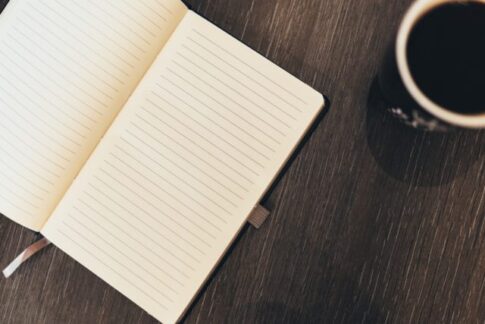








コメントを残す