不動産を相続したものの、「住む予定がない」「遠方で管理が難しい」「税金の負担が心配」といった理由から、売却を検討する方は少なくありません。相続によって手に入れた不動産が、必ずしも生活に必要なものであるとは限らず、空き家のまま放置しておくことで固定資産税や管理費用がかさみ、結果的に負担になるケースも多く見られます。
ただし、売却の前提として避けて通れないのが、相続登記(名義変更)の手続きです。相続登記を行わずに不動産を売却することは、できません。
「どんな手順で進めればいい?」「登記せずに売却できるの?」といった疑問をお持ちの方のために、本記事では司法書士が実際の相談事例を交えながら、相続不動産を売却するための手続きの流れ、必要な書類、税金の注意点、不動産会社との連携方法などを詳しく解説します。
また、2024年からは相続登記が義務化されたため、より一層「早めの対応」が重要です。ぜひ参考にしてください。
目次
1. 相続不動産は名義変更しないと売却できない
結論からいえば、相続登記を済ませない限り、不動産の売却はできません。登記簿上の所有者が亡くなったままでは、法的にその不動産を処分することができず、売買契約を結ぶことも、所有権移転登記を行うこともできません。
トラブルを避けるためにも、まずは誰が相続するのかを明確にし、その方の名義に変更する必要があります。
登記が完了すれば、売却の準備が本格的に進められるようになります。不動産会社への相談や、相場の確認など、次のステップに進むためにも登記は不可欠です。
関連記事:土地・家などの不動産を相続した場合は、相続登記をしましょう
2. 相続した不動産を売却するまでの全体の流れ
相続不動産を売却するには、次のような手順を踏むことが一般的です。それぞれの段階で必要な準備や注意点があるため、順を追って確認しておきましょう。
- 相続人の調査・確定
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を取得し、すべての相続人を明確にします。法定相続人の漏れがあると、後の協議や登記で問題が発生するため、きちんと確認する必要があります。 - 遺産分割協議
相続人全員で話し合い、不動産を含む財産を誰がどのように取得するかを決定。合意内容を書面(遺産分割協議書)にまとめます。協議がまとまらない場合、家庭裁判所での調停や審判に進むこともあります。 - 相続登記(名義変更) 法務局で不動産の登記名義を相続人の名義に変更する手続きを行います。専門家に依頼することで、複雑な書類作成や添付書類の不備を防ぐことができます。
- 不動産会社への査定依頼と媒介契約の締結
複数の不動産会社に査定を依頼し、条件に合う会社と媒介契約を締結します。専任媒介・一般媒介などの契約形態にも注意しましょう。査定価格の根拠を比較することも大切です。 - 買主との売買契約の締結
買主と売却条件を調整し、合意が成立すれば売買契約を締結します。契約書の内容や支払方法、引き渡し時期なども重要なポイントです。 - 引き渡しと所有権移転登記
売却代金を受領し、買主への所有権移転登記を行います。司法書士が決済日に立ち会い、登記と代金のやり取りを同時に進めるのが一般的です。 - 譲渡所得税の申告と納税
売却により利益が出た場合は、翌年の確定申告で譲渡所得税を納めます。必要経費や特例を適用することで課税額を軽減できます。
3. 実際の相談事例:空き家を売却してスムーズに解決
- 相談内容
「父名義の空き家を相続したが、自分で住む予定はなく、維持費もかかるので売却したい」というご相談でした。 - 状況
相続人は兄弟3人。遺産分割協議により、空き家は長男が相続することで全員が合意しました。被相続人の名義のままだったため、まずは相続登記から取り掛かる必要がありました。 - 対応と結果
司法書士が相続登記を担当し、戸籍の取得や協議書の作成もサポート。不動産会社2社に査定を依頼し、そのうち1社と専任媒介契約を締結。1,500万円で売却が成立しました。登記から売却完了まで約3か月、スムーズに進めることができました。
このように、事前の協議と適切な専門家のサポートがあれば、相続不動産の売却もスムーズに進めることができます。税務面の相談も早めに行っておくと安心です。
4. 売却後にかかる譲渡所得税と節税対策
不動産を売却して利益(譲渡益)が出た場合は、譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)が発生します。課税額は利益に対しておよそ20.315%とされており、予想外の出費になることもあります。
(参考)国税庁 譲渡所得税の計算について
節税に活用できる主な特例
- 空き家の3,000万円特別控除
旧耐震基準の住宅を相続し、一定の条件下で売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。
(参考)国税庁 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 - 取得費加算の特例
相続税を支払った場合、その一部を譲渡所得の取得費に加算することができ、税負担を軽減できます。
これらの特例は適用条件が細かく定められているため、売却前に税理士と連携しながら準備を進めることをおすすめします。納税時期や必要書類の確認も忘れずに行いましょう。
5. 相続登記をスムーズに行うためのポイント
相続登記には多くの書類が必要で、戸籍の収集や協議書の作成に時間がかかることもあります。以下のポイントを押さえておくと手続きがスムーズに進みます。
- 代表相続人を決めておく
相続人のなかで手続きを主導する人物を決めておくと、各所との連絡や書類作成が効率的に進みます。 - 必要書類を早めにそろえる
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産取得者の住民票 ・固定資産評価証明書 ・遺産分割協議書(全員の署名・押印)
・相続人全員の印鑑証明書
- 法定相続情報一覧図の活用
法務局で無料で発行できる資料で、複数の手続きで戸籍一式の代わりとして使用できます。金融機関での口座解約や預貯金の手続きにも利用できます。
代表相続人を決めた場合は、換価分割の遺産分割協議書を作成しましょう
換価分割とは、不動産などの相続財産を一旦売却し、売却代金を相続人で分配する方法です。協議書には「売却後に得た金額を何割ずつ分けるか」や「代表相続人が売却を進める権限を持つこと」などを明記します。これにより、他の相続人が手続きを個別に関与する必要がなくなり、売却がスムーズに進みます。
関連記事:遺産分割協議をしたら必ず作成する書類・遺産分割協議書について
6. よくあるご質問(FAQ)
Q. 相続登記をしないまま不動産を売却できますか?
A. できません。売買の前には、必ず相続登記をする必要があります。
Q. 売却益には税金がかかりますか?
A. はい。譲渡所得がある場合、譲渡所得税がかかります。ただし、特例を利用することで軽減できる可能性があります。
Q. 相続登記の費用はどれくらいかかりますか?
A. 司法書士報酬8万〜15万円前後に加えて登録免許税(不動産評価額の0.4%)がかかります。
Q. 司法書士に依頼するメリットは?
A. 書類不備や申請ミスを防ぎ、売却までのスケジュールが円滑に進みます。不動産会社・税理士との連携もスムーズです。
Q. 不動産の売却価格はどのように決まりますか?
A. 立地や築年数、近隣の取引事例、需要などをもとに不動産会社が査定します。複数社に依頼して比較するのがおすすめです。
Q. 相続登記を自分で行うことは可能ですか?
A. 可能ですが、必要書類が多く、法的な知識も求められるため、専門家に依頼することで安心して手続きを進められます。
7. 相続登記義務化に注意!罰則があるので早めの対応を
2024年4月1日から、相続登記は義務化されました。相続が発生してから3年以内に登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記を行わずに放置してしまうと、将来的に相続人が増えたり、協議がまとまらなくなったりと、手続きが非常に複雑化する恐れがあります。また、固定資産税の納付書が相続人の誰にも届かず、税の滞納が発生するケースも見受けられます。
早めに登記を済ませることで、売却の選択肢を確保し、不要なトラブルを未然に防ぐことができます。
みな司法書士法人では、相続登記はもちろん、売却のための不動産会社との連携、税務相談までワンストップでサポートしています。相続・売却のご相談があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。







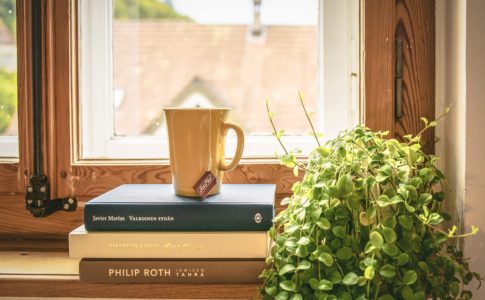














コメントを残す