相続手続きを進める中で、「相続放棄」と「遺留分の放棄」という言葉に出会うことがあります。この二つは響きが似ているため混同されがちですが、法律上の意味や効果は全く異なります。
この違いを正しく理解せずに手続きを進めてしまうと、「借金を免れるはずが、できなかった」「もらえるはずの財産を失ってしまった」といった予期せぬ事態に陥る可能性があります。
この記事では、相続問題に詳しい司法書士が、相続放棄と遺留分の放棄の違いを明確にし、どちらの手続きがどのような状況で必要になるのか、メリット・デメリット、そして具体的な手続きの流れまで、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。
目次
まずは結論!相続放棄と遺留分の放棄の決定的な違い
| 比較項目 | 相続放棄 | 遺留分の放棄 |
| 目的 | 借金などマイナスの財産を含め、すべての相続権を手放す | 最低限保障される相続分(遺留分)の権利だけを手放す |
| 効果 | 最初から相続人ではなかったことになる | 相続人の地位は失わない |
| 借金の放棄 | 可能 | 不可能 |
| 手続き時期 | 相続開始後**(死後)のみ** | 相続開始前(生前)も後(死後)も可能 |
| 家庭裁判所 | 必須(相続開始後3ヶ月以内に申述) | 生前に行う場合は必須、死後に行う場合は不要 |
| 主な選択理由 | ・多額の借金を相続したくない ・相続トラブルに一切関わりたくない | ・特定の相続人に事業や財産を集中させたい ・生前に贈与などで十分な財産をもらった |
1. 相続放棄とは?借金も資産も「すべて」を手放す手続き
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)が残したプラスの財産(預貯金、不動産など)とマイナスの財産(借金、ローンなど)のすべてを放棄する法的な手続きです。
この手続きが完了すると、「初めから相続人ではなかった」とみなされます。そのため、被相続人の財産に対する一切の権利と義務から解放されます。
1-1. 相続放棄の最大のメリットは「借金」からの解放
相続放棄が選ばれる最も一般的な理由は、被相続人の借金を相続したくないというケースです。相続はプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐのが原則です。もし被相続人に多額の負債があれば、相続人がその返済義務を負うことになります。
このマイナスの財産を引き継がずに済む唯一の方法が「相続放棄」です。借金から逃れたいと考えるのであれば、迷わず相続放棄の手続きを検討する必要があります。
1-2. 相続放棄の注意点:期限と撤回不可
相続放棄を検討する際には、以下の重要な注意点があります。
- 3ヶ月の期限(熟慮期間):相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間を過ぎると、単純承認したとみなされ、借金も含めてすべてを相続することになる可能性があります。
- 原則として撤回できない:一度、相続放棄が受理されると、後から「やはり財産が欲しくなった」と思っても、原則として撤回することはできません。
- 生命保険金や遺族年金は別:相続放棄をしても、受取人として指定されている生命保険金や、受給権者となっている遺族年金などは、相続財産とは見なされないため受け取ることができます。
2. 遺留分の放棄とは?「最低限の相続権」だけを手放す手続き
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、親など)に法律上保障されている、最低限の財産の取り分のことです。
被相続人は遺言によって財産を自由に処分できますが、「全財産を愛人に譲る」といった遺言がまかり通ると、残された家族の生活が脅かされる可能性があります。このような事態を防ぎ、相続人の生活を保障するために遺留分という制度が存在します。
そして、この遺留分という「権利」を自らの意思で手放すことが「遺留分の放棄」です。
遺留分の放棄をしても、相続人としての地位を失うわけではありません。あくまで、遺言などによって自分の遺留分が侵害された場合に、「その侵害額を請求する権利(遺留分侵害額請求権)」を失うだけです。
関連記事:【図表付き】遺留分の割合、計算方法をケース別に解説
3. 手続き可能な時期の違い:生前にもできる遺留分放棄
相続放棄と遺留分の放棄の大きな違いの一つが、手続きが可能な時期です。
- 相続放棄:被相続人の死亡後(相続開始後)にしかできません。親が存命中に多額の借金があると分かっても、生前に相続放棄をすることは不可能です。
- 遺留分の放棄:被相続人の生前(相続開始前)にも、死後(相続開始後)にも行うことができます。
3-1. 【生前】の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必須
被相続人が生きている間に遺留分を放棄する場合には、必ず家庭裁判所の許可を得る必要があります。当事者間で「遺留分を放棄します」という念書を交わしただけでは、法的な効力は生じません。
これは、被相続人からの不当な圧力によって、相続人が本来持つべき重要な権利を安易に手放してしまうことを防ぐためです。
民法第1049条
- 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
- 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
家庭裁判所が許可を出す際は、以下の点を慎重に審査します。
- 本人の自由な意思か:誰かに強制されたものではないか。
- 理由の合理性・必要性:なぜ放棄が必要なのか(例:特定の相続人に事業を継がせるためなど)。
- 代償の有無:放棄する代わりに、相応の生前贈与を受けているかなど。
手続きの概要(生前の遺留分放棄)
- 申立人:遺留分を放棄する相続人本人
- 申立先:被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
- 必要な費用:収入印紙800円分、連絡用の郵便切手代
- 必要な書類:申立書、被相続人と申立人の戸籍謄本など
3-2. 【死後】の遺留分放棄は家庭裁判所の許可不要
被相続人が亡くなった後に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可は不要です。
遺言の内容を確認した上で、遺留分を請求する意思がない場合や、他の相続人との話し合いで円満に合意した場合には、遺留分侵害額請求権を行使しない旨を相手方に伝えるだけで足ります。ただし、後日のトラブルを防ぐため、書面で合意内容を残しておくことが望ましいでしょう。
4. よくある質問(Q&A)
- Q1. 相続放棄をすれば、借金の督促は来なくなりますか?
A1. はい、相続放棄が家庭裁判所に受理されると、あなたは法的に相続人ではなくなるため、債権者(貸主)はあなたに返済を請求できなくなります。もし受理後に督促が来た場合は、「相続放棄受理通知書」を提示することで支払いを拒否できます。 - Q2. 生前に「遺留分を放棄しろ」と親に言われました。応じないとダメですか?
A2. いいえ、応じる義務は全くありません。遺留分の放棄は、あくまでご本人の自由な意思に基づくものです。もし放棄に応じる場合でも、その代償として十分な生前贈与を受け取るなど、慎重に判断することが重要です。納得できない場合は、安易に同意せず、専門家に相談することをお勧めします。 - Q3. 親の事業を継ぐ代わりに、他の兄弟に遺留分を放棄してもらいたいです。どうすればいいですか?
A3. まずは、事業承継の必要性や、ご兄弟への代償(相応の金銭の支払いなど)について十分に話し合うことが大切です。全員の合意が得られたら、家庭裁判所に「遺留分放棄の許可申立て」をご兄弟自身が行うことになります。手続きが複雑なため、司法書士などの専門家がサポートすることが一般的です。
5. まとめ:あなたの状況に合う手続きはどっち?
最後に、相続放棄と遺留分の放棄のポイントを改めて整理します。
- 借金から逃れたいなら → 相続放棄
- 被相続人にプラスの財産より明らかにマイナスの財産(借金)が多い場合は、相続放棄が第一の選択肢です。
- 相続トラブルに一切関わりたくない場合も有効です。
- 特定の相続人に財産を集中させたいなら → 遺留分の放棄
- 家業を継ぐ長男にすべての財産を遺したい、といった被相続人の意思を実現するために、他の相続人が協力する形で選択されることがあります。
- 遺留分を放棄しても、借金を免れることはできません。
「相続放棄」と「遺留分の放棄」は、あなたの財産状況や権利に重大な影響を及ぼす重要な法的手続きです。どちらの手続きを選ぶべきか、少しでも迷いや不安がある場合は、ご自身の判断だけで進めず、司法書士のような相続の専門家にご相談ください。
この記事が、あなたの相続に関する疑問解消の一助となれば幸いです。







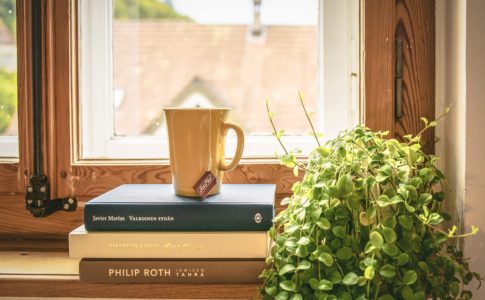














コメントを残す