「実家の土地、そういえば名義は誰になっているんだろう?」
「先祖から受け継いできた不動産があるけれど、手続きが面倒でそのままにしている…」
2024年4月1日から相続登記が義務化されたことで、このように感じている方も多いのではないでしょうか。これまで任意だった不動産の名義変更(相続登記)が法律上の義務となり、正当な理由なく怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性も出てきました。
しかし、長年手続きがされていなかった不動産ほど、いざ名義変更をしようとすると、予想以上に複雑な問題に直面することが少なくありません。
本記事では、当事務所が実際にサポートさせていただいた「数世代にわたって名義変更が放置されていた不動産」の相続登記を、無事に完了させた事例をご紹介します。
この記事を読めば、なぜ相続登記を放置すると手続きが複雑になるのか、そして司法書士がどのように問題を解決していくのか、具体的なイメージを掴んでいただけるはずです。ご自身の状況と重なる部分がある方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
そもそも「相続登記の義務化」とは?制度をおさらい
まずは、今回の事例の背景ともなる「相続登記の義務化」について、簡単におさらいしておきましょう。
相続登記の義務化とは、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、法務局へその旨を登記(名義変更)することを義務付ける制度です。
なぜ義務化されたのか?
この制度が導入された最大の理由は、全国で深刻化する「所有者不明土地問題」を解決するためです。
これまでは相続登記が任意だったため、登記簿上の名義が何十年も前の亡くなった方のまま、というケースが多発していました。すると、現在の本当の所有者が誰なのか分からなくなり、公共事業や災害復旧、民間での土地活用などを進める上での大きな障壁となっていたのです。
そこで、相続が発生した際にきちんと登記をしてもらうことで、不動産の所有者情報を最新の状態に保ち、社会経済活動を円滑にすることが目的とされています。
相続人が知っておくべきポイント
- 対象者: 不動産を相続したすべての人(過去に発生した相続も対象)
- 期限: 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内
- 罰則: 正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象
「3年」という期間は長いように思えるかもしれませんが、後述する事例のように、相続関係が複雑化しているケースでは、準備に1年以上かかることも珍しくありません。「まだ大丈夫」と先延ばしにせず、早めに現状を把握することが重要です。
参考記事:【2024年義務化】相続登記の期限はいつまで?放置で過料も!5つのデメリットと対策を司法書士が徹底解説
【解決事例】曽祖父名義の土地。相続人は20人以上に…
ご相談の経緯
今回ご相談に見えたのは、都内にお住まいのAさん(50代男性)です。
「父が亡くなり、地方にある実家の土地を私が相続することになりました。しかし、先日その土地の登記情報を確認したところ、名義が会ったこともない曽祖父のままになっていることが判明しました。相続登記の義務化も始まったと聞き、どうすればよいか分からず相談に来ました。」
Aさんのお話によれば、その土地は代々長男が受け継いできたものの、祖父の代、父の代と、これまで一度も相続登記が行われていなかったとのこと。長年の懸案事項ではありましたが、手続きの煩雑さから、誰も手を付けられずにいたそうです。
放置された相続登記が抱える「3つの課題」
Aさんのケースのように、数世代にわたって相続登記が放置されると、主に次のような課題が生じます。
- 相続人の人数が増える
相続人の数がネズミ算式に増える本来であれば、曽祖父が亡くなった時点で祖父へ、祖父が亡くなった時点でAさんの父へ…と段階的に登記すべきでした。しかし、それを怠ったため、法律上の相続人は、本来相続するはずだった人(祖父、父)の相続人全員にまで広がってしまいます(これを数次相続といいます)。さらに、本来相続する人がすでに亡くなっている場合は、その子供(兄弟姉妹)が相続権を引き継ぐため、関係者の数がどんどん増えていくのです。 - 収集する書類が膨大になる
戸籍謄本の収集が極めて困難になる相続人を確定させるためには、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等が必要です。今回のケースでは、曽祖父、祖父、そして先に亡くなっていたAさんの叔父など、関係者全員の戸籍を集めなければなりません。古い戸籍は手書きで読みにくかったり、役所の統廃合で保管場所が変わっていたりと、収集には専門的な知識と多大な労力を要します。 - 相続人間の調整が難航する
相続人が確定したら、その全員で「誰がこの不動産を取得するのか」を話し合い、合意内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、全員分の実印と印鑑証明書をもらう必要があります。しかし、相続人が数十人にもなると、中には全く面識のない遠い親戚も含まれます。そのような方々に事情を説明し、協力を取り付けるのは、精神的にも大きな負担となります。
参考記事:遺産相続の最重要ポイント-遺産分割協議の知識と進め方
Aさんのケースも、まさにこの3つの課題をすべて抱えた、非常に複雑な案件でした。
解決までの流れ
当事務所では、Aさんから正式にご依頼を受け、次のステップで手続きを進めました。
ステップ1:相続関係の調査と相続人の確定(所要期間:約3ヶ月)
まず、すべての相続関係を明らかにするため、戸籍の収集から着手しました。 Aさんの曽祖父は明治時代生まれ。当時の古い戸籍や、本籍地の変更履歴を追いかけ、曽祖父の出生から死亡までの戸籍をすべて取得。そこから、祖父の代、父の代へと枝分かれしていく相続関係を一つひとつ辿っていきました。
地道な調査の結果、最終的に法律上の相続人は、Aさんを含め、総勢で23名いることが判明しました。相続人は、全国各地に散らばっていました。
この調査結果をもとに、相続関係を一覧にした「相続関係説明図」を作成し、Aさんと共有。ここで初めて、Aさんは手続きの全体像を正確に把握することができました。
ステップ2:全相続人への連絡と協力依頼(所要期間:約4ヶ月) 次に、確定した23名の相続人全員に対し、当事務所が文面を起案し、Aさんからお手紙を送付しました。 お手紙には、以下の内容を分かりやすく記載しました。
- 今回の相続登記の経緯(曽祖父名義のままになっていること)
- 法律上の相続人にあたること
- 手続きにご協力いただきたい旨のお願い
- 相続に関する意向の確認
ほとんどの方は事情を理解し、快く協力してくださいました。しかし、一部の方からは「なぜ今更?」「自分には関係ない」といった反応もありました。
そのような場合は、電話で丁寧に補足説明したり、資料を追完するなどして、最終的に相続人全員からの協力を取り付けることができました。
相続人全員の意向を確認したあとは、遺産分割協議書の作成と送付を行いました。
ステップ3:遺産分割協議書の作成と登記申請(所要期間:約1ヶ月) 全員分の署名・捺印と印鑑証明書が揃った遺産分割協議書をもとに、法務局へ提出する必要書類一式を整えました。収集した膨大な戸籍謄本や住民票なども、添付書類として整理します。
そして、すべての準備が完了した段階で、管轄の法務局へ「所有権移転登記」を申請。申請から約2週間後、無事に登記が完了し、不動産の名義は晴れて曽祖父からAさんへと移転されました。
解決後のお客様(Aさん)の声
「曽祖父の名義だと知ったときは、本当に途方に暮れました。相続人が20人以上もいると聞いたときは、正直、もう無理かもしれないと諦めかけました。しかし、司法書士さんが一つひとつ丁寧に戸籍を読み解き、全国の親戚に連絡を取ってくれたおかげで、長年の懸案だった実家の名義を、ようやく自分の代で整理することができました。もし一人でやろうとしていたら、間違いなく途中で挫折していたと思います。これで安心して、次の世代にこの土地を引き継ぐことができます。本当にありがとうございました。」
なぜ、放置された相続登記は専門家へ相談すべきなのか?
Aさんの事例からも分かるように、長年放置された相続登記は、ご自身で手続きを進めるには非常にハードルが高いと言えます。
- 時間と労力の節約: 戸籍の収集、法務局への相続登記の申請等の必要な手続きを、すべて専門家が代行します。
- 正確な相続人調査: 戸籍を正確に読み解き、相続人を漏れなく確定させます。
- 法的に有効な遺産分割協議書の作成: 後のトラブルを防ぐため、法律上有効な遺産分割協議書を作成します。
- 円滑な人間関係の維持: 第三者である専門家が間に入ることで、相続人間の感情的な対立を避け、冷静な話し合いを進めやすくなります。
ご自身で手続きを進めようとして、途中で挫折し、結局当事務所にご相談に来られるケースも少なくありません。最初から専門家に任せることが、結果的に最も確実で、時間や費用、そして精神的な負担を軽減する近道となります。
まとめ:相続登記の悩みは、一人で抱え込まずにご相談を
相続登記の義務化は、これまで先延ばしにしてきた不動産の問題と向き合う、またとない機会です。
「うちの土地も、名義がどうなっているか分からない…」
「相続人がたくさんいそうで、手続きが不安…」
もし、少しでもこのように感じたら、まずは一度、お近くの司法書士に相談してみてください。現状を整理し、解決までの道筋を明確にするだけでも、漠然とした不安は解消されるはずです。
当事務所では、今回ご紹介したような複雑な相続案件にも豊富な経験があります。初回のご相談は無料で承っておりますので、お一人で抱え込まず、お気軽にお問い合わせください。







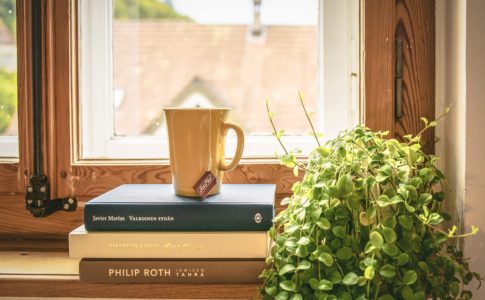














コメントを残す