「自分には大した財産はないから、遺言なんて必要ない」
「家族の仲は良いから、相続で揉めるはずがない」
多くの方が、このように考えていらっしゃるかもしれません。しかし、それは本当に大丈夫でしょうか?
相続は、誰の身にも必ず訪れる出来事です。そして、相続手続きの中心となるのが「遺産分割協議」です。これは、亡くなった方(被相続人)の財産を、相続人全員で話し合って分ける手続きを指します。
この協議が円満に進めば問題ありません。しかし、相続人が遠方に住んでいたり、感情的な対立が生まれたりして、話し合いが長期化することは決して珍しくありません。
家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割調停の約75%は、遺産総額が5000万円以下の「ごく普通の家庭」で起きています(裁判所「司法統計」より)。財産の多少にかかわらず、相続は誰にとってもトラブルの火種になり得えます。
こうしたトラブルの火種を避けるために有効な手段が「遺言」です。
この記事では、司法書士の視点から、遺言を残すことの具体的なメリットを5つ、分かりやすく解説していきます。この記事を読み終える頃には、遺言が「お金持ちのための特別なもの」ではなく、「ごく普通の一般家庭にとって必要なもの」であることがお分かりいただけると思います。
目次
メリット1:相続トラブルの最大の火種「遺産分割協議」を省略できる
遺言を残す最大のメリットは、何と言っても相続トラブルの最大の原因となり得る「遺産分割協議」を原則として省略できる点にあります。
なぜ遺産分割協議は大変なのか?
遺言がない場合、相続手続きは以下の流れで進みます。
- 相続人の確定:亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等を取り寄せ、誰が相続人になるのかを確定させます。
- 相続財産の調査:預貯金、不動産、有価証券など、全ての財産を調査し、財産目録を作成します。
- 遺産分割協議:相続人全員で、財産の分け方を話し合います。
- 遺産分割協議書の作成:合意した内容を書面にし、相続人全員が署名し、実印を押印します。
- 名義変更等の手続き:遺産分割協議書に基づき、銀行や法務局で手続きを行います。
この中で最も時間と労力がかかり、精神的な負担が大きいのが「3.遺産分割協議」です。
- 全員参加が必須:相続人の一人でも欠けたり、合意しなかったりすると協議は成立しません。連絡が取りづらい相続人がいるだけで、手続きは滞ってしまいます。
- 感情的な対立:「親の介護を一番頑張ったのは私だ」「長男なのだから多くもらうのが当然だ」など、お金の問題に過去の感情が絡み合い、冷静な話し合いが難しくなるケースが多くあります。
- 「ハンコ代」の要求:不動産を特定の相続人が相続する代わりに、他の相続人に代償金を支払うといった場面で、金額を巡って対立が深まることもあります。
遺言があれば、財産の分け方が明確に指定されているため、この大変な協議を経ずに手続きを進めることができます。これは、残されたご家族にとって、大きな時間的・精神的負担の軽減に繋がるのです。
メリット2:自分の意思で財産の分け方を自由に決められる
民法では、誰がどのくらいの割合で財産を相続するかの目安として「法定相続分」を定めています。例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合、配偶者が1/2、子供がそれぞれ1/4ずつとなります。
しかし、ご家庭の事情は様々です。「法定相続分」が、必ずしもご自身の想いやご家族の実情に合っているとは限りません。
遺言があれば、この法定相続分にとらわれず、ご自身の意思で自由に財産の分け方を指定できます。
具体的な活用ケース
- 長年連れ添った配偶者の生活を保障したい「私が亡くなった後も、妻(夫)には今の家で安心して暮らし続けてほしい。預貯金も多めに残してあげたい」という想いを実現できます。
- 家業や農業を継ぐ子供を支援したい事業に必要な会社の株式や、農地、事業用の不動産などを、後継者である特定の子供に集中して相続させることができます。これにより、事業の継続がスムーズになります。
- 特に世話になった子供に報いたいご自身の介護を献身的に行ってくれた子供に対し、感謝の気持ちとして他の子供より多くの財産を渡すことができます。
- 障がいのある子の将来のために他の子供たちよりも多くの財産を残すことで、将来の生活基盤を支えてあげたい、という親心も形にできます。
ただし、兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の取り分を主張できる「遺留分」という権利があります。遺言を作成する際は、この遺留分にも配慮することで、より円満な相続の実現に繋がります。
参考記事:【図表付き】遺留分の割合、計算方法をケース別に解説
メリット3:相続人以外の大切な人にも財産を渡せる(遺贈)
遺言の素晴らしい機能の一つに「遺贈(いぞう)」があります。これは、法定相続人ではない人に財産を譲ることを可能にするものです。
遺贈の具体的な活用ケース
- 内縁の妻(夫)や事実婚のパートナーへ法律上の婚姻関係になくても、長年人生を共にしてきた大切なパートナーに財産を残し、今後の生活を支えることができます。
- 息子の妻(お嫁さん)へ「いつも息子のことを支え、自分のことも気遣ってくれた優しいお嫁さんに、感謝の気持ちとして財産の一部を遺したい」という想いを実現できます。
- お世話になった友人や知人へ闘病生活を支えてくれた友人や、事業で助けてくれた恩人など、血縁関係はなくても感謝を伝えたい人に財産を贈ることができます。
- 社会貢献(寄付)お世話になった母校や、応援しているNPO法人、地域の福祉施設などに寄付をすることも可能です。ご自身の財産を社会のために役立てるという、最後の社会貢献も遺言によって実現します。
このように、遺言は血縁を超えて、遺言者の遺志を実現する手段となります。
メリット4:相続手続きそのものの負担を大幅に軽減できる
遺言がない場合、残されたご家族は、銀行口座の解約や不動産の名義変更(相続登記)のために、多くの書類を集めなければなりません。
しかし、遺言書(特に公正証書遺言)で「遺言執行者」を指定しておけば、この手続きの負担を劇的に減らすことができます。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う権限を与えられた人のことです。遺言執行者は、単独で預金の解約や不動産の名義変更などの手続きを進めることができます。
つまり、他の相続人から実印や印鑑証明書をもらう必要がなくなるため、手続きが非常にスムーズかつ迅速に進みます。
参考記事:【司法書士監修】遺言執行者とは?遺言を確実に実現するキーパーソンを徹底解説
メリット5:家族への想いを形にして伝えられる(付言事項)
遺言は、財産の分け方を記すだけの事務的な書類ではありません。「付言事項(ふげんじこう)」として、ご家族への最後のメッセージを書き残すことができます。
付言事項には法的な効力はありませんが、多くの専門家がその重要性を指摘しています。なぜなら、お金では解決できない「感情」の部分を和らげる効果があるからです。
付言事項で伝えられること
- 財産分与の理由「なぜ、このような分け方にしたのか」その理由や背景にある想いを伝えることで、相続人の間に生まれがちな不公平感を和らげ、納得を促すことができます。(例:「妻には、これからの人生を安心して過ごしてほしいという想いから、自宅不動産を相続させます。子供たちはどうか理解してください」)
- 家族への感謝の言葉 「今まで本当にありがとう」「あなたたちが居てくれて幸せでした」といった素直な感謝の気持ちを記すこともできます。
- これからの人生へのエール「これからは兄弟で力を合わせ、お母さんを支えてあげてほしい」「それぞれの夢に向かって、自分らしい人生を歩んでください」といったメッセージは、残された家族の心の支えとなるでしょう。
財産という「結果」だけが残されると、時に誤解や憶測を生みます。そこにあなたの「想い」という言葉が添えられることで、遺言は単なる指示書から、家族の絆を未来へ繋ぐ温かい「手紙」へと変わるのです。
まとめ:遺言は、未来の家族を守る「お守り」です
ここまで、遺言を残す5つのメリットについて解説してきました。
- 遺産分割協議を省略でき、相続トラブルを未然に防げる
- 法定相続分にとらわれず、自分の意思で財産を分けられる
- 相続人以外の大切な人にも財産(感謝)を届けられる
- 面倒な相続手続きの負担を、家族のために軽くしてあげられる
- 最後のメッセージで、家族への想いを伝え、絆を深められる
遺言を作成することは、決して縁起の悪いことではありません。また、特別な資産家だけが行うものでもありません。
それは、ご自身が人生の最後に示す、ご家族への愛情であり、責任です。残された大切なご家族が、お金のことで争うことなく、円満に、そしてスムーズに新しい一歩を踏み出すための「お守り」と言えるでしょう。
ご自身の想いを確実な形で残し、未来の家族を守るために、元気な今のうちから「遺言」について考えてみてはいかがでしょうか。







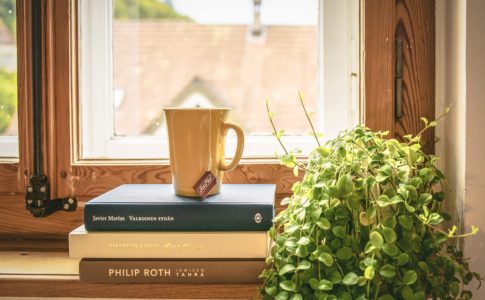







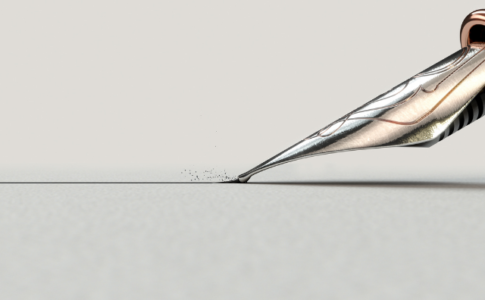
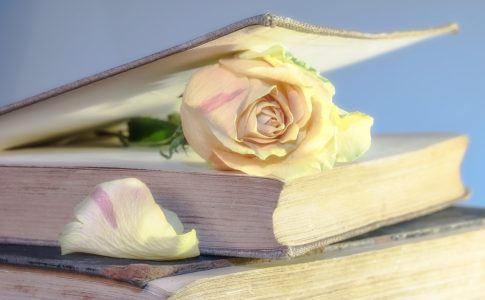





コメントを残す