「自分の死後、残された家族が揉めないように…」
「お世話になったあの人に、確実に財産を渡したい」
こうした想いを込めて遺言書を作成する方は年々増えています。しかし、遺言書は「書けば終わり」ではありません。その内容を法的に実現するための手続き、いわゆる「相続手続き」が待っています。
この大切な手続きをスムーズに進めるために、非常に重要な役割を担うのが「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」です。
おそらく、ほとんどの方が初めて耳にする言葉でしょう。しかし、遺言執行者を指定しておくかどうかで、ご自身の最後の意思がスムーズに実現されるか、はたまた相続トラブルに発展してしまうかの分かれ道になることさえあります。
この記事では、相続の専門家である司法書士の視点から、「遺言執行者」とは何なのか、その役割、権限、選び方から費用まで、網羅的にそして分かりやすく解説していきます。ご自身の遺言書を完璧なものにするため、ぜひ最後までお付き合いください。
目次
1:遺言執行者とは? – 遺言を「絵に描いた餅」にしないために
1-1. 遺言執行者の基本的な役割
遺言執行者とは、一言でいえば「遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う権限を与えられた人」です。
亡くなった方(被相続人)の最後の意思を、その方に代わって法的に実現していく、いわば「遺言内容実現の総責任者」のような存在です。
通常、相続手続きは相続人全員が協力して行います。しかし、相続人が複数いる場合、全員の足並みがそろうとは限りません。
- 仕事が忙しくて手続きに参加できない相続人
- 遠方に住んでいて物理的に協力が難しい相続人
- 遺言の内容に不満があり、手続きに非協力的な相続人
このような状況では、手続きが停滞し、最悪の場合、遺言書があるにもかかわらず内容が実現されないという事態に陥りかねません。
そこで登場するのが遺言執行者です。遺言執行者がいれば、相続人に代わって、単独で銀行預金の解約や不動産の名義変更(相続登記)などの手続きを進めることができます。
1-2. なぜ遺言執行者が必要なのか?
法律上、遺言執行者は必ずしも置かなければならないわけではありません。しかし、遺言執行者を指定しておくことで、以下のような多くのメリットが生まれます。
- 手続きの迅速化・円滑化: 専門家などを指定すれば、複雑な手続きもスムーズに進みます。相続人が自ら行う場合に比べ、時間的・精神的負担が大幅に軽減されます。
- 相続人間のトラブル防止: 第三者である専門家が中立的な立場で手続きを進めるため、相続人間の感情的な対立や憶測による争いを未然に防ぎます。「兄さんが財産を独り占めしているのではないか」といった疑心暗鬼を生む余地がなくなります。
- 相続人の負担軽減: 相続手続きには、戸籍謄本の収集、財産調査、金融機関や法務局での手続きなど、多くの手間と時間がかかります。遺言執行者はこれらの煩雑な手続きをすべて引き受けてくれます。
- 遺言内容の確実な実現: 特に「遺贈(いぞう)」や「子の認知」など、遺言執行者でなければ実現が難しい、あるいは不可能な手続きもあります。
遺言書は、故人の最後のメッセージです。そのメッセージを確実に届けるための「配達人」が遺言執行者であるとイメージすると分かりやすいかもしれません。
2:特に遺言執行者が必要となる5つのケース
遺言執行者の重要性はご理解いただけたかと思います。では、具体的にどのような場合に遺言執行者を指定しておくべきなのでしょうか。特に必要性が高い5つのケースをご紹介します。
ケース1:相続人同士の仲が悪い、または疎遠である
残念ながら、相続をきっかけに家族関係が悪化するケースは少なくありません。少しでも相続人間の関係に不安がある場合は、遺言執行者の指定を推奨します。公平な第三者が介入することで、冷静な手続き進行が期待できます。
ケース2:相続人以外に財産を渡したい(遺贈)
「内縁の妻に財産を残したい」「お世話になった友人に一部を譲りたい」といったように、相続人ではない個人や団体に財産を渡すことを「遺贈(いぞう)」といいます。
この遺贈の手続きは、相続人全員の協力がなければ進めることができません。もし相続人の一人が「なぜ赤の他人に財産を渡すのか」と反対すれば、手続きはストップしてしまいます。
このような事態を防ぐため、遺言執行者を指定しておくことが極めて重要です。遺言執行者がいれば、他の相続人の同意なく、受遺者(財産を受け取る人)への名義変更手続きなどを進めることができます。
ケース3:子の認知や、相続人の廃除・取消しをしたい
遺言では、財産に関することだけでなく、身分に関する行為も定めることができます。
- 子の認知: 婚姻関係にない男女間に生まれた子を、自分の子として法的に認めることです。遺言で認知をする場合、遺言執行者はその就任の日から10日以内に、役所へ認知の届出をしなければなりません。
- 相続人の廃除・取消し: 被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行った相続人から、相続権を剥奪する(廃除)こと、またそれを取り消す(廃除の取消し)ことです。遺言でこれを行う場合、遺言執行者は遅滞なく家庭裁判所にその申立てをする必要があります。
これらの身分行為は、遺言執行者のみが行うことができると解されており、指定が必須となります。
参考記事:非行を繰り返す息子に相続させない方法はある?相続人の廃除とは
ケース4:相続財産が複雑・多岐にわたる
不動産、預貯金、株式、投資信託、ゴルフ会員権など、相続財産の種類が多いほど手続きは複雑になります。特に、非上場の自社株や、複数の場所に不動産がある場合などは、専門的な知識が不可欠です。専門家を遺言執行者に指定しておけば、これらの財産も正確に評価し、適切に手続きを進めてくれます。
ケース5:相続人が高齢、病気、海外在住など
相続人自身が高齢であったり、大きな病気を患っていたり、あるいは海外に住んでいる場合、日本の役所や金融機関を回って手続きをすることは大きな負担となります。遺言執行者を指定しておくことは、そうした相続人への最後の思いやりとも言えるでしょう。
3:誰を遺言執行者に選ぶべきか?
では、具体的に誰を遺言執行者にすればよいのでしょうか。法律上の資格と、それぞれの選択肢のメリット・デメリットを見ていきましょう。
3-1. 遺言執行者になれる人
法律上、以下の2つの条件に当てはまらなければ、誰でも遺言執行者になることができます。法人(会社や信託銀行など)もなることが可能です。
- 未成年者ではないこと
- 破産者ではないこと
つまり、資格さえ満たせば、友人や知人はもちろん、相続人の一人を遺言執行者に指定することも可能です。
3-2. 選択肢ごとのメリット・デメリット
主な選択肢として「相続人」「信頼できる親族・知人」「専門家」が考えられます。
| 選択肢 | メリット | デメリット |
| 相続人(長男など) | ・報酬が不要な場合が多い ・財産状況を把握していることが多い | ・他の相続人から不公平感を抱かれやすい ・手続きの知識がなく、負担が大きい ・感情的対立が起きやすい |
| 信頼できる親族・知人 | ・報酬が不要または低額な場合がある ・気兼ねなく頼める | ・相続に関する専門知識がない ・責任の重さから断られる可能性がある ・万が一のトラブル対応が難しい |
| 専門家(司法書士・弁護士など) | ・中立・公平な立場で執行する ・専門知識で手続きが迅速・正確 ・相続人間の調整役となりトラブルを防ぐ ・法的な責任を負ってくれる安心感 | ・報酬(費用)がかかる |
| 信託銀行など | ・組織として永続的な対応が期待できる ・豊富な実績とノウハウがある | ・報酬が比較的高額になる傾向がある ・一定額以上の財産がないと引き受けない場合がある |
3-3. なぜ「司法書士」が遺言執行者におすすめなのか
無用なトラブルを避け、確実に遺言を実現するためには、第三者である専門家、特に司法書士を遺言執行者に指定することをおすすめします。その理由は以下の通りです。
- 不動産相続登記の専門家であること: 相続財産に不動産が含まれる場合、法務局での名義変更手続き(相続登記)が必須です。司法書士は登記のプロフェッショナルであり、最もスムーズかつ確実に手続きを完了させることができます。
- 相続手続き全般に精通していること: 司法書士は登記だけでなく、預貯金や株式の名義変更、遺産分割協議書の作成など、相続に関する幅広い手続きに対応しています。ワンストップで相続手続きを任せられる安心感があります。
- 中立性と倫理観: 司法書士は高い倫理規定のもと、特定の相続人の利益に偏ることなく、故人の意思と法律に基づき、中立・公正な立場で職務を執行します。
- 費用の透明性・妥当性: 弁護士に比べて、一般的に司法書士の報酬はリーズナブルな傾向があります。もちろん事案によりますが、費用を抑えつつ専門家のサポートを受けたい場合に適しています。
遺言書の作成相談から、その後の執行までを一貫して同じ司法書士に依頼することで、あなたの想いを深く理解した上で、最後まで責任をもって手続きを進めてもらうことが可能になります。
4:遺言執行者の強力な権限と重い責任(義務)
遺言執行者は、その任務を遂行するために、法律で非常に強い権限を与えられています。同時に、それに見合う重い責任も負っています。
4-1. 遺言執行者の強力な権限
民法には、遺言執行者の権限について次のように定められています。
民法 第1012条(遺言執行者の権利義務)
1.遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
この「遺言の執行に必要な一切の行為」とは、具体的に以下のような職務を指します。
- 就任の通知: 全ての相続人および受遺者に対し、遺言執行者に就任したことと遺言の内容を通知します。
- 相続財産の調査・財産目録の作成: 故人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も)をすべて調査し、一覧にした「財産目録」を作成して相続人に交付します。
- 預貯金の解約・払い戻し: 各金融機関で、相続人全員の印鑑をもらうことなく、単独で預貯金の解約や名義変更手続きができます。
- 不動産の名義変更(相続登記): 法務局に対し、単独で不動産の名義を相続人や受遺者に変更する登記申請ができます。
- 株式など有価証券の名義変更: 証券会社などで名義変更手続きを行います。
- 遺贈の履行: 遺言に従い、相続財産を相続人や受遺者に引き渡します。
- 子の認知の届出、相続人廃除の申立てなど
- 任務完了の報告: すべての任務が完了したら、相続人にその経過と結果を報告します。
さらに、この権限を実効的なものにするため、相続人の行動を制限する規定も存在します。
民法 第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)
1.遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
つまり、遺言執行者がいるにもかかわらず、相続人が勝手に遺産である預金を下ろしたり、不動産を売却したりすることはできないのです。もしそのような行為をしても、法的には無効となります(ただし、事情を知らない第三者には対抗できない場合があるため注意は必要です)。
4-2. 遺言執行者の責任(義務)
強い権限を持つ一方で、遺言執行者は次のような義務を負います。
- 善管注意義務(善良な管理者の注意義務): 自分の財産を管理するのと同じレベルではなく、専門家として、あるいはその地位にある者として通常期待されるレベルの注意をもって、財産を管理し職務を遂行する義務です。
- 報告義務: 相続人から請求があったときは、いつでも執行の状況を報告しなければなりません。
- 財産目録の作成・交付義務: 遅滞なく財産目録を作成し、相続人に交付する義務があります。
これらの義務を怠り、相続人に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負う可能性もあります。専門家が遺言執行者となる場合は、こうした重い責任も理解した上で職務にあたっています。
5:遺言執行者の選任方法と就任後の流れ
遺言執行者を定める方法は、大きく分けて2つあります。
5-1. 方法1:遺言書で指定する(最も一般的)
最も一般的で、かつ推奨される方法が、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことです。
【遺言書の記載例】
第〇条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所 静岡市葵区〇〇一丁目2番3号
氏名 司法書士 法務 太郎(ほうむ たろう)
生年月日 昭和〇〇年〇月〇日
このように、住所・氏名・生年月日・職業などを記載して、個人が特定できるように明記します。専門家に依頼する場合は、その事務所の所在地や連絡先も書いておくとより親切です。
また、指定した人が先に亡くなったり、病気で職務が行えなくなったりするケースに備え、予備的な遺言執行者を指定しておくことも可能です。
【予備的指定の記載例】
第〇条
1.(前項と同じ)
2.前項の者が遺言者より先にまたは同時に死亡した場合、あるいは遺言執行者の就職を承諾しない場合、その他任務遂行が困難な事情がある場合は、次の者を遺言執行者に指定する。 (以下、予備者の情報を記載)
5-2. 方法2:家庭裁判所に選任してもらう
遺言書に遺言執行者の指定がない場合や、指定された人が就任を断った場合など、利害関係者(相続人、受遺者、債権者など)は家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を申し立てることができます。
- 申立先: 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 主な必要書類: 申立書、遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本、遺言書の写し、利害関係を証明する資料(戸籍謄本など)、遺言執行者候補者の住民票など
- 費用: 収入印紙800円分、連絡用の郵便切手代
ただし、この手続きは時間と手間がかかります。誰を候補者にするかで揉める可能性もあり、必ずしも希望通りの人が選任されるとは限りません。やはり、あらかじめ遺言書で信頼できる人を指定しておくのが最善策です。
6:気になる遺言執行者の費用(報酬)について
専門家に遺言執行を依頼する際に、最も気になるのが費用(報酬)でしょう。報酬については、明確な法定料金はなく、いくつかの方法で決まります。
6-1. 報酬の決定方法
- 遺言での指定: 遺言書の中で「遺言執行者の報酬は金〇〇円とする」と具体的に定めることができます。
- 相続人との協議: 遺言に定めがない場合、遺言執行者と相続人全員との協議によって報酬額を決定します。
- 家庭裁判所の審判: 協議が整わない場合は、家庭裁判所が、遺産の状況や職務の難易度などを考慮して報酬額を決定します。
一般的には、専門家に依頼する場合、その専門家が定める報酬基準に基づいて協議が行われます。
6-2. 専門家ごとの報酬相場
報酬体系は事務所によって様々ですが、一般的には「遺産総額に応じた料率」で計算されることが多いです。
| 専門家 | 報酬の目安 |
| 司法書士 | ・30万円~100万円程度 ・遺産総額の0.5%~1.5%程度が目安 ・最低報酬額(例:30万円)が設定されていることが多い |
| 弁護士 | ・30万円~ ・遺産総額の1%~3%程度が目安 ・旧弁護士会報酬規程を参考にしている事務所が多い |
| 信託銀行 | ・最低報酬額100万円~ ・遺産総額に応じて段階的に料率が下がる体系が多い(例:5000万円まで2.2%、1億円まで1.65%など) |
※上記はあくまで一般的な目安です。財産の額や種類、手続きの複雑さ、相続人の数などによって変動します。
※別途、不動産登記の登録免許税や戸籍謄本取得などの実費がかかります。
司法書士に依頼する場合、比較的費用を抑えつつ、質の高いサービスが期待できます。ご依頼を検討される際は、必ず事前に見積もりを取り、報酬体系やサービス内容について十分な説明を受けるようにしましょう。
参考記事:相続の相談は、税理士?弁護士?司法書士?あなたにあった専門家の選び方
まとめ:遺言書は「実現」まで考えて作成しましょう
最後に、この記事の要点をもう一度確認しましょう。
- 遺言執行者は、遺言内容を実現するための手続きを単独で行える強い権限を持つ人。
- 特に、相続人間の仲が悪い、相続人以外への遺贈がある、子の認知があるといったケースでは指定が不可欠。
- 相続人も遺言執行者になれるが、トラブル防止と手続きの円滑化のためには、司法書士などの専門家に依頼するのが最も安全で確実。
- 遺言執行者は、財産目録の作成、預貯金解約、不動産登記など、遺言実現に必要な一切の行為を行う。
- 選任は遺言書で行うのがベスト。家庭裁判所への申立ても可能だが手間がかかる。
- 専門家への報酬はかかるが、それに見合う安心と時間、そして円満な相続を手に入れることができる。
遺言書は、確実に実現されてこそ、真の意味で完成します。
そのための最も賢明な選択が、「遺言執行者の指定」です。 もし遺言書の作成や遺言執行者について、少しでもご不安やご不明な点があれば、相続の専門家である司法書士にご相談ください。あなたの想いに寄り添い、最善の解決策をご提案いたします。





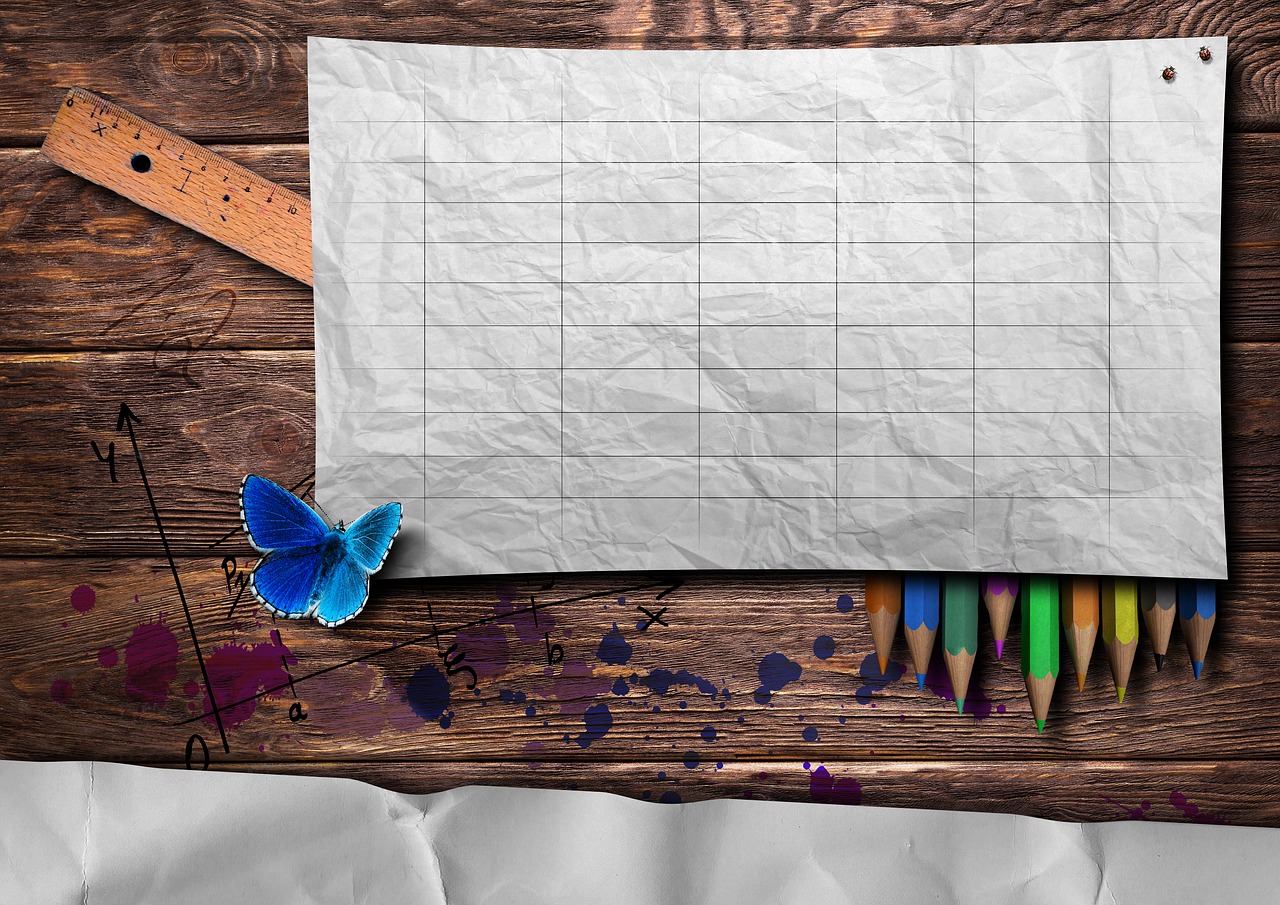

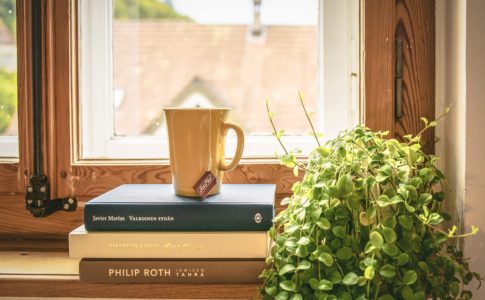






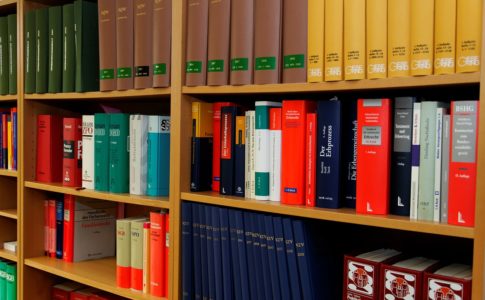



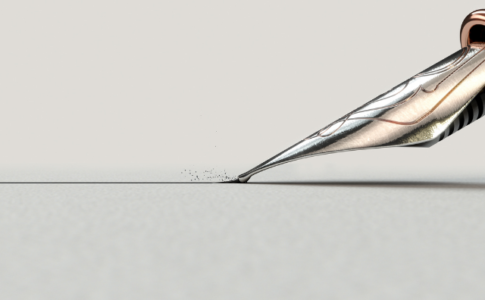



コメントを残す