1.もしも、遺言書に“自宅”と書いてあったら?
遺言書の本に「不動産は登記簿の通りに書きましょう」と書いてあるのを見かけたことがありますか?これって、登記簿を見慣れていない方には違和感を感じるところと思います。
なぜ、このように書かれているのでしょうか。遺言書の使い道から考えてみましょう。
遺言書は、自分が死んだ後にその内容“自分の遺志”を実現してもらうためのものです。遺言書の内容実現のために動いてくれる人のことを、遺言執行者といいます。すなわち、遺言執行者が遺言の内容を円滑に実現できるほうが、より理想的な遺言書といえるでしょう。
例えば、私が「私名義の自宅の土地(X土地と呼びます)を、孫の甲さんに引き継いでもらいたい。」と考えて、遺言書を書きました。この時、下記のA、Bどちらがより理想的な遺言書の書き方だと思いますか?
- A「自宅の土地は甲さんにあげる」
- B「私が所有する土地は甲さんにあげる」
より、理想的なのはBです。
2.遺言書における不動産の特定の重要性
私が死んだ後、甲さんがAの遺言書を法務局に持ち込んで、遺言書にこう書いてあるから、X土地の登記名義を書き換えてくれ、といってもすんなりとは受け付けてくれません。なぜでしょうか?その理由は、自宅とは、どこを指しているのかわからないから、です。
「いや、自宅と書いてあるのだから、住民票の住所で特定できるでしょう。」と、鋭い指摘が飛んできそうです。住民票をよ~く見てください。どこにも自宅とは書いてありません。
一方Bは、どうでしょう。「私が所有する」と書いてあれば、登記簿をみて、登記名義人になっている土地を特定できます。これならば、受け付けてくれるというわけです。
3.遺言書を介して遺言者の想いに心をよせる
ちょっとした言葉の違いですが、結果は大きく違います。
ちなみにAの場合、相続人の全員に、「X土地は甲さんが遺贈を受けたことに相違ありません」という内容の書類を書いてもらえば、名義変更を受け付けてくれます。遺言書として無効というわけではありませんので、決して捨てたりしないでくださいね。遺言書に込められた遺言者の想いに想像を巡らせるのは、素敵なことだと思います。
ちなみに、一番確実なのは、登記簿の通りに書くことです。登記簿の文字数は土地1個当たり30~40文字、建物70~80文字です。「私が所有する」は6文字です。この差は病床の方や高齢で手の力が弱っている方には、大きな差となるでしょう。
















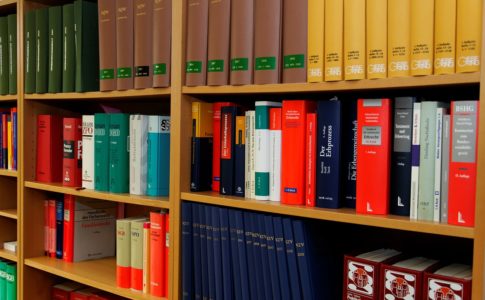





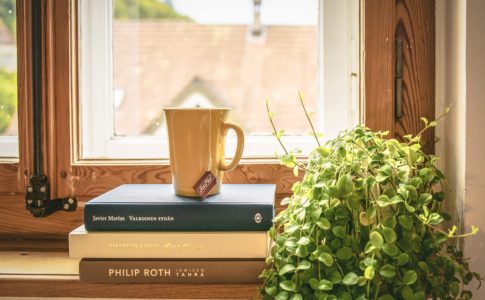



コメントを残す